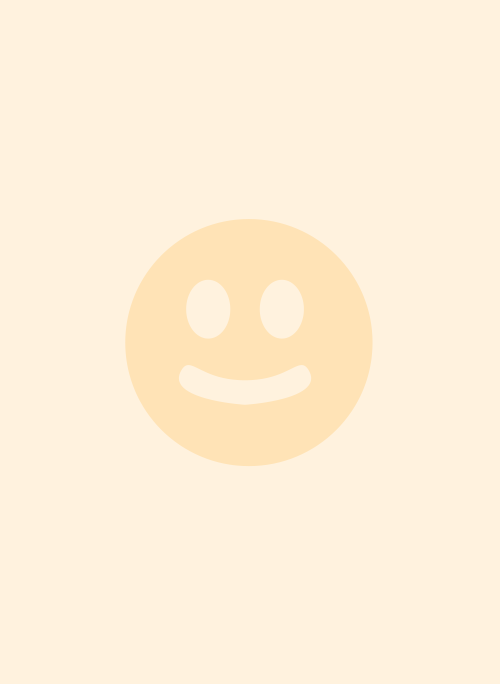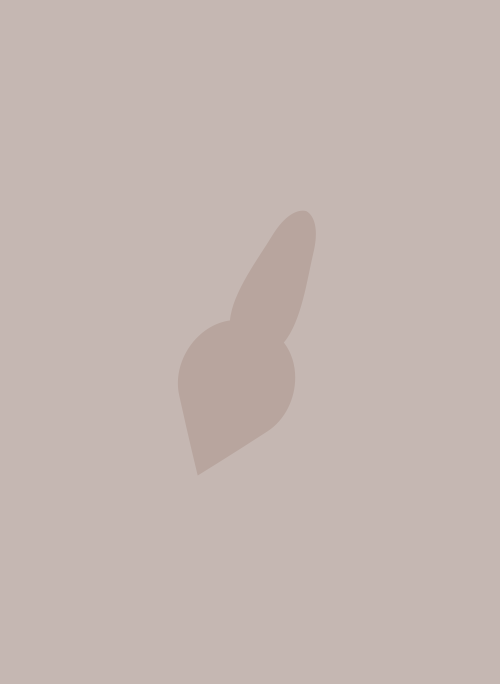心ない方たちは、陰でそんなことを言って私を罵った。
その度にお姉ちゃんやお父さんやお母さんは、『優姫は、私たちの天使なのよ』と笑ってくれた。
でも、もう言ってくれる人はいなくなってしまった。
本気で、私は死神なんじゃないかと思い始めた。
「私…」
生まれてこなければよかったの―――?
目の前がゆらゆらと揺らいできたその時、周りがザワザワとざわついた。
「君が…一条 優姫さんだね?」
「?」
後ろから声をかけられ、振り向いた瞬間に見えたのは、整った顔に悲しげで優しい笑みを浮かべた、男の人だった。
「貴方…は?」
「僕は、白石 完(シライシ タモツ)。君のお姉さんである、一条 陽姫さんの婚約者です」
びっくりした。
私は、今までお姉ちゃんの婚約者さんを見たことがなかったからだ。
「今回は、本当に…残念でした。まさか陽姫が…こんなに早く亡くなるとは…。悲しすぎて、涙さえ枯れ果て、凍り付きました」
そう言って彼はまたにっこりと笑ったが、カタカタと震える手と涙で潤んだ赤く腫れぼったい目が、それを嘘の笑顔だと主張していた。
その度にお姉ちゃんやお父さんやお母さんは、『優姫は、私たちの天使なのよ』と笑ってくれた。
でも、もう言ってくれる人はいなくなってしまった。
本気で、私は死神なんじゃないかと思い始めた。
「私…」
生まれてこなければよかったの―――?
目の前がゆらゆらと揺らいできたその時、周りがザワザワとざわついた。
「君が…一条 優姫さんだね?」
「?」
後ろから声をかけられ、振り向いた瞬間に見えたのは、整った顔に悲しげで優しい笑みを浮かべた、男の人だった。
「貴方…は?」
「僕は、白石 完(シライシ タモツ)。君のお姉さんである、一条 陽姫さんの婚約者です」
びっくりした。
私は、今までお姉ちゃんの婚約者さんを見たことがなかったからだ。
「今回は、本当に…残念でした。まさか陽姫が…こんなに早く亡くなるとは…。悲しすぎて、涙さえ枯れ果て、凍り付きました」
そう言って彼はまたにっこりと笑ったが、カタカタと震える手と涙で潤んだ赤く腫れぼったい目が、それを嘘の笑顔だと主張していた。