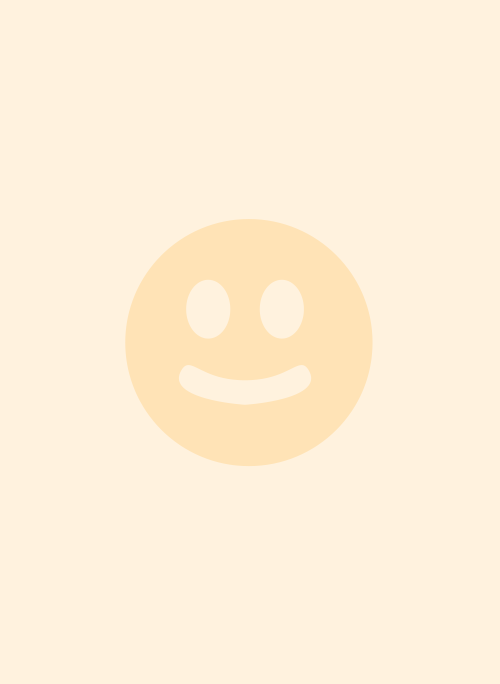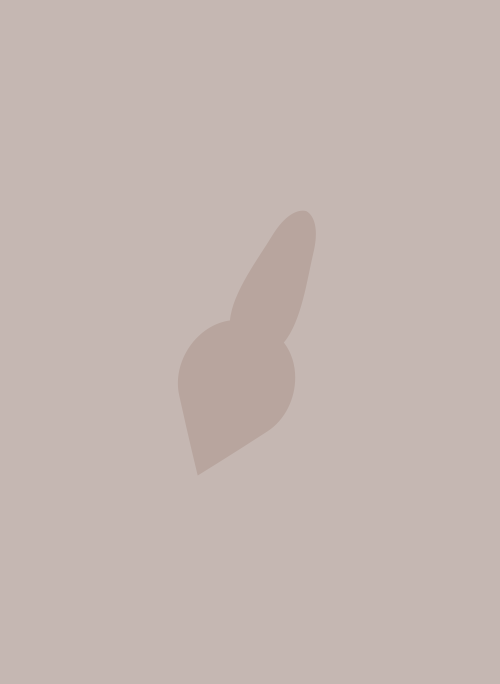俺はその可愛すぎるお腹の音にふっと軽く吹き出し、真っ赤になってうつむくお嬢様の頭を撫でた。
「お嬢様、私もお腹が空きましたので、食堂に参りましょう?」
俺がそう言うと、彼女はパァッと顔を明るくして、こっくりと頷いた。
「では参りましょう、」
彼女の手を取り、半歩先を歩く。
お嬢様はそれに慣れないような顔をなさりながらも俺の後をちょこちょこ着いて来てくださる。
何故だろうか。
人とは、こんなにも愛しい生き物なのか。
俺はお嬢様を見ながら、そう思った。
「お嬢様、私もお腹が空きましたので、食堂に参りましょう?」
俺がそう言うと、彼女はパァッと顔を明るくして、こっくりと頷いた。
「では参りましょう、」
彼女の手を取り、半歩先を歩く。
お嬢様はそれに慣れないような顔をなさりながらも俺の後をちょこちょこ着いて来てくださる。
何故だろうか。
人とは、こんなにも愛しい生き物なのか。
俺はお嬢様を見ながら、そう思った。