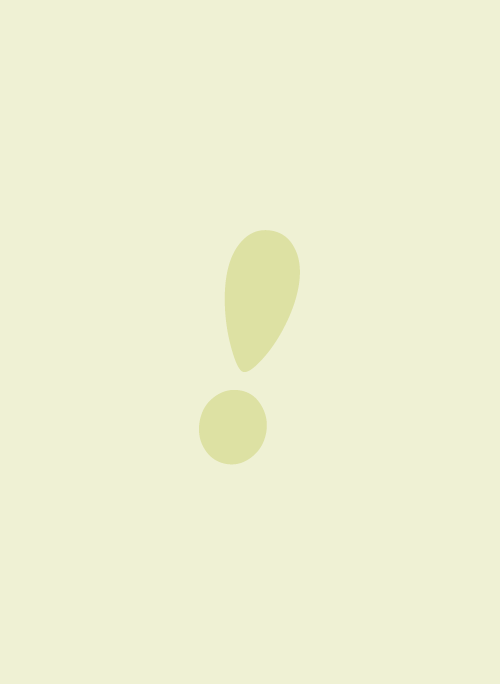まるで私が押し倒したような形で、全くんが下敷きに。
自分のしてしまったことにドキドキしていたが、すぐに我に返る。
「あっ、全くんごめん、大丈夫っ?」
急いで私は起き上がったのだが、返事がない。
「全くん?…」
肩の辺りを軽く揺すってみる。
しかしやはり返事はない。
その時、
彼の肩を揺する私の手に、ぬるりとした生暖かい液体が触れた。
全くんの頭部から出てきたもののようだった。
月明かりと、職員室の明かりしか見えない、暗い夜の中庭。
全くんの頭の下には、とがった大きな石の感触。
石はみるみる黒く染まっていった。
周りの芝生にも、石の感触を確かめた私の手にも、生ぬるい液体が広がる。
混乱した頭の中、私にできたのは
狂ったような悲鳴を上げることだけだった――