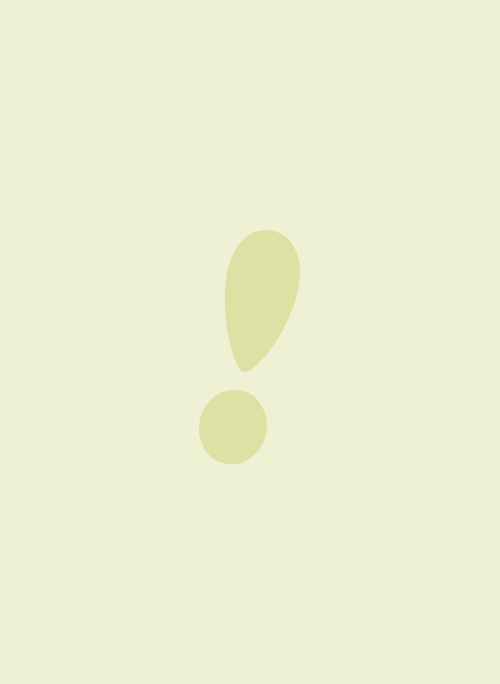「その人が教えてくれたんだ。人は死んだら星に、そして還ってくる時は流れ星になるって」
だんだん、車の通りが減って、風が強くなってきた。
その時、全くんはかすかに身震いした。
私は、全くんが着せてくれた紺のカーディガンを脱ぎ、彼の肩にかけた。
「汗かいた体、冷やすのよくないよ。風邪ひいちゃう」
「…さんきゅ。でも、ツバサは寒くないのか?」
「守ってもらった体、大切にしなきゃダメじゃん」
私は優しく言った。
全くんは、6歳で失った初恋の相手を、未だに忘れてはいない。
その証拠に、彼はまだその人を探している。
星になったんだと信じて…
この無数の星達の中から。
私達は、自転車をおしてゆっくり歩いて帰った。
全くんが疲れた様子だったからだ。
来るときは、一緒に流れ星になれそうなくらい近かった距離が、
夜風にさらされて尚遠ざかっていくように思えた。