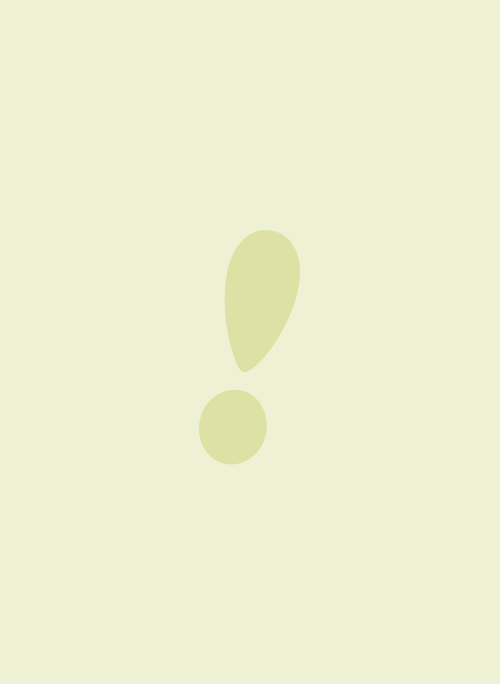「高遠、先生だ。わかるか?」
高遠は微笑んで静かに頷き、口元を僅かに動かした。
何か言いたそうだ。
しかし酸素マスクが邪魔をして、声が聞こえない上、息を漏らす度に白く曇って口元が隠れてしまう。
それでも、精一杯高遠の声を聞き取ろうとする。
「…し…」
「…ほし…が」
星?
「星か?星がどうかしたのか?」
それを聞いた高遠は、ふっと柔らかく笑った。
…彼女のことを、思い出しているのだろうか。
高遠が何を言いたかったのかは分からない。
それでも、昨日よりも確実に元気になっているということは、素人目でも明らかだった。
昨日の今日で、一体何故…
面会を終え、俺は医師と再び話をした。
「渡さんは、高遠くんの担任の先生なんですよね」
「ええ、そうです」