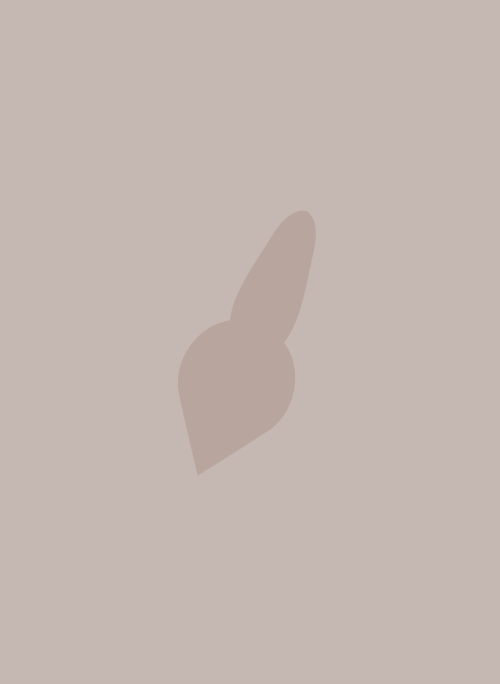「今さら何ができるのよ…」
もう終わったんだ。
涙を拭いて、あたしは立ち上がって帰る支度をする。
この一年、ずっと終わったらすぐ暁人くんの教室に行ってたから…なんか変な感じがするけど、階段に向かった。
だけど思いもよらない声があたしを引き止める。
「置いて帰んの?待ってたのに。」
「…な、んで?」
振り返って見えた景色は、いつもの逆だった。
暁人くんが、あたしの教室の前で座って待っていた。
「…俺、確かにキライって言ったよ。」
「…っもういいの!終わったの!」
「じゃぁなんで泣いてんだよっ!」
「…っ!」
「ごめんな。」
ぎゅっと苦しいくらいあたしを抱きしめるこの体温は、紛れもなくキミの体温で。
あたしはどうすることもできなかった。
「ちゃんと言うから。」