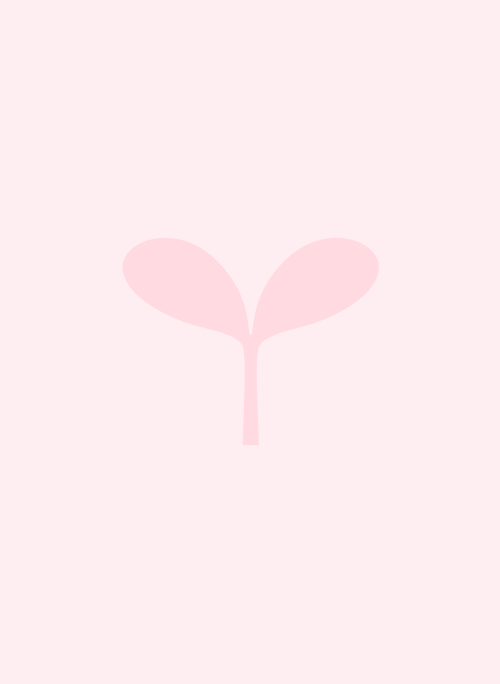その町で出会った老人たちは、彼女の唇から紡がれる歌声を魔法と呼び、空飛ぶ羽虫を妖精と呼んだ。
「僕は行けない」と彼は言った。
「僕も、待っているから」
私と彼女が訪れた海の上の町で、男はそう言って私の誘いを断った。
「この場所で待っていると約束した」
美しい町だった。美しくて、怖ろしく、そして悲しいネバーランド。
「だが──二百年以上待ったが、そいつは現れない」
私の誘いを断った男は、美しい若者の姿をしていた。もしもまだあの町にいるのなら、今もやはり変わらず美しい姿をしているのだろう。
「だから、ひょっとすると忘れているのかもしれない」
男はそう言って、小さな包みを差し出した。
「僕はこの場所を離れるわけにはゆかないが、もしもお前たちが旅の途中で会ったら、渡してもらえるだろうか」
「誰に?」
包みを受け取りながら聞いた私の問いに、彼はこう答えた。
「月から降りてきた女に」
そうして寂しい笑顔を見せた。
「たぶん、その女が最後の希望を持っている」
彼の言葉は私の脳裏に深く刻まれた。
「お前たちが探す希望と同じだと思う」
私は彼の言葉と一緒にその包みを大切にしまい込んで、そしてその包みは今日に至るまで変わらず私の手元にある。
渡すべき相手を見つけられぬまま。
「僕は行けない」と彼は言った。
「僕も、待っているから」
私と彼女が訪れた海の上の町で、男はそう言って私の誘いを断った。
「この場所で待っていると約束した」
美しい町だった。美しくて、怖ろしく、そして悲しいネバーランド。
「だが──二百年以上待ったが、そいつは現れない」
私の誘いを断った男は、美しい若者の姿をしていた。もしもまだあの町にいるのなら、今もやはり変わらず美しい姿をしているのだろう。
「だから、ひょっとすると忘れているのかもしれない」
男はそう言って、小さな包みを差し出した。
「僕はこの場所を離れるわけにはゆかないが、もしもお前たちが旅の途中で会ったら、渡してもらえるだろうか」
「誰に?」
包みを受け取りながら聞いた私の問いに、彼はこう答えた。
「月から降りてきた女に」
そうして寂しい笑顔を見せた。
「たぶん、その女が最後の希望を持っている」
彼の言葉は私の脳裏に深く刻まれた。
「お前たちが探す希望と同じだと思う」
私は彼の言葉と一緒にその包みを大切にしまい込んで、そしてその包みは今日に至るまで変わらず私の手元にある。
渡すべき相手を見つけられぬまま。