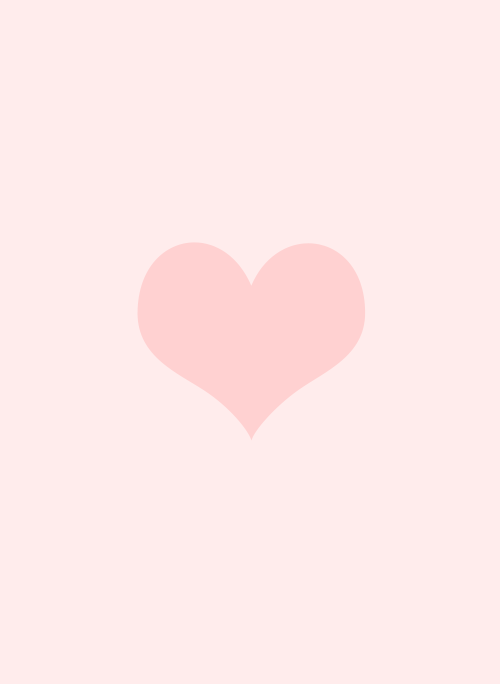本当に久々に、岡ちゃんが店に現れてくれた。
「元気ねぇって聞いたぞ。」
本当に、一体どこから情報を仕入れているのか。
曖昧に笑いながらお酒をつぐと、彼は店内をぐるりと見渡した。
「蛇みたいな顔した店長だなぁ。」
「あぁ、似てるかも。」
思わず笑うと、顔が怖い、と言われてしまう。
今のアイズは入れ替わりが激しく、だからこそ、キャスト同士微妙に噛み合わない部分がるのだ。
会話が弾まなければ、お客は面白味を見い出せない。
そうすると自然と足は遠のき、そのおかげで余計にキャストの入れ替わりが激しくなる悪循環を生んでいる。
岡ちゃんはあたし云々ではなく、この店の空気が嫌で来たがらなくなっていることはわかっていた。
それでも、あたしを娘のようだと言うことは変わらない。
ならば岡ちゃんのためにも、もうアイズを辞めるべきだという思考が脳裏をよぎった。
数々のものが、あたしの背中を押している。
それでも踏み切れない理由があるとするなら、それはひとつ。
店長の期待だ。
厳しくも冷たいことを言うけれど、彼があたしに期待を寄せていることには気付いていた。
あたしが居ればアイズは大丈夫だ、と言ってくれたあの人のことを思うと、沈みかけたこんな船でも見捨てられないのだ。
情により、がんじがらめにされている。
「元気ねぇって聞いたぞ。」
本当に、一体どこから情報を仕入れているのか。
曖昧に笑いながらお酒をつぐと、彼は店内をぐるりと見渡した。
「蛇みたいな顔した店長だなぁ。」
「あぁ、似てるかも。」
思わず笑うと、顔が怖い、と言われてしまう。
今のアイズは入れ替わりが激しく、だからこそ、キャスト同士微妙に噛み合わない部分がるのだ。
会話が弾まなければ、お客は面白味を見い出せない。
そうすると自然と足は遠のき、そのおかげで余計にキャストの入れ替わりが激しくなる悪循環を生んでいる。
岡ちゃんはあたし云々ではなく、この店の空気が嫌で来たがらなくなっていることはわかっていた。
それでも、あたしを娘のようだと言うことは変わらない。
ならば岡ちゃんのためにも、もうアイズを辞めるべきだという思考が脳裏をよぎった。
数々のものが、あたしの背中を押している。
それでも踏み切れない理由があるとするなら、それはひとつ。
店長の期待だ。
厳しくも冷たいことを言うけれど、彼があたしに期待を寄せていることには気付いていた。
あたしが居ればアイズは大丈夫だ、と言ってくれたあの人のことを思うと、沈みかけたこんな船でも見捨てられないのだ。
情により、がんじがらめにされている。