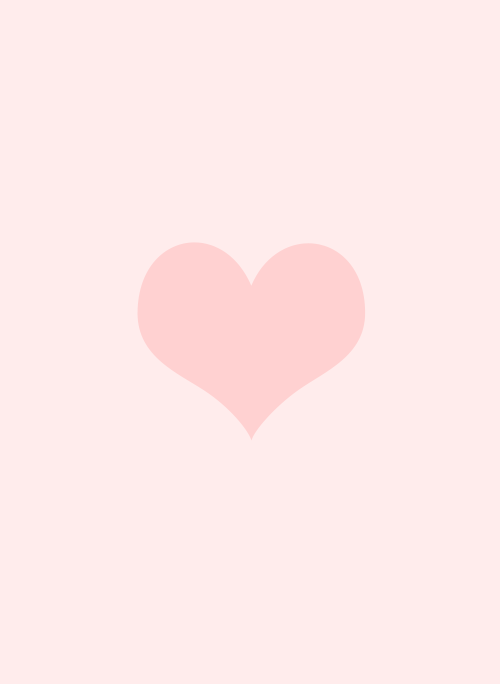「キャバ嬢のくせに、傘買う金もないんか?」
「ないって言ったら買ってくれんの?」
「タカんなやぁ。」
それは、いつものいけ好かない瞳ではなかった。
「いつまでここ居んねん?」
「もう帰るよ、用も済んだことだし。」
「ほなね。」
煙草を咥えたまま、彼は手をヒラヒラとさせるだけ。
よくわからない男だと思った。
「優しくないんだね。
嘘でも送るとか言えば良いのに。」
「俺に送られたいん?
つか、何でそんなんせなあかんねんな。」
「ほら、雨だし?」
「アホか。」
笑いながらそんな言葉を残し、彼はさっさと車に乗り込んだ。
あたしは未だコンビニの軒先に佇んだまま、雨空を見上げ続けた。
シュウが泣いているようだと思うことは相変わらずで、どうにもいたたまれなくなるのだ。
酔いが醒めるにつれ、押し潰されそうな感覚に襲われる。
こんな時は、決まってジルに会いたいと思ってしまう。
頭で考えるより先に、求めてしまうのだ。
ギンちゃんは、そんなあたしに報われない恋だと言った。
彩の顔が頭をよぎる。
「ないって言ったら買ってくれんの?」
「タカんなやぁ。」
それは、いつものいけ好かない瞳ではなかった。
「いつまでここ居んねん?」
「もう帰るよ、用も済んだことだし。」
「ほなね。」
煙草を咥えたまま、彼は手をヒラヒラとさせるだけ。
よくわからない男だと思った。
「優しくないんだね。
嘘でも送るとか言えば良いのに。」
「俺に送られたいん?
つか、何でそんなんせなあかんねんな。」
「ほら、雨だし?」
「アホか。」
笑いながらそんな言葉を残し、彼はさっさと車に乗り込んだ。
あたしは未だコンビニの軒先に佇んだまま、雨空を見上げ続けた。
シュウが泣いているようだと思うことは相変わらずで、どうにもいたたまれなくなるのだ。
酔いが醒めるにつれ、押し潰されそうな感覚に襲われる。
こんな時は、決まってジルに会いたいと思ってしまう。
頭で考えるより先に、求めてしまうのだ。
ギンちゃんは、そんなあたしに報われない恋だと言った。
彩の顔が頭をよぎる。