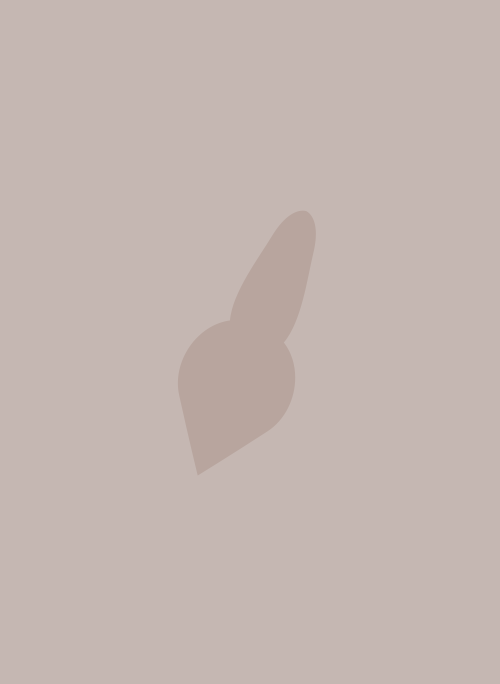「…講師…?」
「小さい塾だけどな」
彼は、勉強を教えることに関してはすでに素人ではなかった。
私くらいの年の子たちから、先生と呼ばれる立場だったのだ。
「…そんな髪で?」
「そこにツッコむか。まあ小さい塾だからな。子供ウケは悪くないぞ」
子供から見たら、お洒落で格好いいお兄さんなんだと思うけれど、親が見たらびっくりするだろう。
私の両親なら、そんな塾にあたしを入れようとは思わないだろうな。
「何でそんな大変なバイトにしたの?」
「お前、塾講師の給料知らないな。結構もらえるんだぜ」
「そんな不純な動機…?」
「生活かかってんだもん、何でもやるさ」
彩に数学を教えてくれている時の、あの優しい目を思い出せば、他にも理由があるのは明らかだったけれど、彼が私にそうであるように、私もそれ以上は聞かないことにした。