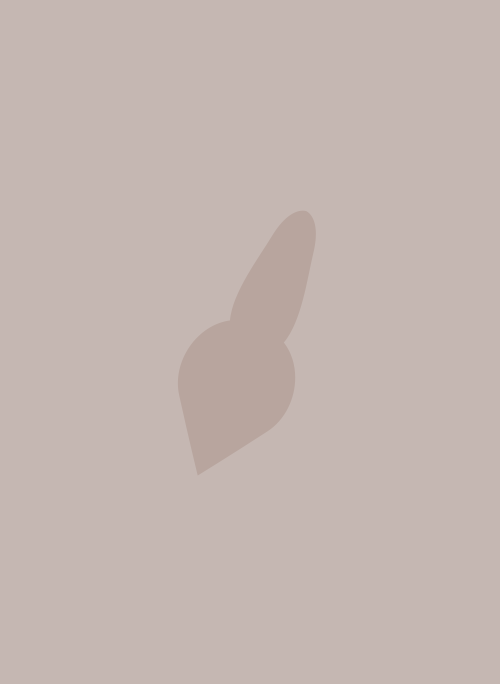ずきんと、胸の辺りに鈍い痛みが走った。
自分を唯一女として見るこの男の表情を見ていたら、体中がざわつくような、放っておくと泣き出しそうな思いが、体を蠢いた。
これ以上、彼に近づいたらまずい。
頭ではわかっているのに。
今ここで、彼が油断している内に大声をあげれば、彼が逃げるのが早いか、人が来るのが早いか。
少なくとも彼とこうして会話することはなくなるだろうに。
自分の体はそのように動こうとはしない。
やっとの思いで、彼から視線を外して、
「もう行け。誰か人が来ればただではすまされないぞ」
と呟いた。
「また、来ていいか?」
そんな風に聞く彼に、
「来るな」
と返せば、ゼンはリアの髪に優しく触れた。
「来るなって顔、してない」
リアは赤くなって、ゼンの手を振り払った。
「もう行け」
「ああ、じゃあ、またな」
ゼンは笑いながら、窓を開け、出て行った。
自分を唯一女として見るこの男の表情を見ていたら、体中がざわつくような、放っておくと泣き出しそうな思いが、体を蠢いた。
これ以上、彼に近づいたらまずい。
頭ではわかっているのに。
今ここで、彼が油断している内に大声をあげれば、彼が逃げるのが早いか、人が来るのが早いか。
少なくとも彼とこうして会話することはなくなるだろうに。
自分の体はそのように動こうとはしない。
やっとの思いで、彼から視線を外して、
「もう行け。誰か人が来ればただではすまされないぞ」
と呟いた。
「また、来ていいか?」
そんな風に聞く彼に、
「来るな」
と返せば、ゼンはリアの髪に優しく触れた。
「来るなって顔、してない」
リアは赤くなって、ゼンの手を振り払った。
「もう行け」
「ああ、じゃあ、またな」
ゼンは笑いながら、窓を開け、出て行った。