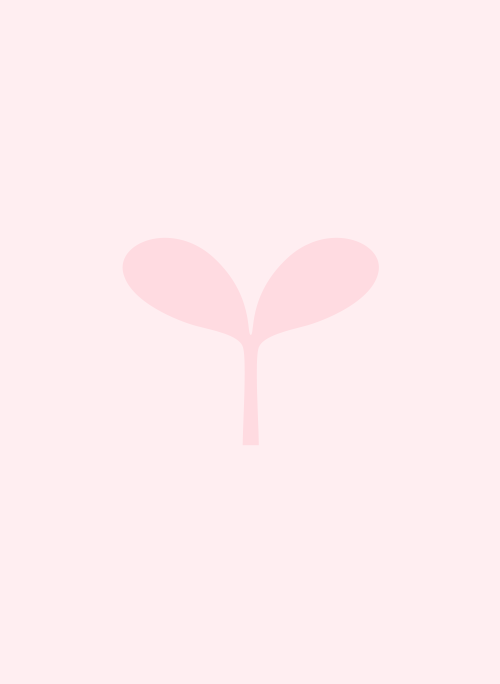その姫付きの侍女の名は、稚宝という。
十を過ぎた頃から、稚宝は侍女の見習いとして暮らし始めた。物覚えが良く、よく気付いて働く。年頃になると見習いではなく、年の近い恭姫に仕えるようになった。
「この者……」
二人は、稚宝の記録を辿った。第十の月の二十七日から二十八日朝にかけてが不寝番。さらに遡る。満の日、あの夜に、姫と一緒にいた者だ。
雨の中、姫が月を見たいと言って城を飛び出した夜。それを何人かの侍女がすぐに追いかけた。その中にいたのか。
「まさか」
暁晏と羽雨は息を飲んだ。
追いかけたときに、まさか、蛇殺し草で傷付いたのではないか。姫ほどの傷でなかったために気付かれなかったが、徐々にあの蛇の痣が現れたのではないか。それを見られたくなくて、風呂に入らないのではないか。
「羽雨よ」
「暁晏さん、見落としたことはあとで謝るわ。すぐに稚宝を」
羽雨の顔から血の気が引いている。
「私も行こう」
二人が腰を上げ、まさに部屋を出ようとしたとき、部屋の戸が叩かれた。
「枋先生」
呼んだのは章王の側近である。
つまり。
「陛下がお呼びです」