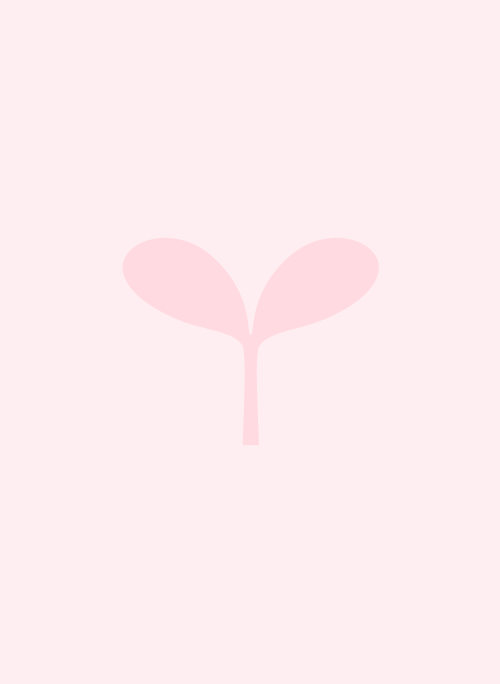「何」
菜音はまだ、この国に来て日が浅い。
「恵孝」
続けて何か言いたげにしているが、言葉に出来ずもどかしそうに顔を赤らめた。
「菜音、恵孝がいたろう」
梯子の下からした声は、祖母のものだった。菜音は下を見て大きく頷く。一度梯子を降りていく。
「これを、恵孝に」
そう、祖母が言うのが聞こえて、また菜音が現れた。懐が大きく膨らんでいる。二階の板間に降りて、すぐ近くに座る。菜音は懐から竹の皮の包みを取り出した。恵孝は受け取る。広げると、味噌を塗って焼いた大きな握り飯が一つ入っていた。
「丹祢さん、言う、恵孝、食べる、これ」
香ばしい匂いに釣られてか、恵孝の腹が大きな音を立てた。情けなくて自分で笑ってしまうと、菜音の腹も大きく鳴った。堪えきれず、二人して笑い転げる。笑いながら、握り飯を半分に割る。半分を手で掴み、残りを菜音に渡した。共にかぶりつく。
実は街の悪童に無理矢理食わされた饅頭が腐っていて、それを祖父や父に知られるのが嫌だから勝手にやったのだと、食べながら菜音に白状した。どこまで通じているのかは分からないが、菜音は目を見開いて話を聞いてくれた。握り飯は甘くて塩辛かった。
――ここまでは記憶なのだ。
菜音はまだ、この国に来て日が浅い。
「恵孝」
続けて何か言いたげにしているが、言葉に出来ずもどかしそうに顔を赤らめた。
「菜音、恵孝がいたろう」
梯子の下からした声は、祖母のものだった。菜音は下を見て大きく頷く。一度梯子を降りていく。
「これを、恵孝に」
そう、祖母が言うのが聞こえて、また菜音が現れた。懐が大きく膨らんでいる。二階の板間に降りて、すぐ近くに座る。菜音は懐から竹の皮の包みを取り出した。恵孝は受け取る。広げると、味噌を塗って焼いた大きな握り飯が一つ入っていた。
「丹祢さん、言う、恵孝、食べる、これ」
香ばしい匂いに釣られてか、恵孝の腹が大きな音を立てた。情けなくて自分で笑ってしまうと、菜音の腹も大きく鳴った。堪えきれず、二人して笑い転げる。笑いながら、握り飯を半分に割る。半分を手で掴み、残りを菜音に渡した。共にかぶりつく。
実は街の悪童に無理矢理食わされた饅頭が腐っていて、それを祖父や父に知られるのが嫌だから勝手にやったのだと、食べながら菜音に白状した。どこまで通じているのかは分からないが、菜音は目を見開いて話を聞いてくれた。握り飯は甘くて塩辛かった。
――ここまでは記憶なのだ。