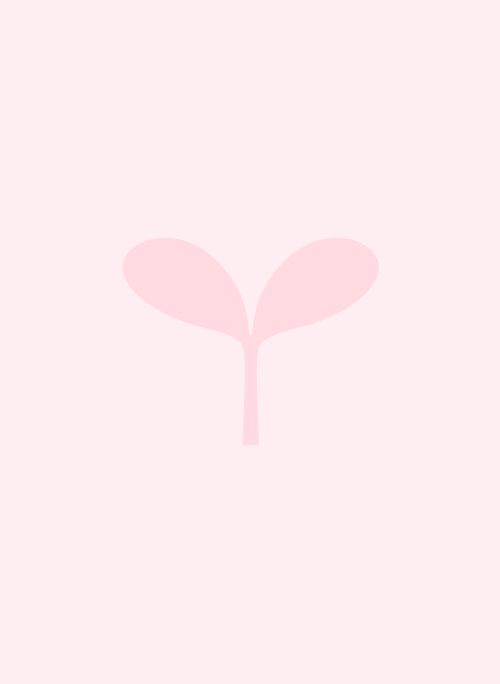するとそれが合図だったかのように、ザァ──‥っと勢いよく雨が降ってきた。
私たちは最寄りの無人駅へと走り、雨が止むのを待った。
その間、手は繋いだままだった。
人もいなかったから、恥ずかしさはもうなかったし、こうして手を繋いでいることが気持ちよかったから、離そうとは思わなかった。
電車の時間にはまだ余裕があるから、私たちはお互いに持っていたタオルで体を拭いた。
このときばかりは手を離したけど、何だか勿体ない気がしてならなかった。
肌にぺったりと張り付く服が気持ち悪い。
そんなことをぼんやり思っていたら髪をタオルでわしゃわしゃと掻き回された。
「ちょっ‥何すんの!?ぐちゃぐちゃになっちゃうじゃんっ!」
「いいじゃん別に。もとからぐっちゃぐちゃになんだし」
乱暴に私の髪を掻き回す彼は心底楽しそうだった。
「黙れ!」
最初は、タオルを引っ張って抵抗していた私も、途中からは一緒になって彼の髪をタオルで掻き回した。
ひとしきりそんなことを続けていたら、髪はすっかり乾いてしまって、私も彼も疲れ果て、背も垂れにぐったりと寄り掛かった。
もちろん、お互いにタオルを頭からかぶったまま。
周りから見ればただのバカップルにしか見えないのだろうけど、私たちが楽しいのなら、それはそれでいい気がした。
「‥‥ん、?」
不意に彼の指が私の唇をなぞったから、変な声が出た。
キス、を、されると思った。
あまりにも彼の目が真剣だったから、少し怖かった。
でも、あのとき感じた彼の手の温もりはあまりにも優しく心地がよかったから、思わず続きを期待してしまった。
「好きだ」
「うん、」
「お前は?」
「私も、」
好き
言って、初めて、知った。
私は彼を好きになっていたのだと。
あの日、初めて彼に言われたとき、私は彼をただのクラスメイトとしか認識していなかった。
それが今はどうだ。
掛け替えのない、私の一部。
否、掛け替えのない、私の半身。
触れただけの唇は柔らかかった。
目を瞑って、そうして思わず息まで止めてしまって。
離れていく唇が名残惜しかったけど、今の私にはまだおねだりなんて、恥ずかしくてできなかった。
だからただ、手を握った。
それだけは一人前にできるようになっていた。
私たちは最寄りの無人駅へと走り、雨が止むのを待った。
その間、手は繋いだままだった。
人もいなかったから、恥ずかしさはもうなかったし、こうして手を繋いでいることが気持ちよかったから、離そうとは思わなかった。
電車の時間にはまだ余裕があるから、私たちはお互いに持っていたタオルで体を拭いた。
このときばかりは手を離したけど、何だか勿体ない気がしてならなかった。
肌にぺったりと張り付く服が気持ち悪い。
そんなことをぼんやり思っていたら髪をタオルでわしゃわしゃと掻き回された。
「ちょっ‥何すんの!?ぐちゃぐちゃになっちゃうじゃんっ!」
「いいじゃん別に。もとからぐっちゃぐちゃになんだし」
乱暴に私の髪を掻き回す彼は心底楽しそうだった。
「黙れ!」
最初は、タオルを引っ張って抵抗していた私も、途中からは一緒になって彼の髪をタオルで掻き回した。
ひとしきりそんなことを続けていたら、髪はすっかり乾いてしまって、私も彼も疲れ果て、背も垂れにぐったりと寄り掛かった。
もちろん、お互いにタオルを頭からかぶったまま。
周りから見ればただのバカップルにしか見えないのだろうけど、私たちが楽しいのなら、それはそれでいい気がした。
「‥‥ん、?」
不意に彼の指が私の唇をなぞったから、変な声が出た。
キス、を、されると思った。
あまりにも彼の目が真剣だったから、少し怖かった。
でも、あのとき感じた彼の手の温もりはあまりにも優しく心地がよかったから、思わず続きを期待してしまった。
「好きだ」
「うん、」
「お前は?」
「私も、」
好き
言って、初めて、知った。
私は彼を好きになっていたのだと。
あの日、初めて彼に言われたとき、私は彼をただのクラスメイトとしか認識していなかった。
それが今はどうだ。
掛け替えのない、私の一部。
否、掛け替えのない、私の半身。
触れただけの唇は柔らかかった。
目を瞑って、そうして思わず息まで止めてしまって。
離れていく唇が名残惜しかったけど、今の私にはまだおねだりなんて、恥ずかしくてできなかった。
だからただ、手を握った。
それだけは一人前にできるようになっていた。