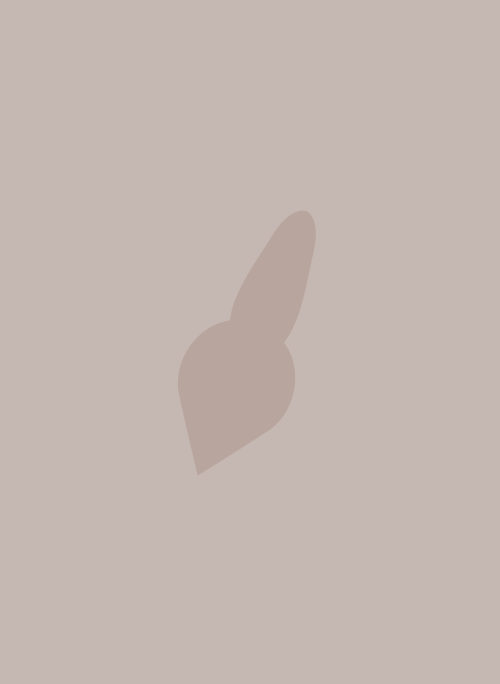ミカンはいつだって、こうやって合わせてくれた。
ミカンは多くを望まない娘だった。
「何か欲しい?」
「何がしたい?」
訊くだけ無駄である程に。
ただそこにナツが居てくれたら良かった。
ナツはいつも羨望の眼差しに晒された。
橋の真ん中で笑い合う2人の頭上から、汚れる寸前の真っ白い綿雪が落ちてきた。
「おぉ!すげぇ」
空を仰ぐナツは、思い当たりのない不愉快な不安に囚われる。
(この白い螢が全てを埋め尽くしてしまうのではないか?)
しかし、それを否定するかのようにミカンが嬉しそうに言った。
「ねぇ、知ってる?クリスマスに降る雪は、サンタさんがそこを通った時なんだって」
「てことは、今この上をサンタが通り抜けたってこと?じゃあ、雪が降んねぇ所にはサンタ来ねぇの?」
「何でそう夢を壊すの!?現実に戻さないでよぉ~」
ミカンは多くを望まない娘だった。
「何か欲しい?」
「何がしたい?」
訊くだけ無駄である程に。
ただそこにナツが居てくれたら良かった。
ナツはいつも羨望の眼差しに晒された。
橋の真ん中で笑い合う2人の頭上から、汚れる寸前の真っ白い綿雪が落ちてきた。
「おぉ!すげぇ」
空を仰ぐナツは、思い当たりのない不愉快な不安に囚われる。
(この白い螢が全てを埋め尽くしてしまうのではないか?)
しかし、それを否定するかのようにミカンが嬉しそうに言った。
「ねぇ、知ってる?クリスマスに降る雪は、サンタさんがそこを通った時なんだって」
「てことは、今この上をサンタが通り抜けたってこと?じゃあ、雪が降んねぇ所にはサンタ来ねぇの?」
「何でそう夢を壊すの!?現実に戻さないでよぉ~」