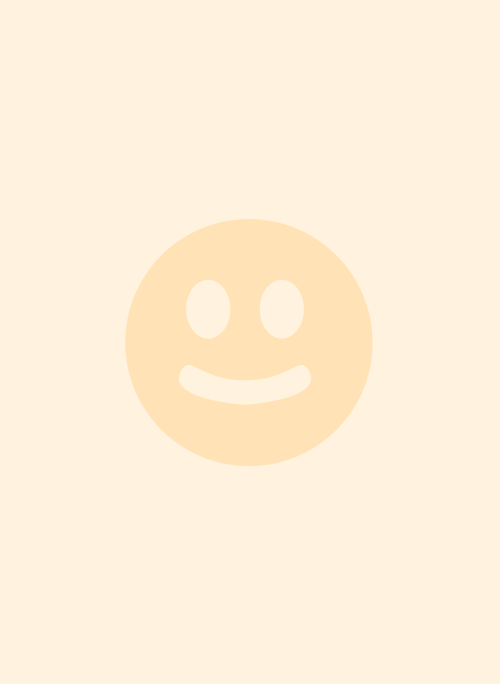ナハトが鍛冶場を出てきたのは翌日の日も高く昇った頃だった。
全身に玉のような汗を浮かべ、疲労した表情で姿を現したナハト。
その手には、彼女の背丈ほどの刀身を持つ片刃の剣が握られている。
「ナハト…それが…」
顔さえ映り込むほど磨き上げられ、鍛え上げられたその美しい美術品のような剣に、俺は魅入られる。
勿論ただの観賞用ではない。
あの刃竜の角を加工し、世界一の業を持つドーラの民であるナハトによって鍛えられた剣だ。
名剣と呼んでも差し支えはないだろう。
「…仮の柄と鍔を取り付けておいた…すぐにでも…使える…」
そこまで言って、彼女は足をもつれさせる。
「ナハト!」
俺は慌てて彼女の体を支えた。
無理もない。
丸一日以上鍛冶場に閉じこもり、食事も睡眠もとらずに剣を鍛え続けていたのだ。
体力を消耗するのも当然だ。
「武具屋の店主から…聞いた…牙竜の所在が…」
「今はいい」
俺はナハトに肩を貸したまま、宿の方角へと歩き出す。
休息と栄養補給。
それがナハトにとって今必要な事だった。
全身に玉のような汗を浮かべ、疲労した表情で姿を現したナハト。
その手には、彼女の背丈ほどの刀身を持つ片刃の剣が握られている。
「ナハト…それが…」
顔さえ映り込むほど磨き上げられ、鍛え上げられたその美しい美術品のような剣に、俺は魅入られる。
勿論ただの観賞用ではない。
あの刃竜の角を加工し、世界一の業を持つドーラの民であるナハトによって鍛えられた剣だ。
名剣と呼んでも差し支えはないだろう。
「…仮の柄と鍔を取り付けておいた…すぐにでも…使える…」
そこまで言って、彼女は足をもつれさせる。
「ナハト!」
俺は慌てて彼女の体を支えた。
無理もない。
丸一日以上鍛冶場に閉じこもり、食事も睡眠もとらずに剣を鍛え続けていたのだ。
体力を消耗するのも当然だ。
「武具屋の店主から…聞いた…牙竜の所在が…」
「今はいい」
俺はナハトに肩を貸したまま、宿の方角へと歩き出す。
休息と栄養補給。
それがナハトにとって今必要な事だった。