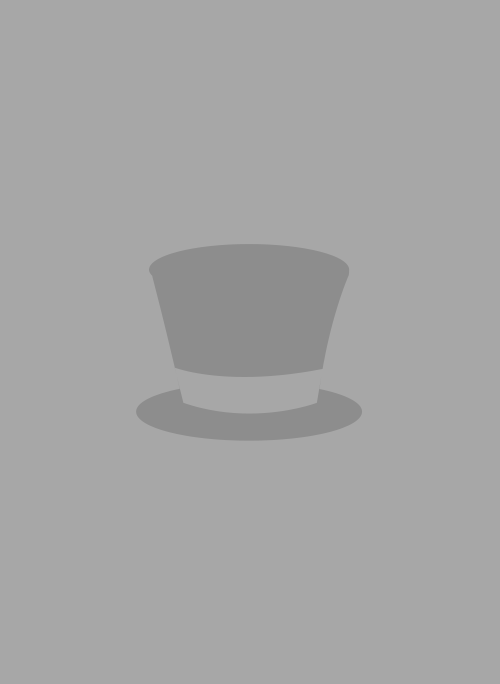アンソニーと呼ばれた、50歳くらいの金髪の男性が、毛布に包まれた母を抱いて、温室に入ってきた。
両足と片腕を失った母はとても小さくて、まるで小さな子供のようにも見えた。
父はまるでガラス細工でも扱うかのように、彼女を受け取り抱きしめた。
愛する者を抱く、その表情はとても幸せそうで…
それゆえに、切なくて…
目覚めぬ母を想い続ける父に、胸が熱くなった。
父は自分の席の傍らに設置されたベッドにゆっくりと彼女を横たえた。
父が年を取ったように、母もまた年を取っていたが、今日の祝いの為に美しく化粧を施した母は、俺の記憶の中の面影のままだった。
ベッドの傍らに立ち母を見下ろすと、その手を取り跪く。
声を掛けようとするが、感情が込み上げ喉が詰まり、思うように出なかった。
「母さん…響だよ」
無理やり搾り出した声は、思った以上に小さく擦れていた。
「……久しぶりだね…会いたかったよ」
母はその瞳を閉じたままだったが、僅かに頬が色を増した気がした。
それは父も感じたらしい。
ほんの少しでも反応があった事は、全員を沸き立たせ、回復を促そうと皆で代わる代わる語りかけた。
両足と片腕を失った母はとても小さくて、まるで小さな子供のようにも見えた。
父はまるでガラス細工でも扱うかのように、彼女を受け取り抱きしめた。
愛する者を抱く、その表情はとても幸せそうで…
それゆえに、切なくて…
目覚めぬ母を想い続ける父に、胸が熱くなった。
父は自分の席の傍らに設置されたベッドにゆっくりと彼女を横たえた。
父が年を取ったように、母もまた年を取っていたが、今日の祝いの為に美しく化粧を施した母は、俺の記憶の中の面影のままだった。
ベッドの傍らに立ち母を見下ろすと、その手を取り跪く。
声を掛けようとするが、感情が込み上げ喉が詰まり、思うように出なかった。
「母さん…響だよ」
無理やり搾り出した声は、思った以上に小さく擦れていた。
「……久しぶりだね…会いたかったよ」
母はその瞳を閉じたままだったが、僅かに頬が色を増した気がした。
それは父も感じたらしい。
ほんの少しでも反応があった事は、全員を沸き立たせ、回復を促そうと皆で代わる代わる語りかけた。