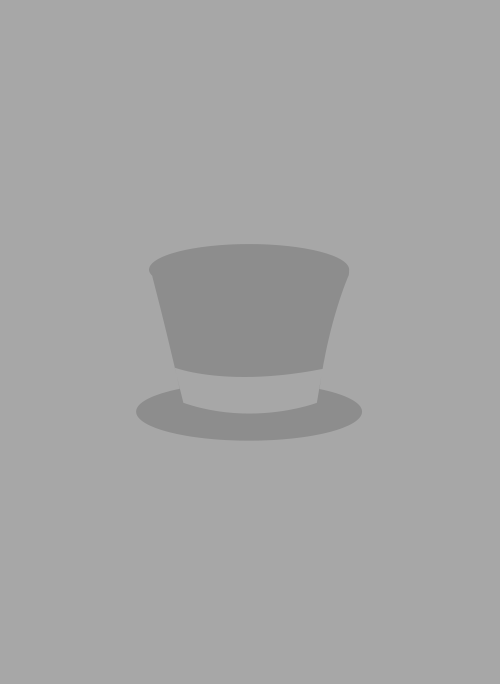「少しマジな話なんだけどさ…聖良には聞いて欲しいんだ。」
そう言うと少し悲しげな複雑な顔をして龍也先輩はあたしを引寄せて小さな声で話し始めた。
一つだけ咲いた小さな桜が春風に煽られる。
その光景が何故か切なく映ったのは龍也先輩の声がとても切ないものだったからかもしれない。
「俺のいなくなった母親はさくらと言うんだ。俺の誕生日の頃はいつも桜が満開でこの川縁へ毎年花見に来たよ。母親と死んだ父親と三人でさ。」
あたしを抱きしめる手に僅かに力が入る。あたしは先輩の背中に腕を回すと支えるようにして抱きしめた。
あれほど心を閉ざしていたお母さんの話を龍也先輩が自ら話してくれていることに驚くと同時に、それだけあたしを信頼してくれている事に感動を覚えた。
嬉しさと、愛しさが込み上げてくる。
「母親が蒸発してから俺の父は仕事にのめり込んだ。母親の事を忘れたかったんだろうな。無理がたたって倒れたときにはガンの末期でもう手遅れだったんだ。」
「そんな…。」
「俺は母親が憎かったよ。今でも許せるとは思っていない。でも…聖良に出逢ってから、折に触れて母親が俺を愛していた頃の記憶って言うのが少しずつ蘇ってきているんだ。最近では俺達の前から姿を消したのには何か理由があったんじゃないかと思うようになってきた。」
天を仰ぐようにして、一旦呼吸を整えるように間を置くとあたしの瞳を見つめてくる。
その瞳の中に先輩が何か決意をしているように見えた。
そう言うと少し悲しげな複雑な顔をして龍也先輩はあたしを引寄せて小さな声で話し始めた。
一つだけ咲いた小さな桜が春風に煽られる。
その光景が何故か切なく映ったのは龍也先輩の声がとても切ないものだったからかもしれない。
「俺のいなくなった母親はさくらと言うんだ。俺の誕生日の頃はいつも桜が満開でこの川縁へ毎年花見に来たよ。母親と死んだ父親と三人でさ。」
あたしを抱きしめる手に僅かに力が入る。あたしは先輩の背中に腕を回すと支えるようにして抱きしめた。
あれほど心を閉ざしていたお母さんの話を龍也先輩が自ら話してくれていることに驚くと同時に、それだけあたしを信頼してくれている事に感動を覚えた。
嬉しさと、愛しさが込み上げてくる。
「母親が蒸発してから俺の父は仕事にのめり込んだ。母親の事を忘れたかったんだろうな。無理がたたって倒れたときにはガンの末期でもう手遅れだったんだ。」
「そんな…。」
「俺は母親が憎かったよ。今でも許せるとは思っていない。でも…聖良に出逢ってから、折に触れて母親が俺を愛していた頃の記憶って言うのが少しずつ蘇ってきているんだ。最近では俺達の前から姿を消したのには何か理由があったんじゃないかと思うようになってきた。」
天を仰ぐようにして、一旦呼吸を整えるように間を置くとあたしの瞳を見つめてくる。
その瞳の中に先輩が何か決意をしているように見えた。