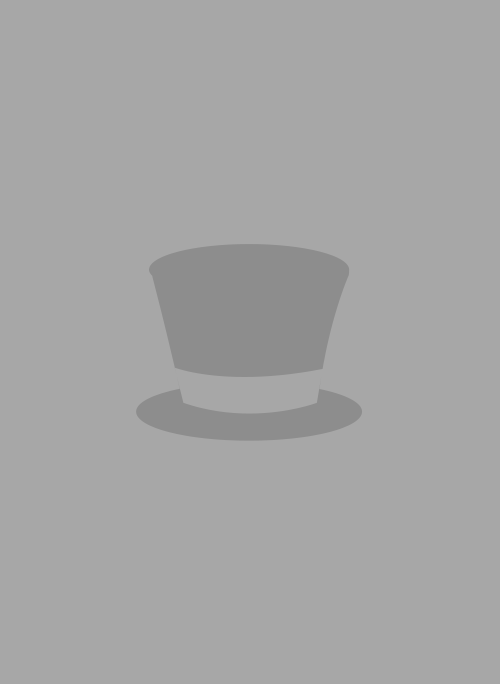「あ、ごめんなさい。そんなつもりで言ったんじゃないんです。気にしないで下さい。ごめんなさい、なんだか愚痴みたいな事…。」
「愚痴ならもっと言ってくれて良いよ。何でもっと会えないのかって我が侭言ってくれればいい。そしたら夜中だって構わずに会いに行ってやるよ。聖良はイイコになりすぎる。もっと我が侭になっていいんだ。」
「ダメですよ。そんな我が侭言ったら先輩は本当に夜中でも来ちゃいそう。ただでさえ忙しくて充分睡眠も取っていないんじゃないんですか?」
「…いいんだ。どうせ眠れないんだから。」
「不眠症なんですか?」
「この間は聖良の腕の中で凄く良く眠れたよ。あんなに寝たのは久しぶりだった。ダメなんだよ。一人で寝ようとしても見るのはいつも悪い夢で…。だからいっそ眠らないほうが良いんだ。短時間で深く眠れば夢もみない。そのほうが俺には幸せなんだよ。」
いつの間にか俺の表情が固く強張っていたようで聖良が心配そうに俺を見上げてくるのを感じた。慌てて笑顔を作って明るく振る舞ってみせる。
「じゃあ、あたしが傍にいたら眠れますか?」
「…え?」
「あたしが先輩の傍にいたら悪夢を見ないでちゃんと眠れますか?」
「…クスッ、そうだな。聖良が傍にいたくれればぐっすり眠れるかもしれない。聖良は俺の抱き枕になってくれるのか?」
からかうように冗談めかして言ってみると聖良は真っ赤になって俺の腕の中に顔を埋めるようにして顔を伏せた。
目の前に聖良の白いうなじが飛び込んできて心臓が一気に心拍数を上げて動き始めた。
そのとき
夜空に年明けを告げる花火が上がった
「愚痴ならもっと言ってくれて良いよ。何でもっと会えないのかって我が侭言ってくれればいい。そしたら夜中だって構わずに会いに行ってやるよ。聖良はイイコになりすぎる。もっと我が侭になっていいんだ。」
「ダメですよ。そんな我が侭言ったら先輩は本当に夜中でも来ちゃいそう。ただでさえ忙しくて充分睡眠も取っていないんじゃないんですか?」
「…いいんだ。どうせ眠れないんだから。」
「不眠症なんですか?」
「この間は聖良の腕の中で凄く良く眠れたよ。あんなに寝たのは久しぶりだった。ダメなんだよ。一人で寝ようとしても見るのはいつも悪い夢で…。だからいっそ眠らないほうが良いんだ。短時間で深く眠れば夢もみない。そのほうが俺には幸せなんだよ。」
いつの間にか俺の表情が固く強張っていたようで聖良が心配そうに俺を見上げてくるのを感じた。慌てて笑顔を作って明るく振る舞ってみせる。
「じゃあ、あたしが傍にいたら眠れますか?」
「…え?」
「あたしが先輩の傍にいたら悪夢を見ないでちゃんと眠れますか?」
「…クスッ、そうだな。聖良が傍にいたくれればぐっすり眠れるかもしれない。聖良は俺の抱き枕になってくれるのか?」
からかうように冗談めかして言ってみると聖良は真っ赤になって俺の腕の中に顔を埋めるようにして顔を伏せた。
目の前に聖良の白いうなじが飛び込んできて心臓が一気に心拍数を上げて動き始めた。
そのとき
夜空に年明けを告げる花火が上がった