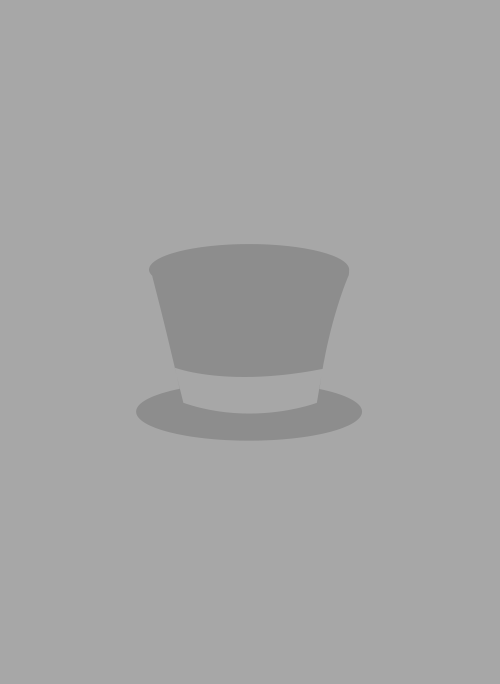アパートが少し古かったことも、ずっと気になっていた。
水回りや雨戸のたてつけの悪さなど、至るところでそれを感じさせる。
限界を感じ、とうとう引っ越しを決意した。
どうせならと都心部に出たのだが――世の中、一つ問題が解決すればまた新たに問題は出てくるものである。
大きなため息をついて、百夏はベンチに腰を下ろした。
生まれた時から父がおらず、母と二人で過ごしてきた百夏は、多少の苦労には耐性があると自負している。
というか、苦労を苦労だと認識するのが嫌で、認めたくない頑固な性格なのかもしれないが。
そんな百夏だからこそ、限界まであのアパートで生活できたのかもしれない。
快適とは言えないその生活を我慢してまでも、そこに住み続けた訳。
今は亡き、母との思い出が僅かに残る住まいをなかなか手離す勇気がなかったのだ――。