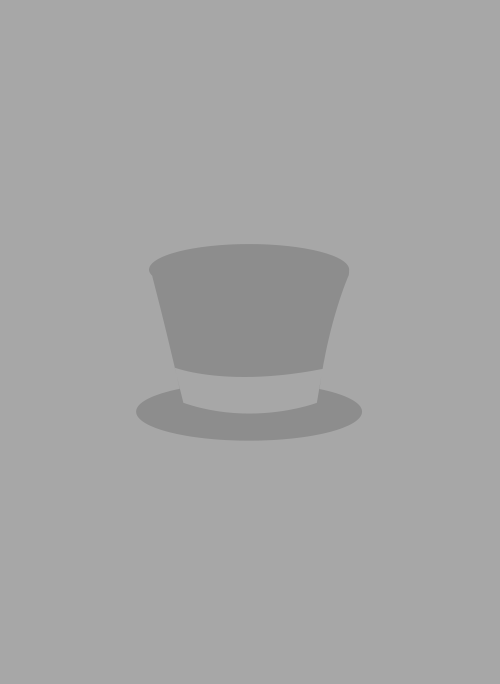「じゃ、また」
「うん。よろしくお願いします」
手を振って見送る繁人にちょこんと一礼すると、女子高生の後ろに並んでバスへ乗り込んだ。
今まで、記憶についてさほど真剣に考えたことなどなかった。
忘れたり、覚えていないことがあったりしても、ごく当たり前の事だろうと思っていた。
幼い頃の、父の記憶が残っていないことも大して悔しいことではなかったし、別に知ろうともしなかった。
なのに、なぜこんなにも固執しているんだろう――。
別に、知らなくてもいいではないか。
それも、二人はとっくに別れていて、終わった話だとするならなおさら関係のない事だ。
だが……百夏は、どうしてもその記憶を取り返したいと思った。
――繁人の脳内にある『モモカ』が、手招きして自分を呼んでいる気がするのだ……。