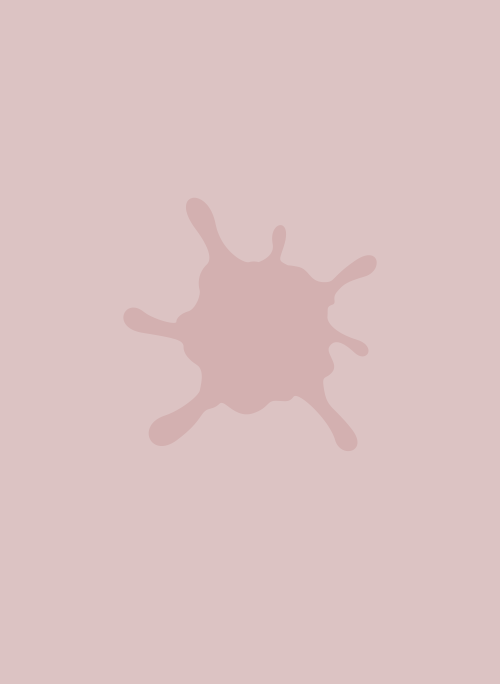「あーあ。せっかくチャンスあげたのにあっけないなぁ。」
少年は顔についた赤い液体を手でこすった。
白かった部屋は鉄のツンとしたにおいとで包まれ、赤に染まっていた。
下には無惨に転がる愛しい人。
もう硬直して動かなくなっていた。
少年は下に倒れている愛しい人を優しく見つめ、抱えこんだ。
「父さんよかったね。これで明日の新聞の一面を乗っ取れるよ。名誉あることだね。よかったね。よかったね。よかったね。よかったね…」
少年は何度も何度も呟いた。
何度も何度も何度も…
自分の手を見ると赤く染まっていて、鏡をみると、自分が赤く染まっていた。
自分の瞳には光がなく虚ろだったが、表情はいたって豊かで不気味なほど笑っていた。
「父さん。俺いままで父さんが憎くて仕方なかったけど今は愛しいよ。
だって…こんなにも脆いんだもん。あんなに強いと思っていたのに…。」
少年の顔に笑顔は絶えない。