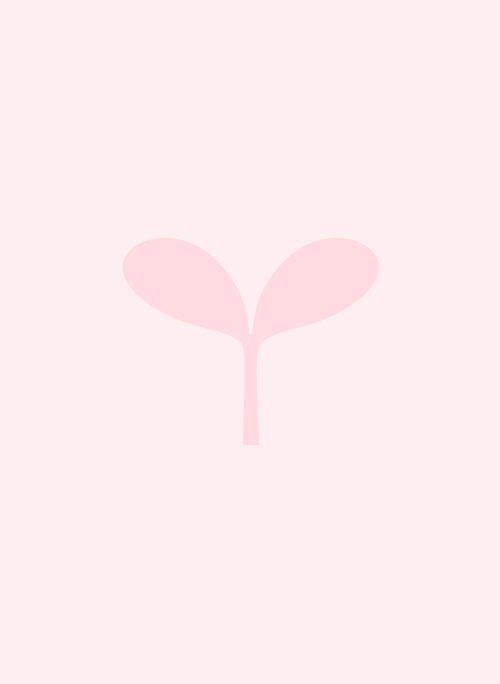誰も居ない部屋を出て、勤めを終えて帰宅するまで、尚美は何度も自分自身の人生を忌み嫌い、何人ものすれ違う人間を妬み、自身と関わる周囲の人間を、何度もバカだと思う事で、自らを傷つけまいとしていた。
尚美は、自分を傷つけまいとしながらも、より一層深く追い詰められて行く自分を、決して認めようとしなかった。
悪魔に魅入られて、氷の鎧で固められたその
心は、蟻地獄、いや、食虫花の如く、甘い芳しい香りさえ携え、尚美を苦しめていた。
尚美は、自分を傷つけまいとしながらも、より一層深く追い詰められて行く自分を、決して認めようとしなかった。
悪魔に魅入られて、氷の鎧で固められたその
心は、蟻地獄、いや、食虫花の如く、甘い芳しい香りさえ携え、尚美を苦しめていた。