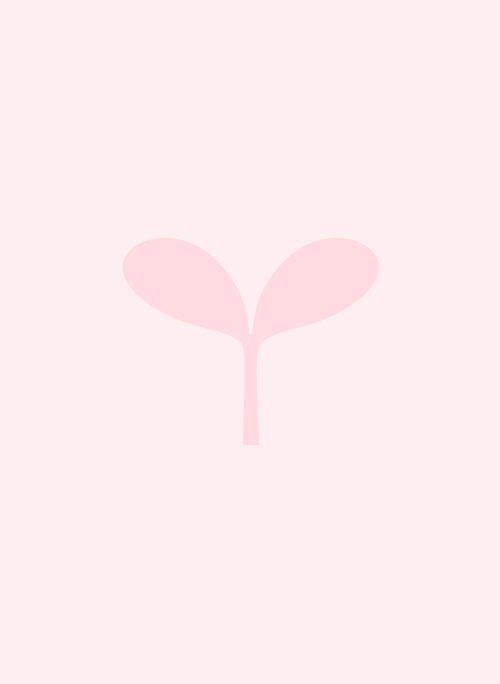細い細い真っ暗な路地を遠々と泣きながら走る夢を尚美は、24才になる今日まで、何度みた事だろう。
それは、幼い頃迷子になった時の記憶の様であり、更に遠い遠い昔、DNAにたたき込まれた記憶の様でもあった。
その夢をみて目覚める度に、尚美はその映像を、絵画か映画にでもとどめておきたい衝動に駆られた。
それが単に、懐かしく感じられたという訳だけで無い事を、彼女は直感的に感じていた。
小崎尚美は、挫けていた。
「あーもう いや!」
大きなため息と共に吐き出した嘆きは、尚美自身をナーバスにさせる悲鳴であった。
朝、7時40分起床8時きっかりに家を出る。会社に向かう途中、何度も逃げ出したくなる衝動に駆られながら、尚美はひたすら堪えていた。
それは、幼い頃迷子になった時の記憶の様であり、更に遠い遠い昔、DNAにたたき込まれた記憶の様でもあった。
その夢をみて目覚める度に、尚美はその映像を、絵画か映画にでもとどめておきたい衝動に駆られた。
それが単に、懐かしく感じられたという訳だけで無い事を、彼女は直感的に感じていた。
小崎尚美は、挫けていた。
「あーもう いや!」
大きなため息と共に吐き出した嘆きは、尚美自身をナーバスにさせる悲鳴であった。
朝、7時40分起床8時きっかりに家を出る。会社に向かう途中、何度も逃げ出したくなる衝動に駆られながら、尚美はひたすら堪えていた。