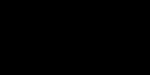気まずい。気まずすぎる。
12月25日。今日、この日は一花と僕の家でクリスマスパーティをする日。
なのに、2日前、喧嘩をしてしまった。
2日前をそっと思い出す。
その日は、バイトが終わった後一緒にファミレスに来ていた。
注文が終わり、食べ物が運ばれてくるまで宿題をすることにした。
やばい課題が溜まってる。しかも最近整理整頓があまり出来ていない...。
「ねえ、何それ?カバンの中は綺麗にしなって言ったじゃん。しかもいつも綺麗にしてあげてるし。次からはちゃんとするって言ってたよね?」
帰る前に、店長に少しだけ注意された一花は機嫌が悪く、さらにこの汚さを見て機嫌が悪くなってしまったみたいだ。
「ごめん、最近忙してくてさ。」
忙しい、という言葉に引っかかったのか、こっちを見ていた目がキツくなった。
「忙しい?だったら整理整頓とかはなんでも良いわけ?良い加減高校生なんだからちゃんとしたら?」
僕だってきちんとしないといけないことぐらい分かってる。でも保護者でもないのに、そんなこと言わなくていいだろ、と思ってしまう。
「分かってる。」
「あとさ、何この溜まってる課題。何のために高校行ってるか分かってるの?バイト重視じゃないんだかるさ。」
課題をカバンから取り出して、手に持ちながら一花はそう言った。
「分かってるって。それはさ僕自身の問題であって、一花には関係ないから。」
「関係ない?じゃあ関係ある話しよっか?」
そう言って一花はポケットからスマホを取り出した。やばいどんどん機嫌が悪くなっている...互いに...。
「これ見て。」
すると、僕と友達が歩いている写真が写っていた。
「これ誰?浮気?」
写っていたのは、家の近くに住んでいる幼馴染の心菜だった。浮気でもないし、勝手に僕をつけて盗撮していゆことに少し怒りがあった。
理由を説明する間もなく、一花は立ち上がった。
「私もう食べ物いらないから、どうぞ食べて。お金置いていくから。」
「ちょっ、どゆこと?」
僕の言葉を無視して、一花は店を出た。一花が座っていた椅子には1000円札だけがあった。
心菜とは、クリスマスのプレゼントを買うためだったのに...。
このまま追いかけたところで、多分話なんか聞いてくれないと思う。
だから、LINEを開き、メッセージを送ることにした。
(蒼空:さっきの人は幼馴染だから、何も浮気とかじゃないです。ちゃんと話がしたいので、約束してた25日に僕の家来て下さい。待ってます。)
きっと来てくれるだろうと信じて、僕は今待っている。家族を追い出してまでして...。
掃除が終わり、ソファに座ってスマホを触っているとインターフォンが鳴る。
心臓がドキッとして、足が少しだけ震える。
“応答”のボタンを押すと、そこにいたのは…一花だった。
思いたくもないけど、別れるなんて言われたらどうしよう、実はあんな所がが嫌いだったとか言われたらどうしよう。いろんな言葉を考えてしまう。
深呼吸をして、扉を開ける。
いつもとは少し違う雰囲気をまとった、一花がいた。
「来てくれて、ありがとう。じゃあ入って。」
一花は靴を脱ぎ、何も言わずに中へ入った。
「あのさ、早くあれはどう言うことか話してくれる?」
一花は床に荷物を置いた後にそう言った。
「うん、あれは幼馴染の心菜って子で。」
僕は、机の上に置いていた、袋を一花に渡す。
「それ、一花にクリスマスプレゼント何がいいか、一緒に選んでもらってただけ。」
えっ、と一花言って、袋を開けた。
中からは、白いマフラーが出てくる。
「これ、私の欲しかったマフラー。どうして分かったの?」
固かった表情が、少し柔らかくなった。
「スマホでそのマフラーばっかり調べてたじゃん、そりゃ分かるよ。僕が選んだマフラーか、一花が欲しいと思ってるマフラーどっちが良いか心菜と選んでただけだよ。誤解させちゃってごめん。」
僕は謝罪の意を込めて、頭を下げる。
「ごめん、私こそ。私のためにそんなことしてくれてたなんて思ってなくて。」
今にも泣きそうな顔で、一花は胸の中に飛んできた。外から来たばかりの一花のもこもこのジャンバーは、まだ冷たかった。
「ううん、僕こそ。それよりもさ、どうやって盗撮したの?」
疑問にもっていたことを聞いた。
「あれはなぎさちゃんと遊びに行った時に、たまたま見かけたから。ごめん...。」
同じバイトの青山なぎさ。最近、バイトでもよく話していると思ったらそういうことだったのか...。
「ううん、じゃあそんなこと忘れてパーティ早くしよ。」
「そだね。あっ、私も蒼空君に渡すね。」
ガサガサとカバンの中から、袋を取り出す。
中を開けてみると、さっき渡したブランドの黒色のマフラー、つまり一花と色違い。こんな偶然あるのか、と嬉しくなる。
「ありがと。やっぱり考えてること一緒だよな。」
そう言って、小さく笑い合う。
「うん。ほらほらお菓子もジュースもいっぱい持ってきたんだから、はじめよ。」
僕たちは、お菓子を広げて、ジュースを注いで、切ない恋の映画をつける。
一緒に笑い合って、泣いて、また笑う。そんな幸せな時間はあっという間に過ぎた。
窓の外をチラリとみる。
もう、雪が降っていた。きれいな白い雪に、満月。
満月の前を、トナカイが引くソリに乗った、サンタがいた。そんな気がした。
12月25日。今日、この日は一花と僕の家でクリスマスパーティをする日。
なのに、2日前、喧嘩をしてしまった。
2日前をそっと思い出す。
その日は、バイトが終わった後一緒にファミレスに来ていた。
注文が終わり、食べ物が運ばれてくるまで宿題をすることにした。
やばい課題が溜まってる。しかも最近整理整頓があまり出来ていない...。
「ねえ、何それ?カバンの中は綺麗にしなって言ったじゃん。しかもいつも綺麗にしてあげてるし。次からはちゃんとするって言ってたよね?」
帰る前に、店長に少しだけ注意された一花は機嫌が悪く、さらにこの汚さを見て機嫌が悪くなってしまったみたいだ。
「ごめん、最近忙してくてさ。」
忙しい、という言葉に引っかかったのか、こっちを見ていた目がキツくなった。
「忙しい?だったら整理整頓とかはなんでも良いわけ?良い加減高校生なんだからちゃんとしたら?」
僕だってきちんとしないといけないことぐらい分かってる。でも保護者でもないのに、そんなこと言わなくていいだろ、と思ってしまう。
「分かってる。」
「あとさ、何この溜まってる課題。何のために高校行ってるか分かってるの?バイト重視じゃないんだかるさ。」
課題をカバンから取り出して、手に持ちながら一花はそう言った。
「分かってるって。それはさ僕自身の問題であって、一花には関係ないから。」
「関係ない?じゃあ関係ある話しよっか?」
そう言って一花はポケットからスマホを取り出した。やばいどんどん機嫌が悪くなっている...互いに...。
「これ見て。」
すると、僕と友達が歩いている写真が写っていた。
「これ誰?浮気?」
写っていたのは、家の近くに住んでいる幼馴染の心菜だった。浮気でもないし、勝手に僕をつけて盗撮していゆことに少し怒りがあった。
理由を説明する間もなく、一花は立ち上がった。
「私もう食べ物いらないから、どうぞ食べて。お金置いていくから。」
「ちょっ、どゆこと?」
僕の言葉を無視して、一花は店を出た。一花が座っていた椅子には1000円札だけがあった。
心菜とは、クリスマスのプレゼントを買うためだったのに...。
このまま追いかけたところで、多分話なんか聞いてくれないと思う。
だから、LINEを開き、メッセージを送ることにした。
(蒼空:さっきの人は幼馴染だから、何も浮気とかじゃないです。ちゃんと話がしたいので、約束してた25日に僕の家来て下さい。待ってます。)
きっと来てくれるだろうと信じて、僕は今待っている。家族を追い出してまでして...。
掃除が終わり、ソファに座ってスマホを触っているとインターフォンが鳴る。
心臓がドキッとして、足が少しだけ震える。
“応答”のボタンを押すと、そこにいたのは…一花だった。
思いたくもないけど、別れるなんて言われたらどうしよう、実はあんな所がが嫌いだったとか言われたらどうしよう。いろんな言葉を考えてしまう。
深呼吸をして、扉を開ける。
いつもとは少し違う雰囲気をまとった、一花がいた。
「来てくれて、ありがとう。じゃあ入って。」
一花は靴を脱ぎ、何も言わずに中へ入った。
「あのさ、早くあれはどう言うことか話してくれる?」
一花は床に荷物を置いた後にそう言った。
「うん、あれは幼馴染の心菜って子で。」
僕は、机の上に置いていた、袋を一花に渡す。
「それ、一花にクリスマスプレゼント何がいいか、一緒に選んでもらってただけ。」
えっ、と一花言って、袋を開けた。
中からは、白いマフラーが出てくる。
「これ、私の欲しかったマフラー。どうして分かったの?」
固かった表情が、少し柔らかくなった。
「スマホでそのマフラーばっかり調べてたじゃん、そりゃ分かるよ。僕が選んだマフラーか、一花が欲しいと思ってるマフラーどっちが良いか心菜と選んでただけだよ。誤解させちゃってごめん。」
僕は謝罪の意を込めて、頭を下げる。
「ごめん、私こそ。私のためにそんなことしてくれてたなんて思ってなくて。」
今にも泣きそうな顔で、一花は胸の中に飛んできた。外から来たばかりの一花のもこもこのジャンバーは、まだ冷たかった。
「ううん、僕こそ。それよりもさ、どうやって盗撮したの?」
疑問にもっていたことを聞いた。
「あれはなぎさちゃんと遊びに行った時に、たまたま見かけたから。ごめん...。」
同じバイトの青山なぎさ。最近、バイトでもよく話していると思ったらそういうことだったのか...。
「ううん、じゃあそんなこと忘れてパーティ早くしよ。」
「そだね。あっ、私も蒼空君に渡すね。」
ガサガサとカバンの中から、袋を取り出す。
中を開けてみると、さっき渡したブランドの黒色のマフラー、つまり一花と色違い。こんな偶然あるのか、と嬉しくなる。
「ありがと。やっぱり考えてること一緒だよな。」
そう言って、小さく笑い合う。
「うん。ほらほらお菓子もジュースもいっぱい持ってきたんだから、はじめよ。」
僕たちは、お菓子を広げて、ジュースを注いで、切ない恋の映画をつける。
一緒に笑い合って、泣いて、また笑う。そんな幸せな時間はあっという間に過ぎた。
窓の外をチラリとみる。
もう、雪が降っていた。きれいな白い雪に、満月。
満月の前を、トナカイが引くソリに乗った、サンタがいた。そんな気がした。