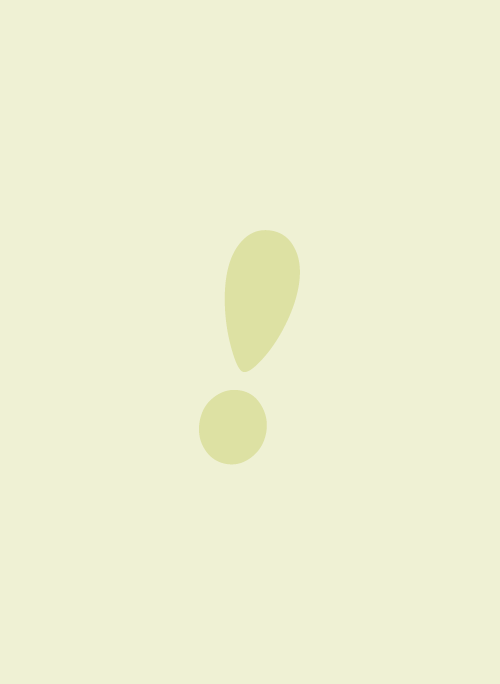二十代後半の彼は、まるで二つの世界を行き来する旅人のようだった。
音楽の世界と現実の世界。
二十代前半のように、同時には生きることが出来なかった。
夢と現実の狭間で、彼はいつも揺れていた。
そんなある日、一本の電話が鳴った。
「……あいつ、事故で亡くなった」
長距離仲間の死、信じられなかった。
昨日まで笑っていた仲間が、もうこの世にいない。
高速道路のどこかで、突然命の灯火が消えた。
トラックの運転席に座ると、やけに空しく感じた。
深夜の高速道路を走るたびに無線で、 「おい、居眠りするなよ」 と笑っていた声が、耳の奥で響いた。
彼は思った。
「俺は、何がしたいのか」
夢を追い続ける自分。
家庭を守れなかった自分。
そして、仲間を失った現実。
そのすべてが、胸に重くのしかかった。
やがて、彼は静かにギターを置いた。
三十二歳。
バンド活動の終わりだった。
メンバーは形を変え、オリジナルメンバーは彼だけだった。
気がつけばバンドのすべてを背負っていた。
ステージに立つ夢は、確かに形になった。
雑誌にも載った。
テレビにも出た。
作品も残した。
だが、夢の先にあるはずだった“未来”は、仲間の死とともに、どこか遥か遠くへ消えていった。
「もう、終わりにしよう」
その言葉は、誰に向けたものでもなく、自分自身に向けた静かな宣告だった。
だが、夢を手放した彼の胸には、新しい空白が生まれた。
その空白を埋めるように、彼は次の道を探し始める。
そして―― その道は、彼を思いもよらない世界へと導いていく。
音楽の世界と現実の世界。
二十代前半のように、同時には生きることが出来なかった。
夢と現実の狭間で、彼はいつも揺れていた。
そんなある日、一本の電話が鳴った。
「……あいつ、事故で亡くなった」
長距離仲間の死、信じられなかった。
昨日まで笑っていた仲間が、もうこの世にいない。
高速道路のどこかで、突然命の灯火が消えた。
トラックの運転席に座ると、やけに空しく感じた。
深夜の高速道路を走るたびに無線で、 「おい、居眠りするなよ」 と笑っていた声が、耳の奥で響いた。
彼は思った。
「俺は、何がしたいのか」
夢を追い続ける自分。
家庭を守れなかった自分。
そして、仲間を失った現実。
そのすべてが、胸に重くのしかかった。
やがて、彼は静かにギターを置いた。
三十二歳。
バンド活動の終わりだった。
メンバーは形を変え、オリジナルメンバーは彼だけだった。
気がつけばバンドのすべてを背負っていた。
ステージに立つ夢は、確かに形になった。
雑誌にも載った。
テレビにも出た。
作品も残した。
だが、夢の先にあるはずだった“未来”は、仲間の死とともに、どこか遥か遠くへ消えていった。
「もう、終わりにしよう」
その言葉は、誰に向けたものでもなく、自分自身に向けた静かな宣告だった。
だが、夢を手放した彼の胸には、新しい空白が生まれた。
その空白を埋めるように、彼は次の道を探し始める。
そして―― その道は、彼を思いもよらない世界へと導いていく。