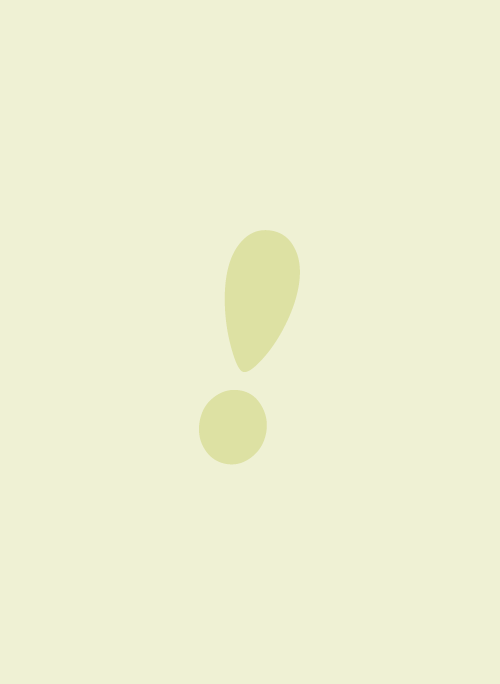昭和四十年代の地方都市。
冬の朝はいつも薄曇りで、白い息が長く伸びた。
その灰色の空の下で、一人の男の人生は静かに始まった。
父は地方公務員――鉄道の運転士だった。
制服に袖を通し、制帽をかぶり、まだ薄暗い早朝の駅へ向かう父の背中は、少年にとって“ヒーロー”そのものだった。
「お父さんみたいに電車を運転したい」
それが、少年が初めて抱いた夢だった。
父の帰宅後、制服の胸ポケットに差し込まれた時刻表をこっそり開き、線路の上を走る電車を想像した。
駅に停まるたびに人々の生活を運び、遠くの街へとつながっていく鉄路。
そのすべてが、少年には眩しく見えた。
しかし、現実は静かに別の方向へ進み始める。
小学生の頃、彼は学力が良かった。
周囲の期待もあり、当時としては珍しい進学塾に通い、中学受験に挑むことになった。
父のような運転士になりたいという夢は、いつしか「もっと上を目指せ」という大人たちの声に押し込められていった。
だが、結果は不合格。
戦前生まれの女性教師は、少年の心をえぐるように言い放った。
「あなたには失望したわ。期待外れね」
その一言は、幼い心に深い傷を刻んだ。
胸の奥に、黒い石のようなものが沈んでいく。
その石は、これから長い年月をかけて彼の人生に影を落とすことになる。
少年は、初めて「自分は価値がないのかもしれない」と思った。
だが、夢は完全には消えなかった。
父の運転する電車の音、レールの響き、駅のアナウンス。
それらは少年の胸の奥で、静かに灯り続けていた。
そして―― その灯りは、やがて“別の夢”へと姿を変えていく。
冬の朝はいつも薄曇りで、白い息が長く伸びた。
その灰色の空の下で、一人の男の人生は静かに始まった。
父は地方公務員――鉄道の運転士だった。
制服に袖を通し、制帽をかぶり、まだ薄暗い早朝の駅へ向かう父の背中は、少年にとって“ヒーロー”そのものだった。
「お父さんみたいに電車を運転したい」
それが、少年が初めて抱いた夢だった。
父の帰宅後、制服の胸ポケットに差し込まれた時刻表をこっそり開き、線路の上を走る電車を想像した。
駅に停まるたびに人々の生活を運び、遠くの街へとつながっていく鉄路。
そのすべてが、少年には眩しく見えた。
しかし、現実は静かに別の方向へ進み始める。
小学生の頃、彼は学力が良かった。
周囲の期待もあり、当時としては珍しい進学塾に通い、中学受験に挑むことになった。
父のような運転士になりたいという夢は、いつしか「もっと上を目指せ」という大人たちの声に押し込められていった。
だが、結果は不合格。
戦前生まれの女性教師は、少年の心をえぐるように言い放った。
「あなたには失望したわ。期待外れね」
その一言は、幼い心に深い傷を刻んだ。
胸の奥に、黒い石のようなものが沈んでいく。
その石は、これから長い年月をかけて彼の人生に影を落とすことになる。
少年は、初めて「自分は価値がないのかもしれない」と思った。
だが、夢は完全には消えなかった。
父の運転する電車の音、レールの響き、駅のアナウンス。
それらは少年の胸の奥で、静かに灯り続けていた。
そして―― その灯りは、やがて“別の夢”へと姿を変えていく。