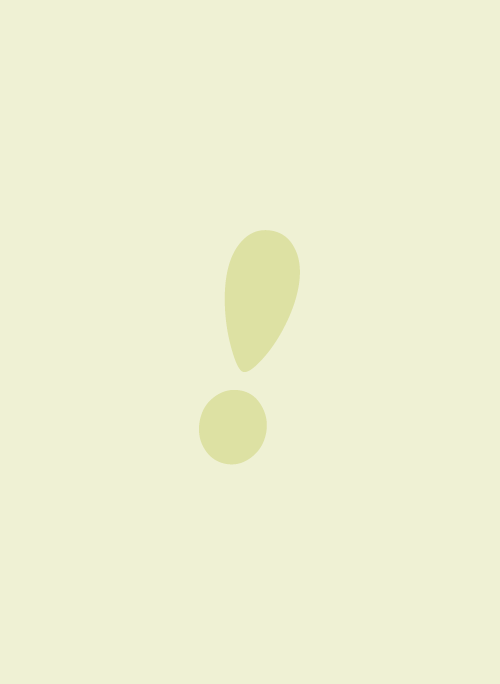比叡山の朝は、静かだ。
風の音も、鳥の声も、すべてが遠くで響く。
山の空気は冷たく、澄みきっていて、まるで人の心の奥底をそのまま映し出す鏡のようだった。
彼は、毎年必ずこの山に戻ってくる。
高野山の阿闍梨との仏縁、比叡山千日回峰行大阿闍梨との出会い、
そして「涓塵会」の活動――
それらはすべて、彼の人生が“精神の道”へと向かう必然だった。
山に入るたび、彼は自分の過去と向き合う。
今までの人生のすべてが、彼の中で“業”として静かに積み重なっていた。
だが、彼は言う。
「後悔はない」
それは強がりではない。
本心だった。
過去のどの瞬間も、
どの選択も、どの痛みも、今の自分を形づくるために必要だった。
そして、彼は続ける。
「苦労もない」
人はよく「苦労した」と言う。
だが彼にとって、苦労とは“避けたいもの”ではなく、“生きるための燃料”だった。
苦しみも、挫折も、裏切りも、すべてが彼を前へ押し出した。
では、何が残ったのか。
彼は静かに笑う。
「あるのは未練、そして欲だ」
未練――
それは、まだやり残したことがあるという証。
もっと良くなりたい、もっと深く知りたい、もっと遠くへ行きたい。
その想いが、彼を山へと向かわせる。
欲――
それは、ただの物欲ではない。
“生きたい”という強烈な生命力。
“もっと成長したい”という渇望。
“人の役に立ちたい”という願い。
それらはすべて、彼の中で静かに燃え続けている。
比叡山の冷たい空気を吸い込みながら、彼は思う。
――俺はまだ終わっていない。
人生は、何度でもやり直せる。
何度でも立ち上がれる。
そして、何度でも変われる。
彼は今日も山を歩く。
過去の業を抱えながら、それでも前へ進むために。
その背中は、かつて憧れた鉄道運転士であった亡き父の背中と同じように、まっすぐで、力強かった。
風の音も、鳥の声も、すべてが遠くで響く。
山の空気は冷たく、澄みきっていて、まるで人の心の奥底をそのまま映し出す鏡のようだった。
彼は、毎年必ずこの山に戻ってくる。
高野山の阿闍梨との仏縁、比叡山千日回峰行大阿闍梨との出会い、
そして「涓塵会」の活動――
それらはすべて、彼の人生が“精神の道”へと向かう必然だった。
山に入るたび、彼は自分の過去と向き合う。
今までの人生のすべてが、彼の中で“業”として静かに積み重なっていた。
だが、彼は言う。
「後悔はない」
それは強がりではない。
本心だった。
過去のどの瞬間も、
どの選択も、どの痛みも、今の自分を形づくるために必要だった。
そして、彼は続ける。
「苦労もない」
人はよく「苦労した」と言う。
だが彼にとって、苦労とは“避けたいもの”ではなく、“生きるための燃料”だった。
苦しみも、挫折も、裏切りも、すべてが彼を前へ押し出した。
では、何が残ったのか。
彼は静かに笑う。
「あるのは未練、そして欲だ」
未練――
それは、まだやり残したことがあるという証。
もっと良くなりたい、もっと深く知りたい、もっと遠くへ行きたい。
その想いが、彼を山へと向かわせる。
欲――
それは、ただの物欲ではない。
“生きたい”という強烈な生命力。
“もっと成長したい”という渇望。
“人の役に立ちたい”という願い。
それらはすべて、彼の中で静かに燃え続けている。
比叡山の冷たい空気を吸い込みながら、彼は思う。
――俺はまだ終わっていない。
人生は、何度でもやり直せる。
何度でも立ち上がれる。
そして、何度でも変われる。
彼は今日も山を歩く。
過去の業を抱えながら、それでも前へ進むために。
その背中は、かつて憧れた鉄道運転士であった亡き父の背中と同じように、まっすぐで、力強かった。