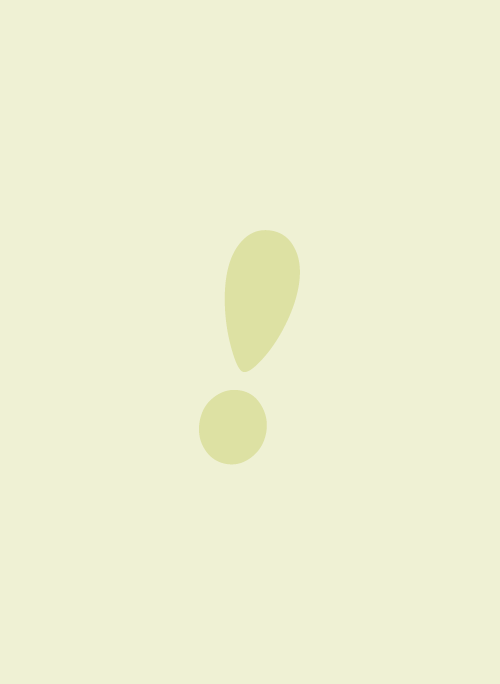労働組合を離れたとき、彼の胸にはひとつの想いが残っていた。
もう一度、経営者として勝負したい、自分の力で未来を切り開きたい、と。
その想いは、音楽を追っていた頃と同じ熱を帯びていた。
そんな彼の前に、運命の出会いが訪れる。
四十四歳。
創業を志す仲間と出会い、彼は再び経営の世界へ足を踏み入れた。
選んだ道は―― 遺品整理業。
最初は、ただの仕事だった。
だが、現場に立つたびに、彼は気づいていく。
孤独死した部屋に残された手紙。
誰にも看取られずに消えた命の痕跡。
家族に伝えられなかった想い。
「人は、こんなにも静かに消えていくのか」
その現実は、彼の胸に深く突き刺さった。
遺品整理は、ただ物を片づける仕事ではない。
“その人の人生を最後に受け止める仕事”だった。
彼は、亡くなった人の尊厳を守るために、遺族の心に寄り添うために、 一つひとつの現場に誠実に向き合った。
その姿勢は、やがて社会の目に留まる。
平成二十九年、仏教タイムスに掲載。
遺品整理を通して見える“死と向き合う現場”を語った記事は、多くの読者の心を揺さぶった。
令和元年、毎日新聞全国版に掲載。
孤独死の増加と、遺品整理の現場で見える社会の課題。
彼の言葉は、全国へと広がっていった。
さらに、孤独死を扱う書籍「孤独死大国」「これからの葬儀の話をしよう」「超孤独死社会」などに取材され、業務を行う姿が掲載された。
彼の語る現場のリアルは、単なる仕事の話ではなく、“現代社会の影”そのものだった。
気づけば、彼は、「遺品整理の専門家」として知られる存在になっていた。
だが、彼の胸には、もうひとつの問いが生まれていた。
――俺は、何のためにこの仕事をしているのか。
遺品整理の現場で向き合う“死”は、 彼自身の過去の影―― 音楽の夢、家庭の崩壊、破産、闇との接点―― そのすべてを静かに照らし出していた。
そして、彼の人生は再び大きく動き出す。
ある人物との出会いが、 彼を“精神の世界”へと導いていく。
もう一度、経営者として勝負したい、自分の力で未来を切り開きたい、と。
その想いは、音楽を追っていた頃と同じ熱を帯びていた。
そんな彼の前に、運命の出会いが訪れる。
四十四歳。
創業を志す仲間と出会い、彼は再び経営の世界へ足を踏み入れた。
選んだ道は―― 遺品整理業。
最初は、ただの仕事だった。
だが、現場に立つたびに、彼は気づいていく。
孤独死した部屋に残された手紙。
誰にも看取られずに消えた命の痕跡。
家族に伝えられなかった想い。
「人は、こんなにも静かに消えていくのか」
その現実は、彼の胸に深く突き刺さった。
遺品整理は、ただ物を片づける仕事ではない。
“その人の人生を最後に受け止める仕事”だった。
彼は、亡くなった人の尊厳を守るために、遺族の心に寄り添うために、 一つひとつの現場に誠実に向き合った。
その姿勢は、やがて社会の目に留まる。
平成二十九年、仏教タイムスに掲載。
遺品整理を通して見える“死と向き合う現場”を語った記事は、多くの読者の心を揺さぶった。
令和元年、毎日新聞全国版に掲載。
孤独死の増加と、遺品整理の現場で見える社会の課題。
彼の言葉は、全国へと広がっていった。
さらに、孤独死を扱う書籍「孤独死大国」「これからの葬儀の話をしよう」「超孤独死社会」などに取材され、業務を行う姿が掲載された。
彼の語る現場のリアルは、単なる仕事の話ではなく、“現代社会の影”そのものだった。
気づけば、彼は、「遺品整理の専門家」として知られる存在になっていた。
だが、彼の胸には、もうひとつの問いが生まれていた。
――俺は、何のためにこの仕事をしているのか。
遺品整理の現場で向き合う“死”は、 彼自身の過去の影―― 音楽の夢、家庭の崩壊、破産、闇との接点―― そのすべてを静かに照らし出していた。
そして、彼の人生は再び大きく動き出す。
ある人物との出会いが、 彼を“精神の世界”へと導いていく。