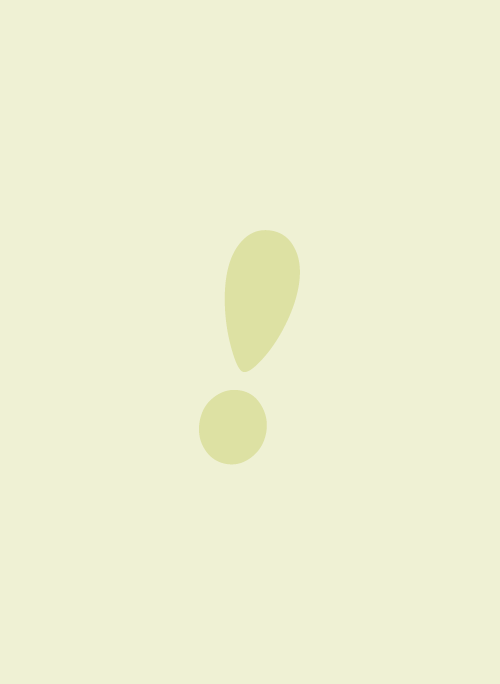人は、生まれた瞬間から、見えない塵を抱いて歩き始める。
それは業とも呼ばれ、未練とも呼ばれ、欲とも呼ばれる。
名は違えど、どれも人が人として生きるための重さであり、温度である。
彼もまた、その塵を抱えて生きてきた。
夢に焦がれ、家族を失い、闇に触れ、仲間のために拳を突き上げ、 孤独死の現場で“生と死”の境界に立ち続けた。
そして、山に導かれた。
比叡の峰、高野の森。
静寂の中で、彼は自らの塵を見つめ、抱きしめ、そしてそっと払う術を学んでいった。
後悔はない。
苦労という言葉も、彼には似合わない。
ただ、胸の奥に残るのは―― 消えぬ未練と、尽きぬ欲。
それらは煩悩ではなく、彼にとって“生きる証”だった。
この物語は、波乱の人生を語るためのものではない。
塵を抱き、塵を払いながら、それでも歩き続ける一人の人間の記録である。
静かに幕は上がる。
彼の半世紀を照らす光と影が、いま語られようとしている。
それは業とも呼ばれ、未練とも呼ばれ、欲とも呼ばれる。
名は違えど、どれも人が人として生きるための重さであり、温度である。
彼もまた、その塵を抱えて生きてきた。
夢に焦がれ、家族を失い、闇に触れ、仲間のために拳を突き上げ、 孤独死の現場で“生と死”の境界に立ち続けた。
そして、山に導かれた。
比叡の峰、高野の森。
静寂の中で、彼は自らの塵を見つめ、抱きしめ、そしてそっと払う術を学んでいった。
後悔はない。
苦労という言葉も、彼には似合わない。
ただ、胸の奥に残るのは―― 消えぬ未練と、尽きぬ欲。
それらは煩悩ではなく、彼にとって“生きる証”だった。
この物語は、波乱の人生を語るためのものではない。
塵を抱き、塵を払いながら、それでも歩き続ける一人の人間の記録である。
静かに幕は上がる。
彼の半世紀を照らす光と影が、いま語られようとしている。