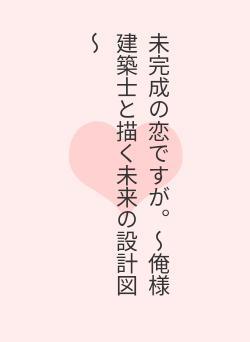子ども図書館の開館は明日だ。
屋根裏に続く急角度の階段を上がる。
足を置くたびに軋む音がする踏み面は、補強したうえで残した。この音もまた、慈しむべき古さだと考えたからだ。
低い屋根の下に敷いた畳に大の字に寝転がる。張り替えたばかりの畳は若く、草の青い匂いが呼吸のたびに胸に入り込んだ。
朝から続いたオープン準備で、少しだけ体が重い。
大きく深呼吸をすると、だるさの底がわずかに持ち上がった。
幼い時も、この屋根裏が俺にとっての癒しの場所だった。
天井は低く、屋根裏特有の圧迫感があるはずなのに、不思議と息は苦しくない。
屋根の傾斜に沿って斜めに切り取られた真四角の窓を見上げると、ちょうど夕方が夜に溶け変わるところだった。
子どものころ、この窓が好きだった。仰向けになって、ここから星を数えた。街灯も少なく、夜空は今よりずっと濃くて、手を伸ばせば触れられそうだった。
(大人になって、また戻ってこられるなんてな)
明日、子ども図書館としてこの家は正式に生まれ変わる。
古い柱も、軋む階段も、そのまま残した。失われたと思っていた場所が、もう一度息をし始めたことは、素直にうれしい。
なのに、胸の奥に沈むこの重さはなんだ。
「……終わり、か」
声は、屋根裏の薄闇に吸い込まれた。
終わる。
消える。
プロジェクトも、彼女との接点も。
準備のたびに顔を合わせ、言葉を交わすたび、宮本を好きになっていた。
何気ない一言、視線を逸らす癖、少し遅れて見せる笑顔。その全部が、俺の中に積み重なっていった。
「では、また」
丁寧に頭を下げながら言う声が、耳の奥で何度も繰り返される。明日が来たら、「また」はない。
顔が近づいた瞬間、彼女がわずかに頬を染めたことがあった。これまで、触れた手を拒まれたこともない。それでも、このまま告白してうまくいくと信じられるほど、楽観的にはなれなかった。
この気持ちを打ち明けたら、すべてが壊れるかもしれない。でも、何も言わなければ、確実に終わる。
(どうすればいい……)
自分に問いかけても、答えは返ってこない。
ただ、彼女が欲しい。それだけは、はっきりしていた。
視界が滲み、考えは途中で途切れる。気づいたときには、畳の香りに包まれたまま、俺は緩い眠りに落ちていた。
「……黒川さん?」
小さく抑えた声に、眠りの底から浮上する。
目を開けると、斜めの天井に切り取られた窓の色が、さっきより一段濃くなっていた。
「ああ……うとうとしてた」
遠慮がちに立っている宮本に、「ここ、寝ころんでみろよ」と隣の畳を軽く叩く。彼女がそっと身を横たえると、畳がかすかに鳴った。
「ほら、あそこ」
指を伸ばして、窓の端で輝く一番星を指す。
「昔から、ここから見る星が好きでさ」
しばらく、何も言わずに並んで夜を待つ。
風が屋根を撫で、遠くで大樹が葉を揺らす音がした。
(気持ちを伝えるのなら、今、じゃないのか?)
でも、彼女が俺から去る未来が怖い。
「なあ……お前にとって、このプロジェクトはなんだった?」
宮本にそう問うたのは、もし俺の想いが届かなかったとしても、これまで俺と過ごした時間が、彼女の中で無意味にならないでほしかったからだ。
一緒に悩み、迷い、形にしたこのプロジェクトを通じて、彼女が何かを手に入れていたなら、それでいいと思った。
せめて、その場に自分がいたことだけは、消えないでほしかった。彼女が少しだけ前に進めた、その瞬間に立ち会った一人として、俺の存在が記憶の端に残っていてほしかった。
もっと先の人生で、ふと振り返ったときでいい。
あの転機に、黒川という男がいたと思い出してもらえたら、それで救われる気がした。
恋人になれなくても、選ばれなくても、出会った意味はあったのだと。
彼女の人生のどこかに、自分の足跡が残るのだと信じたかった。
宮本は少し考え、胸の上で手を組んだ。
「はじめは、正直、くじけそうでした。でも、黒川さんをはじめ、皆さんがいたから、やり遂げることができました。今は……地域整備課の仕事も、悪くないって思ってます」
一拍置いて、照れたように続けた。
「諦めてた絵も、また描き始めましたし」
宮本は、俺が思い描いていた通りの言葉を差し出してくれた。ひとつひとつの言葉が胸に雫のように落ちて、波立っていた感情が凪いでいく。
想いが叶わなくても、悔いはない。本気で思った。
「黒川さんにとっては?」
宮本にそう聞き返される。
思い出の家が生き返ったこと。でも、それだけじゃない。
「……お前に、会えたことが一番良かった」
見つめていた星が、一瞬、強く光った気がした。
もう、結果はどうでもいい。宮本の記憶の中に、俺は残る。
好きになった理由はひとつじゃなかった。
古民家での作業では、誰よりも早くやってきて窓を開け、空気を入れ替える。
立て込んだ話し合いの中でも、絵本の話題になると声をやわらげる。
思い返せば、どれも取るに足らない瞬間ばかりで、劇的に恋に落ちたわけではないけれど。
でも、そういう場面が重なるたび、気づけば視線は彼女を追った。
好きになろうとした覚えはない。
ただ、積み上がっていく時間の中でいつしか、とらわれた。
「……好きだ。俺と、付き合って、ください」
返事は、ない。
口を開けたり閉じたり、視線が行き場を失って揺れる。
否定じゃない、と直感した。
その戸惑いさえ、たまらなく愛おしい。気づけば腕を伸ばし、抱き寄せていた。
「“はい”か、“イエス”で答えろ。でなきゃ放さない」
俺のそばにいて欲しい。願いとは裏腹に、口をついて出る言葉はいつものわがままそのもの。でも、宮本は笑った。
「もう……強引ですね」
額と額をつけると、息が触れ合う。二人で笑う。
窓の向こうで、一番星が静かにきらめいていた。
屋根裏に続く急角度の階段を上がる。
足を置くたびに軋む音がする踏み面は、補強したうえで残した。この音もまた、慈しむべき古さだと考えたからだ。
低い屋根の下に敷いた畳に大の字に寝転がる。張り替えたばかりの畳は若く、草の青い匂いが呼吸のたびに胸に入り込んだ。
朝から続いたオープン準備で、少しだけ体が重い。
大きく深呼吸をすると、だるさの底がわずかに持ち上がった。
幼い時も、この屋根裏が俺にとっての癒しの場所だった。
天井は低く、屋根裏特有の圧迫感があるはずなのに、不思議と息は苦しくない。
屋根の傾斜に沿って斜めに切り取られた真四角の窓を見上げると、ちょうど夕方が夜に溶け変わるところだった。
子どものころ、この窓が好きだった。仰向けになって、ここから星を数えた。街灯も少なく、夜空は今よりずっと濃くて、手を伸ばせば触れられそうだった。
(大人になって、また戻ってこられるなんてな)
明日、子ども図書館としてこの家は正式に生まれ変わる。
古い柱も、軋む階段も、そのまま残した。失われたと思っていた場所が、もう一度息をし始めたことは、素直にうれしい。
なのに、胸の奥に沈むこの重さはなんだ。
「……終わり、か」
声は、屋根裏の薄闇に吸い込まれた。
終わる。
消える。
プロジェクトも、彼女との接点も。
準備のたびに顔を合わせ、言葉を交わすたび、宮本を好きになっていた。
何気ない一言、視線を逸らす癖、少し遅れて見せる笑顔。その全部が、俺の中に積み重なっていった。
「では、また」
丁寧に頭を下げながら言う声が、耳の奥で何度も繰り返される。明日が来たら、「また」はない。
顔が近づいた瞬間、彼女がわずかに頬を染めたことがあった。これまで、触れた手を拒まれたこともない。それでも、このまま告白してうまくいくと信じられるほど、楽観的にはなれなかった。
この気持ちを打ち明けたら、すべてが壊れるかもしれない。でも、何も言わなければ、確実に終わる。
(どうすればいい……)
自分に問いかけても、答えは返ってこない。
ただ、彼女が欲しい。それだけは、はっきりしていた。
視界が滲み、考えは途中で途切れる。気づいたときには、畳の香りに包まれたまま、俺は緩い眠りに落ちていた。
「……黒川さん?」
小さく抑えた声に、眠りの底から浮上する。
目を開けると、斜めの天井に切り取られた窓の色が、さっきより一段濃くなっていた。
「ああ……うとうとしてた」
遠慮がちに立っている宮本に、「ここ、寝ころんでみろよ」と隣の畳を軽く叩く。彼女がそっと身を横たえると、畳がかすかに鳴った。
「ほら、あそこ」
指を伸ばして、窓の端で輝く一番星を指す。
「昔から、ここから見る星が好きでさ」
しばらく、何も言わずに並んで夜を待つ。
風が屋根を撫で、遠くで大樹が葉を揺らす音がした。
(気持ちを伝えるのなら、今、じゃないのか?)
でも、彼女が俺から去る未来が怖い。
「なあ……お前にとって、このプロジェクトはなんだった?」
宮本にそう問うたのは、もし俺の想いが届かなかったとしても、これまで俺と過ごした時間が、彼女の中で無意味にならないでほしかったからだ。
一緒に悩み、迷い、形にしたこのプロジェクトを通じて、彼女が何かを手に入れていたなら、それでいいと思った。
せめて、その場に自分がいたことだけは、消えないでほしかった。彼女が少しだけ前に進めた、その瞬間に立ち会った一人として、俺の存在が記憶の端に残っていてほしかった。
もっと先の人生で、ふと振り返ったときでいい。
あの転機に、黒川という男がいたと思い出してもらえたら、それで救われる気がした。
恋人になれなくても、選ばれなくても、出会った意味はあったのだと。
彼女の人生のどこかに、自分の足跡が残るのだと信じたかった。
宮本は少し考え、胸の上で手を組んだ。
「はじめは、正直、くじけそうでした。でも、黒川さんをはじめ、皆さんがいたから、やり遂げることができました。今は……地域整備課の仕事も、悪くないって思ってます」
一拍置いて、照れたように続けた。
「諦めてた絵も、また描き始めましたし」
宮本は、俺が思い描いていた通りの言葉を差し出してくれた。ひとつひとつの言葉が胸に雫のように落ちて、波立っていた感情が凪いでいく。
想いが叶わなくても、悔いはない。本気で思った。
「黒川さんにとっては?」
宮本にそう聞き返される。
思い出の家が生き返ったこと。でも、それだけじゃない。
「……お前に、会えたことが一番良かった」
見つめていた星が、一瞬、強く光った気がした。
もう、結果はどうでもいい。宮本の記憶の中に、俺は残る。
好きになった理由はひとつじゃなかった。
古民家での作業では、誰よりも早くやってきて窓を開け、空気を入れ替える。
立て込んだ話し合いの中でも、絵本の話題になると声をやわらげる。
思い返せば、どれも取るに足らない瞬間ばかりで、劇的に恋に落ちたわけではないけれど。
でも、そういう場面が重なるたび、気づけば視線は彼女を追った。
好きになろうとした覚えはない。
ただ、積み上がっていく時間の中でいつしか、とらわれた。
「……好きだ。俺と、付き合って、ください」
返事は、ない。
口を開けたり閉じたり、視線が行き場を失って揺れる。
否定じゃない、と直感した。
その戸惑いさえ、たまらなく愛おしい。気づけば腕を伸ばし、抱き寄せていた。
「“はい”か、“イエス”で答えろ。でなきゃ放さない」
俺のそばにいて欲しい。願いとは裏腹に、口をついて出る言葉はいつものわがままそのもの。でも、宮本は笑った。
「もう……強引ですね」
額と額をつけると、息が触れ合う。二人で笑う。
窓の向こうで、一番星が静かにきらめいていた。