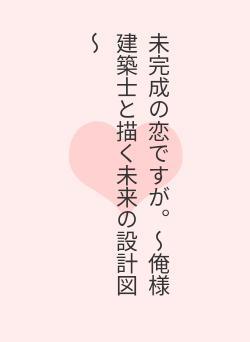いくら飲んでも酔いが回ってこなかった。
あおったグラスをダイニングテーブルに置くと、氷が乾いた音を立てた。
額をテーブルに伏せる。冷たい天板の温度が直に伝わってきて、頭がますます冴えてきた。
ひとことでいうなら。
“やっちまった”。
まぶたの奥に、肩を落とした宮本の姿が焼き付いている。
事務所にやってきた宮本の顔は強張っていた。悪い知らせを持ってきたのだ。
予算の変更があり、予定していた国産材を使える額を捻出できなくなった、代わりに、外材を使うことになった、そしてその手配は、副市長の一存で黒川建設――よりによって親父の会社――に任された、というのだ。
(なんで、俺になんの断りもなくそんなこと……)
相談さえしてくれれば、別の考えを提案できたかもしれないのに。
いや。
相談がなかったのは、市側に俺の意見を聞く気がなかったのではないか。
面倒な建築士を、この機に排除したかったのではないか。
不信感が頭をもたげる。
ここまで築き上げてきた計画が、根こそぎ崩れていく感覚だった。
宮本はこの展開をどう感じているのだろう。
「お前はどう思う」
「完成させることを目標とするなら、かなめの部分だけ国産材にするなど……そういう調整はできないかな、と」
彼女は伏し目がちに言った。
古さを装った演出や古いものを悪いと決めつけることを、宮本、お前は良しとするのか。
俺と宮本は足並みが揃っていると思っていた。
なのに……
口調は次第に強くなった。
「そっちは完成しさえすれば市民が喜ぶって思ってるのかもしれないけど、外材なんかで作ったら、近い将来必ずガタが来る。誰も責任をとらないお役人と違って、俺たち建築士は名前を出してモノを作ってるんだ。そんなものに自分の看板貼れるかよ」
しまいには、そう言って彼女を市側の他の人間と同じくくりにして事務所から去らせた。
(最低だな……俺は)
もう一口酒を飲もうとグラスに手を伸ばしたが、カラだ。
伏せた顔を今度は宙に向けて、盛大にため息を吐く。
俺は宮本の何を見てきたんだ。
彼女が、上役の意見に反対しないはずはない。きっと彼女なりに反論し、説得したのだろう。でも、対抗できるだけの策がなかったのだ。
先週見かけた広報誌には、子ども図書館のオープンの日付が大きく掲載されていた。木材の関係で先送りになれば、市はいくつもの問題を抱えることになる。
俺と宮本では、同じプロジェクトに参加していても立場が違う。
そもそも、古い木材と外材との相性なんて、宮本にわかる話じゃない。
なのに、責めてしまった。
どう考えても“謝る”一択だ。
『悠ちゃん、言い方きついから気をつけたほうがいいと思う。嫌われないようにね』
陽菜に言われた一言が思い出される。
忠告を受けていながら、俺は宮本を言葉の圧で押し切った。
(間違いなく嫌われただろ……)
ぐしゃぐしゃと頭を掻いて、またテーブルに突っ伏した。
(とにかく、謝ろう)
伏せたまま手探りでスマホを引き寄せ、指が止まる。俺は、彼女のプライベートの連絡先を知らない。
今さら気づくなんて。
距離が近づいているつもりでいた。
けれど、それは、仕事の中だけの話だ。
謝りたいと思った、この瞬間に連絡が取れない。
それだけで、現実を突きつけられた気がした。
親しいつもりでいただけで、踏み込めるほどの距離には、まだ至っていなかったのだと、胸の奥が重くなる。
俺はスマホを握ったまま、もう一度、テーブルに顔を伏せた。
そのとき、手のひらの中のスマホが鳴りだした。画面には『親父』の二文字が並んでいる。
「なんだよ、こんな時に」
俺はひとりごちた。父親とは、俺が事務所を立ち上げたときから連絡を取り合っていない。もともと俺は父親の会社で働いていたが、建築士としての考え方が違いすぎて、当時は顔を合わせれば言い争いになっていた。
3年ぶりの電話に身構える。
でも、ちょうどいい。今回の外材の件で、言ってやりたいことがあった。
数回目のコールで液晶をスワイプする。
「悠真、久しぶりだな。元気にしてたか」
「ああ。……親父は」
「ぼちぼちだな。まあ、歳はとった」
電話越しに、小さく笑う気配が感じられた。
「で、何の用? というか、俺も用事があった。明日、そっちに行こうと思ってたとこだ」
「穂坂の図書館のことかな?」
「……わかってるなら、余計な事、するなよ。あの家をつぶす気か? 古い国産材と外材なんて相性が悪すぎる。使ったとしても、ただ古っぽくペイントした家なんて、俺には絶対建てられない。キャンセルだ」
不快感を隠しもせずに、俺は言った。けれども、答える親父の声は笑いを含んでいる。
「心配するな。キャンセル済みだ」
「は? なんだ、それ」
「今のお前と同じ勢いと同じ言葉で、キャンセルを頼み込んできた女性がいてね。私としては、想定外だったが。確か……地域整備課の宮本さん、とか」
息が止まった。
(宮本? なんで彼女が黒川建設に?)
俺はスマホを握りこんだ。
「ひとりで? 宮本が?」
「そうだよ。気の毒に。あらかた、副市長に『キャンセルするなら自分で話をつけてこい』とでも言われたんじゃないか」
もともと引っ込み思案の宮本が、副市長に直談判し、黒川建設にキャンセルの交渉に行くなんて。
どれほどに自分を奮い立たせたことだろう。
あの時、宮本を責めるのではなく、なぜ、お前の立場なら仕方なかった、俺が何とかすると言えなかったのか。
……俺のせいだ。どう宮本に詫びればいい。俺の思いを理解してくれていたのに、彼女ひとりを矢面に立たせた。
「それで、どうするつもりだ。木材は何を使う?」
なぞかけのように、親父に問われた。
悔しいが、すぐには答えられない。
でも、俺はきっぱりと言い切った。
「探してみせる。何としてでも」
宮本は、俺に幻滅しているだろう。
けれど、これで終わりにしたくない。彼女との仕事も、彼女への想いも。
謝る。
代わりの木材を探す。
少なくともそれが、俺がいま示すべき、宮本への誠意だった。