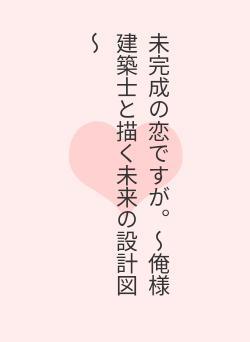桜色の唇を小さく開いて眠る莉央の肩に、そっと触れる。
彼女は気だるそうに片目だけを開き、すぐに眉根を寄せた。
「……ん?……黒川、さん?」
まだ夢の続きを引きずっている声だった。
「朝ごはんできたぞ」
「へ?」
無防備な顔の額にキスをすると、ぼんやりと焦点が定まらなかった目がみるみる見開かれた。
勢いをつけて直角に上半身を起こした次の瞬間、今度はあらわになった自分の胸元を見下ろして、叫ぶ。
「わ、わあ!」
反射的にブランケットを頭からかぶって、莉央は完全な籠城体制に入った。
朝の静けさを破る小さな騒動に、俺は声をたてて笑った。
ブランケットの奥から、消え入りそうな声が聞こえてくる。
「えっと……いったいどうすれば?」
「とりあえず、そうだな……」
寝室にあるクローゼットに向かい、白いシャツを取り出して、ベッドの上にふわり、空気を含ませるようにして掛ける。
「これ、着ていいよ」
ブランケットの端がわずかに持ち上がる。
おずおずと顔の上半分だけをのぞかせた莉央が、瞳をきゅっと細めた。
「んーっ、おいしいです。悠真さんって、お料理までできるんですね」
俺のシャツを無造作に腕まくりした莉央が、クロックムッシュを両手で持ったまま目を輝かせる。
「料理って言えるものでもないだろ」
「いえいえ、外はカリッとしてるのに、中はふわふわで、すごいですよ」
向かいの席で、俺はコーヒーを口に含んだ。
休日の穏やかな朝陽が満ちる部屋。
焼き立てのパンの香りと、湯気がたつコーヒーの匂い。そして、柔らかく笑う莉央。
この何気ない風景を失くしたくない。
「これ、渡しとく」
俺は、さっきから手のひらで温めていたそれをテーブルに置き、莉央の目の前に滑らせた。
「鍵?」
莉央が首を傾げる。
「いつでも、ここに来ていい」
彼女は目をしばたたかせた。
やがてゆっくりと表情がほどけ、笑みに変わっていく。
鍵には家の形に切り取られた木製のキーホルダーが付けてある。
「穂坂杉、ですか?」
「正解。俺が作った」
「わあ……」
そう言うと莉央は鍵をそっと両手で包み、胸に当てた。
「ありがとうございます」
その仕草があまりにも愛おしくて。
この部屋に、彼女がいる夜が、朝が、少しずつ増えていく。
そういう日々を、もう想像ではなく、現実として思い描けた。
俺は、窓に目を向ける。
差し込む光は昨日と同じはずなのに、確かに昨日とは違う朝だった。
彼女との夜を越えた先にあった、初めての朝。
その柔らかい光の中に、ふたりで並んで歩く未来が確かに続いている気がした。