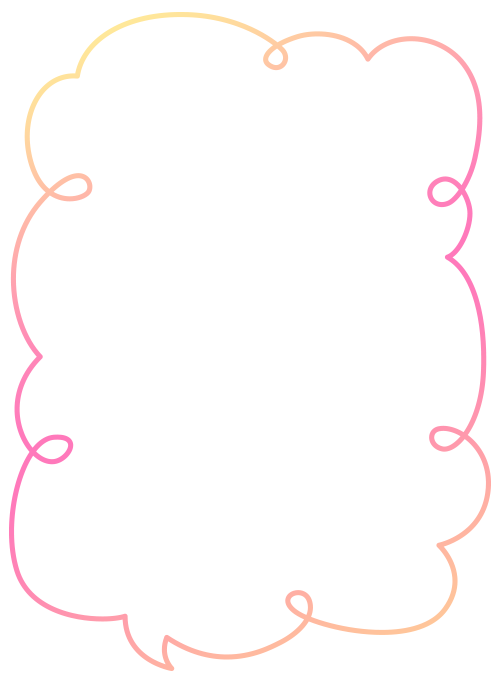「私も、律さんといると、
物語みたいだなって思うんです。
自分の人生なのに、
『こんな場面、書けない』ってくらい、
胸がいっぱいになることが、
何度もありました」
「……」
「だから、その……
はい。よろしくお願いします」
最後の「お願いします」は、
とても小さかったけれど、
風に消えずに、
律の胸に真っ直ぐ届きました。
そっと、二人の手が触れ合う。
今度は、
誰も謝らなかった。
指先を少し絡めるように握ってみると、
蘭の手は、
驚くほどあたたかかった。
丘の上のベンチから見える街は、
夕焼けに少しずつ染まり始めている。
この先、
どんな季節が来ても、
きっとこの日の匂いと、
空の色と、
手のぬくもりを思い出すだろう——。
そんな予感が、
二人の間に、
新しい物語の始まりとして
そっと横たわりました。
物語みたいだなって思うんです。
自分の人生なのに、
『こんな場面、書けない』ってくらい、
胸がいっぱいになることが、
何度もありました」
「……」
「だから、その……
はい。よろしくお願いします」
最後の「お願いします」は、
とても小さかったけれど、
風に消えずに、
律の胸に真っ直ぐ届きました。
そっと、二人の手が触れ合う。
今度は、
誰も謝らなかった。
指先を少し絡めるように握ってみると、
蘭の手は、
驚くほどあたたかかった。
丘の上のベンチから見える街は、
夕焼けに少しずつ染まり始めている。
この先、
どんな季節が来ても、
きっとこの日の匂いと、
空の色と、
手のぬくもりを思い出すだろう——。
そんな予感が、
二人の間に、
新しい物語の始まりとして
そっと横たわりました。