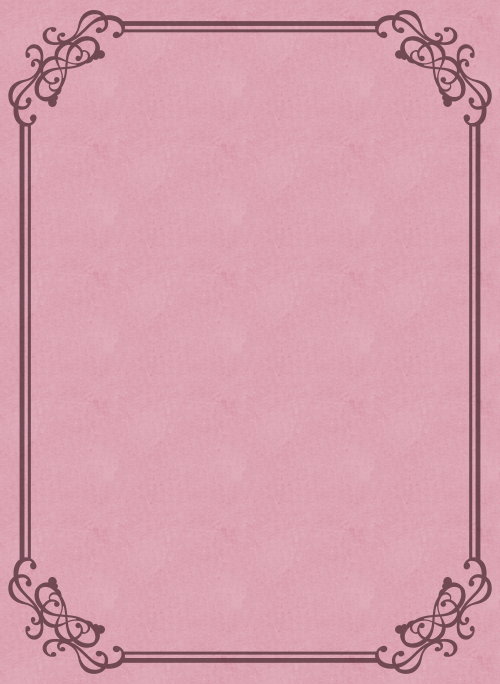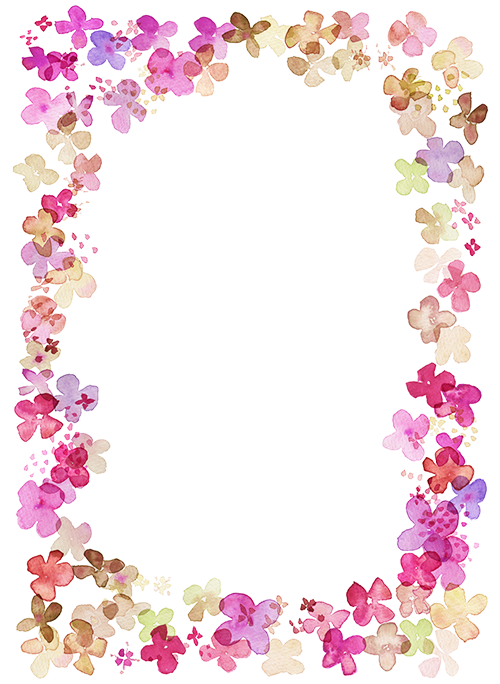アパートの2階、角部屋。かれこれ7年、同じ隣の部屋に住む佐藤さんは、今日も23時過ぎに帰宅する。鍵の音がして、5秒後にインターホンが鳴る。
「佐藤です。悪いんだけど、電池切れたみたいで……」
いつものセリフ。私は玄関を開けて、予備のリモコンを無言で渡す。佐藤さんは「助かる、ほんと毎回ごめん」と小さく頭を下げて、濡れた傘をビニール袋に入れてから自分の部屋に戻っていく。これが私たちの、ほぼ全ての会話だった。
でも私は知っている。佐藤さんが風邪を引いた週は、ゴミ出しの朝だけ私のゴミ箱が空っぽになっていること。私が夜勤明けでフラフラの日は、ドアノブにコンビニの温かいお茶がぶら下がっていること。私が旅行で一週間留守にしたとき、帰ったら玄関先に新しいマットが敷かれていて、靴箱の上に「カビ注意」と書かれた付箋が貼ってあったこと。
言葉はほとんどない。でも佐藤さんは、ずっと私の生活の隙間を、静かに埋めていた。
ある晩、いつものようにインターホンが鳴った。
「……電池、じゃないよね」
私が先に言ったら、佐藤さんは少し驚いた顔をして、それから苦笑いした。
「うん。今日は……違う」
雨がひどくて、帰り道でずぶ濡れになったらしい。傘も折れて、シャツもブラウスも体重の分くらい水を吸っている。
「とりあえず上がって。風邪引くよ」
佐藤さんは「いや、汚すから」と遠慮したけど、私はもうドアを大きく開けていた。
タオルを何枚か渡して、洗濯機を回しながら、私はようやく言えた。
「ねえ、佐藤さん」
「……ん?」
「私、ずっと待ってたんだけど」
佐藤さんはタオルで髪を拭く手を止めた。
「待ってたって……何を?」「『電池切れた』以外の理由で、私のインターホンを押してくれるのを」
静かだった。雨の音だけが、部屋の中に満ちていた。
佐藤さんはゆっくりタオルを下ろして、濡れた前髪の隙間から私を見た。
「……今まで、押す理由が思いつかなかったんだ」
「うそ。いっぱいあったでしょ」
「……バレてたか」
小さく笑って、それから佐藤さんは言った。
「じゃあ、これからはずっと理由ありで来る。いい?」
私は頷いて、でもちょっと意地悪したくなって、「でもさ、電池切れたときも来ていいよ」
佐藤さんは一瞬きょとんとして、それから今までで一番大きな声で笑った。
「それは……ズルいな」
雨はまだ止まない。でも、もうインターホンを押す理由を探さなくてもいい。だってこれからは、ただ「帰ってきた」って伝えるだけで、私のドアが開くから。
「佐藤です。悪いんだけど、電池切れたみたいで……」
いつものセリフ。私は玄関を開けて、予備のリモコンを無言で渡す。佐藤さんは「助かる、ほんと毎回ごめん」と小さく頭を下げて、濡れた傘をビニール袋に入れてから自分の部屋に戻っていく。これが私たちの、ほぼ全ての会話だった。
でも私は知っている。佐藤さんが風邪を引いた週は、ゴミ出しの朝だけ私のゴミ箱が空っぽになっていること。私が夜勤明けでフラフラの日は、ドアノブにコンビニの温かいお茶がぶら下がっていること。私が旅行で一週間留守にしたとき、帰ったら玄関先に新しいマットが敷かれていて、靴箱の上に「カビ注意」と書かれた付箋が貼ってあったこと。
言葉はほとんどない。でも佐藤さんは、ずっと私の生活の隙間を、静かに埋めていた。
ある晩、いつものようにインターホンが鳴った。
「……電池、じゃないよね」
私が先に言ったら、佐藤さんは少し驚いた顔をして、それから苦笑いした。
「うん。今日は……違う」
雨がひどくて、帰り道でずぶ濡れになったらしい。傘も折れて、シャツもブラウスも体重の分くらい水を吸っている。
「とりあえず上がって。風邪引くよ」
佐藤さんは「いや、汚すから」と遠慮したけど、私はもうドアを大きく開けていた。
タオルを何枚か渡して、洗濯機を回しながら、私はようやく言えた。
「ねえ、佐藤さん」
「……ん?」
「私、ずっと待ってたんだけど」
佐藤さんはタオルで髪を拭く手を止めた。
「待ってたって……何を?」「『電池切れた』以外の理由で、私のインターホンを押してくれるのを」
静かだった。雨の音だけが、部屋の中に満ちていた。
佐藤さんはゆっくりタオルを下ろして、濡れた前髪の隙間から私を見た。
「……今まで、押す理由が思いつかなかったんだ」
「うそ。いっぱいあったでしょ」
「……バレてたか」
小さく笑って、それから佐藤さんは言った。
「じゃあ、これからはずっと理由ありで来る。いい?」
私は頷いて、でもちょっと意地悪したくなって、「でもさ、電池切れたときも来ていいよ」
佐藤さんは一瞬きょとんとして、それから今までで一番大きな声で笑った。
「それは……ズルいな」
雨はまだ止まない。でも、もうインターホンを押す理由を探さなくてもいい。だってこれからは、ただ「帰ってきた」って伝えるだけで、私のドアが開くから。