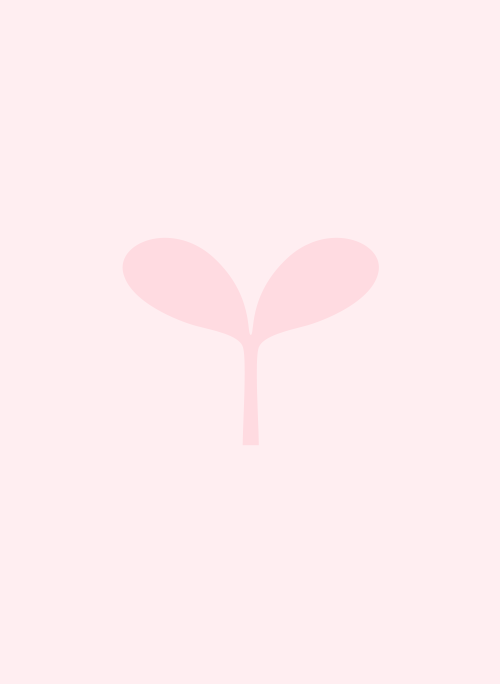小次郎は猫のくせにネクタイを欠かしたことがない。
ピンと伸びた髭を自慢げに撫でながらわたしを見上げる。
「昔は加奈子と違って手紙を配るのに自転車なんて使いやしなかった。この足で一日中、歩いたもんさ」
郵便配達夫を辞めて、もう何年にもなるというのに、小次郎は昨日のことのように現役だった頃のことを話す。
わたしは相づちを打ちながら、でも本当はうわの空で、お昼のお弁当に箸をのばす。
川を渡ってくる風が気持ちいい。
見上げると、しなやかな栴檀の木が揺れて、木漏れ日があふれた。
晴れた日の川面は穏やかで美しい。
河口が近いこともあって、流れはゆったりで陽光が川面に反射してキラキラまぶしい。
前任者からの引き継ぎが終わると、ここでお弁当を食べるようになった。
そして、いつからだったか、隣には小次郎がいた。
「じゃ、そろそろ行くね」
わたしは手紙の入った鞄を肩からさげると自転車にまたがった。
いつになく早い出発に小次郎は怪訝そうな顔をしたが、わたしはかまわずペダルを強く踏み込んだ。