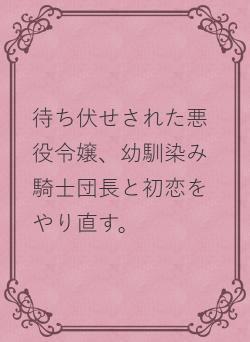私の愛する人を初めて見た時を、今でも鮮やかに覚えている。
とある午後に何気なく窓を覗き込んだ私は、帰りの馬車へ向かう背の高い男性の後ろ姿を見たのだ。まっすぐに伸びた背筋に優雅な足取り、遠くから見てもその容姿は際立って良かった。
そして、何を思ったのか、馬車に乗る直前、彼は邸の方向を振り返って見た。
三階の窓に居る私が見えた訳でもないだろうに、胸はどきんと高鳴り、握りしめた手のひらにはじわっと汗をかいていた。
さらりとした黒髪が揺れた下には印象的な緑の眼差し、遠目で見ても整った容貌は見てとれたけれど、何故だか憂いのある雰囲気を漂わせていた。
わからない。見蕩れていた私には。彼がどのくらい、名残惜しそうに、こちらを見て居たのか。
五秒のことなのか、それとも、何分かのことなのか。まるで、永遠にも思えてしまったようで。
ああ、あの人……私、すごく好き。ただ、それだけでそう思ったのだ。
馬車はいつのまにか視界からいなくなり、あの男性が誰だか知りたくて、私が階段を駆け下りれば、玄関ホールには彼を見送ったらしい寄宿制の貴族学校から帰省をしていた兄ロバートが居た。