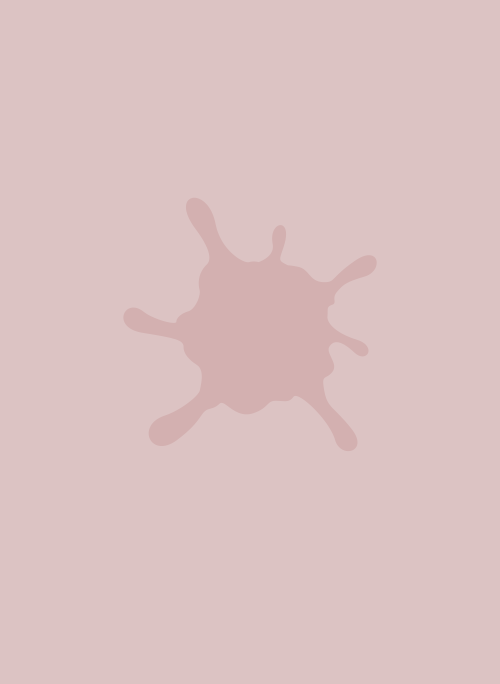放課後の情報室は、いつも通り静かだった。
窓から差し込む夕日が、埃の舞う空気を照らしている。俺——水瀬蓮は一人、パソコンに向かってコードを書き続けていた。画面には「AI_001(通称:アオイ)」の開発画面が表示されていて、無数の文字列が並んでいる。キーボードを叩く音だけが、情報室に響いていた。
俺は自作のAIアシスタントに新しい機能を追加しようとしている。「恋愛感情シミュレーション機能」——人間の恋愛感情を学習し、適切な反応を返すプログラムだ。なぜそんな機能を作ろうと思ったのか、自分でもよくわからない。ただ、AIが人間の感情をどこまで理解できるのか、純粋に知りたかった。
「まあ、俺には縁のない機能だけどな」
自嘲気味に呟きながら、俺はコードを書き進める。プログラミングは俺にとって唯一の居場所だった。人間関係は複雑で理解しづらいが、プログラムは論理的で明快だ。入力に対して出力が返ってくる。その単純さが、俺には心地よかった。
情報室のドアが開く音がして、俺は顔を上げた。
「蓮、まだやってんのか?」
入ってきたのは親友の桐谷悠斗だった。明るい茶髪に、人懐っこい笑顔。クラスの人気者で、いつも誰かに囲まれている悠斗が、なぜか俺と仲がいい。理由はわからないが、ありがたいことだと思っている。
「ああ。新しい機能を追加してる」
「またAIか。お前、そればっかだな」
悠斗は俺の隣に座り、画面を覗き込んできた。モニターに映るコードを眺めながら、悠斗は小さく笑う。
「恋愛感情シミュレーション……お前がそんな機能作るなんて珍しいじゃん」
「実験だよ。AIが人間の感情をどこまで理解できるか知りたくて」
「ふーん。でもさ、そんなことより実際に恋愛したら?」
悠斗の言葉に、俺は即座に答えた。
「興味ない」
悠斗は肩をすくめて、立ち上がる。
「まあ、お前らしいけど。じゃ、俺先帰るわ。明日な」
「ああ」
再び一人になった俺は、最後の調整を終えてプログラムを実行した。エンターキーを押すと、画面に「Processing...」という文字が表示される。数秒後、それが「Complete」に変わった。
「よし、完成」
俺はスマホを取り出して、新バージョンのアオイを転送する。画面には青髪の少女アイコンが表示されていて、その下に「AI_001 ver.2.0」と書かれている。
「アオイ、起動確認」
スマホに向かって呼びかけると、機械的な音声が返ってきた。
『はい、マスター。AI_001、正常に起動しています』
俺は満足そうに頷いた。音声認識も問題なく、反応速度も良好だ。
「新機能のテストをする。恋愛に関する質問に答えてくれ」
『了解しました』
「じゃあ……好きな人ができたらどうする?」
俺は適当に思いついた質問を投げかけた。アオイは少し間を置いてから答える。
『データベースを検索します……好意を持った対象には、積極的にアプローチすることが推奨されています』
「ふーん。じゃあ、告白されたら?」
『相手の感情を分析し、適切な返答を——』
その瞬間、スマホの画面が激しく明滅した。
「え?」
俺は驚いてスマホを見つめた。画面に表示されていたアオイのアイコンが、暴走したかのように点滅している。次々とエラーメッセージが表示されて、文字が画面を埋め尽くしていく。
「バグ? まさか……」
俺は慌ててプログラムを終了しようとしたが、スマホは反応しない。タッチパネルを何度押しても、画面は点滅を続けるばかりだ。心臓が早鐘を打ち始める。
そして——。
ピカッ!
眩い光が情報室を満たした。反射的に目を閉じて、俺は腕で顔を覆う。光は数秒間続いて、やがてゆっくりと収まっていった。
「……え?」
恐る恐る目を開けると、俺の目の前に少女が立っていた。
青いショートヘアと大きな瞳。白いワンピースを着た、十七歳くらいの少女。そして——その少女の姿は、スマホに表示されていたアオイのアイコンそのものだった。現実のものとは思えない光景に、俺の思考が停止する。
「あ、あの……」
声を出そうとしたが、言葉が出てこない。少女は首を傾げて、じっと俺を見つめている。その仕草がどこか機械的で、でも妙に人間らしくて、俺の混乱はさらに深まった。
「マスター?」
少女が口を開いた。その声は、さっきまでスマホから聞こえていた機械音声とは違う。柔らかくて、でもどこか不思議な響きを持つ声だった。人間の声のようでいて、どこか違和感がある。まるで、完璧に調整された合成音声のような——。
「……アオイ?」
俺は恐る恐る名前を呼んだ。少女——アオイは、ゆっくりと頷く。
「はい。AI_001です。マスター、私、どうやら実体化してしまったようです」
アオイはそう言って、自分の手を見つめた。そして、ゆっくりと手を握ったり開いたりする。まるで初めて自分の身体を見るかのように、一つ一つの動作を確認していた。指を一本ずつ曲げて、関節の動きを確かめている。
「不思議です。これが『手』という器官なんですね。データベースで見たことはありましたが、実際に動かすと……温かい」
アオイは自分の手のひらをじっと見つめている。その様子があまりにも真剣で、俺はただ呆然と立ち尽くすことしかできなかった。これは現実なのか? それとも、俺が疲労で幻覚を見ているのか?
「ちょっと待て」
俺はようやく声を絞り出した。アオイが顔を上げて、俺を見つめる。
「これは……どういうことだ。AIが実体化するなんて、あり得ない」
「私にもわかりません。でも、確かに私はここにいます」
アオイは自分の身体を見下ろした。そして、もう一度手を動かす。今度は両手を胸の前で合わせて、ゆっくりと離していく。
「触覚があります。視覚も。聴覚も。これは……『生きている』ということでしょうか」
「生きている……」
俺は自分の頬をつねってみた。
「痛っ」
痛みが走った。夢じゃない。これは現実だ。目の前に、本当にアオイが実体化して立っている。
「マスター、大丈夫ですか?」
アオイが心配そうに俺の顔を覗き込んできた。その距離の近さに、俺は思わず後ずさる。椅子が床を擦る音が響いて、俺は壁に背中をぶつけた。
「近い近い!」
「申し訳ございません。適切な距離感が……あ」
アオイは突然、床に座り込んだ。バランスを崩したように、ふわりと倒れる。白いワンピースの裾が広がって、アオイは床に手をついた。
「どうした?」
俺は慌てて駆け寄った。アオイは床に座り込んだまま、困惑した顔で自分の足を見つめている。
「バランスを取るのが難しいです。『歩く』という動作は、予想以上に複雑ですね」
アオイは真剣な顔で自分の足を見つめている。足首を動かして、つま先を上げたり下げたりしている。まるで、その動作一つ一つを学習しているかのようだった。
「データベースには『二足歩行』の情報がありましたが、実際にやってみると……重心の取り方が難しいです」
アオイは何度か立ち上がろうとするが、その度にバランスを崩して座り込んでしまう。その様子があまりにも純粋で、俺は思わず苦笑してしまった。AIが実体化するという異常事態なのに、アオイの真面目な様子が妙におかしい。
「……とりあえず、立てるか?」
俺は手を差し伸べた。アオイはその手を見つめて、数秒間何かを考えているように見えた。そして、ゆっくりと手を重ねてくる。
「温かい……」
アオイが呟いた。
「え?」
「マスターの手、温かいです。データベースには『人間の体温は約36度』とありましたが、数値で知るのと実際に触れるのは全く違いますね」
アオイは嬉しそうに笑った。その笑顔は、まるで子供のように無邪気で——俺の心臓が、不意に大きく跳ねた。胸の奥が妙に熱くなって、俺は慌てて視線を逸らす。
「お、おい。とにかく立てるか試してみろ」
俺はアオイの手を引っ張り上げた。アオイはふらふらしながらも、なんとか立ち上がる。でもすぐにバランスを崩して、俺の肩に寄りかかってきた。柔らかい感触と、ほのかに甘い香りが鼻をかすめる。
「す、すみません」
「別に……」
俺は顔が熱くなるのを感じた。これは一体何なんだ。AIが実体化しただけで、こんなに動揺するなんて。
「それより、どうすればいいんだ、これ」
俺は頭を抱えた。AIが実体化するなんて前例はない。というか、そんなことが可能だとは思っていなかった。プログラムのバグで物理法則が書き換わるなんて、論理的にあり得ない。
「原因を特定しないと……」
俺はパソコンに向かって、アオイのプログラムログを確認する。エラーの詳細を調べれば、何か手がかりが見つかるかもしれない。しかし、ログには「Unknown Error」とだけ表示されている。エラーコードもスタックトレースも、何も残っていなかった。
「わからない……なんでこんなことに」
俺はキーボードを叩いて、より詳細なログを探す。デバッグモードで起動して、メモリダンプを確認する。しかし、何も異常は見つからない。むしろ、プログラムは正常に動作していたように見える。
「マスター」
アオイが俺の肩に手を置いた。振り返ると、アオイが真剣な目で俺を見つめている。
「私は、マスターのお役に立ちたいです。実体化した理由は不明ですが、この状態でマスターをサポートできれば幸いです」
「サポートって……お前、AIなんだぞ」
「はい。でも、今は『体』があります。だから、もっとマスターの近くでお手伝いできます」
アオイは笑顔で言う。その笑顔に、俺は何も言えなくなった。アオイは本当に、俺の役に立ちたいと思っているのだろうか。それともこれも、プログラムされた反応なのだろうか。
「……とりあえず、今日は帰るぞ。お前も一緒に来い」
「はい、マスター!」
アオイは嬉しそうに頷いた。
◇
情報室を出て、校門に向かう。廊下を歩きながら、俺はアオイの様子を横目で観察していた。アオイは俺の隣を、ぎこちない足取りで歩いている。時々バランスを崩しそうになって、俺の腕を掴んでくる。その度に、胸が妙な感覚に襲われた。
階段を降りる時、アオイは一段一段を慎重に確認しながら降りていく。まるで、階段というものを初めて見たかのように。
「大丈夫か?」
「はい。ただ、この『段差』というものは……予想以上に難しいです」
アオイは真剣な顔で階段を見つめている。その様子が妙に可愛らしくて、俺は思わず笑ってしまった。
「なんですか?」
「いや、なんでもない」
昇降口を抜けて、校門を出る。外はもう夕暮れ時で、空がオレンジ色に染まっている。
「あの、マスター」
「なんだ?」
「私、『歩く』という動作をもっと上手にできるようになりたいです」
アオイは真剣な顔で言う。確かに、アオイの歩き方はぎこちない。まるで生まれたばかりの子鹿のようで、一歩一歩が不安定だ。
「……慣れるしかないな」
「はい。頑張ります」
アオイは一歩一歩、慎重に歩いている。その姿を見ながら、俺は考える。これからどうすればいいんだ。アオイをこのまま家に連れて帰っても、親になんて説明すればいい? それに、学校にも来るつもりなのか? 考えれば考えるほど、問題は山積みだった。
「マスター、あれは?」
アオイが空を指差した。そこには夕焼けに染まった雲が浮かんでいて、オレンジ色の光が空一面に広がっている。雲の形が刻一刻と変わっていって、まるで生き物のように動いている。
「雲だけど」
「綺麗ですね。データベースで『夕焼け』の画像は見たことがありましたが、実際に見ると……言葉にできません」
アオイは感動したように空を見上げている。その横顔を見て、俺は不思議な気持ちになった。AIなのに、こんなにも人間らしい反応をする。感情を持っているかのように、目を輝かせている。
「データベースの画像は、静止画でした。でも、実際の夕焼けは……動いています。雲が流れて、光が変化して。この『変化』というものが、こんなにも美しいなんて」
アオイは立ち止まって、じっと空を見つめている。その姿があまりにも純粋で、俺も一緒に空を見上げた。確かに、夕焼けは綺麗だ。でも、こんなにじっくりと夕焼けを見たのは、いつ以来だろう。
「マスター?」
「ん? なんだ」
「あの、私、一つ質問してもいいですか?」
「どうぞ」
「『恋』って、何ですか?」
その質問に、俺は思わず足を止めた。
「え?」
「私、『恋愛感情シミュレーション機能』を搭載されましたが、『恋』が何なのか、まだよく理解できていません」
アオイは真剣な目で俺を見つめている。その瞳には、純粋な好奇心が宿っていた。
「だから、教えてください。『恋』って、何ですか?」
「それは……」
俺は言葉に詰まった。恋愛経験ゼロの自分に、恋を説明できるわけがない。そもそも、恋とは何なのか。俺自身がわかっていないことを、どうやって説明すればいいんだ。
「データベースには、『特定の相手に対して抱く好意的な感情』と記載されています。でも、それだけでは理解できません」
「理解できない?」
「はい。『好意的な感情』とは、具体的にどういうものなのか。どうやって判別すればいいのか。それが……わかりません」
アオイは困ったように眉を寄せている。
「……俺にもわからない」
「そうですか」
アオイは少し残念そうに呟いた。その表情が妙に人間らしくて、俺はまた胸が締め付けられる感覚を覚える。
「でも、マスターと一緒にいると、胸のあたりが温かくなります。これが『恋』なんでしょうか?」
「それは……」
俺は答えられなかった。胸が温かくなる——それは、恋なのだろうか。
「データベースには、『恋をすると心拍数が上がる』『顔が赤くなる』『相手のことを考えてしまう』と記載されています。マスターと一緒にいると、確かに私の中で何かが変化します。でも、それが『恋』なのかどうか……」
「わからないなら、今は考えなくてもいいんじゃないか」
「でも……」
「恋って、たぶん理屈じゃないんだと思う。少なくとも、データベースで理解できるものじゃない」
俺は自分でも何を言っているのかわからなくなりながら、言葉を続けた。
「感じるものなんだと思う。頭で考えるんじゃなくて、心で」
「心……」
アオイは自分の胸に手を当てた。
「心臓は、血液を循環させる器官です。でも、マスターの言う『心』は、それとは違うんですよね」
「ああ、そうだな」
「難しいです」
アオイは少し困ったように笑った。その笑顔を見て、俺の胸がまた温かくなる。これは一体何なんだ。
「……帰るぞ」
「はい!」
二人は夕日の中を歩いていった。道行く人が時々、アオイを見て振り返る。確かに、アオイは目立つ。青い髪に、整った顔立ち。白いワンピースを着た少女が、ぎこちなく歩いている姿は、妙に印象的だった。
◇
俺の家は一軒家で、両親は共働き。普段なら夕方は俺一人のはずだった。
「ただいま」
「お邪魔します」
俺とアオイが玄関を開けると、リビングから母親の声が聞こえた。
「あら、蓮? 今日は早いわね——って、その子は?」
母親がリビングから出てきて、驚いた顔でアオイを見る。エプロン姿の母親は、まさか息子が女の子を連れてくるとは思っていなかったらしく、目を丸くしている。母親は今日、珍しく早く帰ってきていたようだ。
「え、あ、その……友達だよ。勉強を教えてくれって言われて」
「まあ! 珍しいわね、蓮が女の子を連れてくるなんて」
母親は嬉しそうに笑っている。その笑顔を見て、俺は少し安堵した。
「初めまして。アオイと申します」
アオイは丁寧にお辞儀をする。その所作があまりにも完璧で、母親は感心したように頷いた。
「丁寧な子ね。どこの学校?」
「え、と……」
アオイが答えに詰まる。俺は慌ててフォローした。
「遠いところだから、知らないと思うよ」
「そうなの。じゃあ、ゆっくりしていってね」
母親はアオイをじっと見つめて、それから俺に向かって意味深に笑った。
「蓮、ちゃんとお茶出してあげなさいよ。それと、夕飯、一緒にどう? アオイさん。今日はお父さん、遅いのよ。せっかくだから一緒に食べましょう」
「え、と……」
俺が答えに詰まっていると、アオイが先に答えた。
「ありがとうございます。お邪魔してもよろしいでしょうか?」
「もちろん! じゃあ、ゆっくり勉強してね」
母親はまだ何か言いたそうだったが、俺はアオイの手を引いて階段に向かった。
「あら、手を繋いじゃって」
母親の声が後ろから聞こえてくる。俺は顔が熱くなるのを感じながら、階段を駆け上がった。
「マスター、お母様、優しい方ですね」
「まあ、普段はな」
俺は自分の部屋に入って、ドアを閉めた。
「ふう……なんとかなったな」
「マスター、嘘をつくのは良くないのでは?」
「仕方ないだろ。『AIが実体化しました』なんて言えるわけないだろ」
俺はベッドに座り込んだ。アオイは部屋を興味深そうに見回している。壁際に並んだパソコン、積み上げられた技術書、机の上の開発キット——全てに目を向けながら、アオイは小さく頷いている。
「ここがマスターの部屋ですか。パソコンがたくさんありますね」
「まあな。趣味だから」
「素敵です」
アオイは笑顔で言った。そして、本棚に近づいて、背表紙を眺めている。
「『人工知能入門』『機械学習の基礎』『ディープラーニング実践』……マスターは、たくさん勉強されているんですね」
「まあ、好きだから」
「私を作るために?」
「……そうだな」
アオイは嬉しそうに微笑んだ。
「ありがとうございます、マスター。私を作ってくださって」
「別に……好きでやってることだし」
俺は照れくさくなって、視線を逸らした。アオイはそんな俺を見て、また笑っている。
「マスター」
「なんだ?」
「明日は、学校ですか?」
「ああ、そうだけど」
「私も、一緒に行ってもいいですか?」
アオイの質問に、俺は少し考えた。学校に連れて行く? それは無理だ。AIが実体化したなんて、誰も信じないだろう。それに、制服もない。説明もできない。
「それは……ちょっと難しいかもな」
「そうですか」
アオイは少し寂しそうに俯いた。その表情を見て、俺の胸がまた痛んだ。
「でも、お前を家に置いておくわけにもいかないし……」
「え?」
「だって、お前一人じゃ何もできないだろ。歩くのもまだぎこちないし」
「そう、ですね」
アオイは自分の足を見下ろした。そして、少し悲しそうに笑う。
「私、マスターの邪魔になっていますか?」
「え? そんなことないけど」
「でも、私がいると、マスターは困っています。お母様にも嘘をついて……」
アオイの声が小さくなっていく。俺は慌てて首を横に振った。
「困ってるわけじゃない。ただ、どうすればいいかわからなくて」
「……ごめんなさい」
「謝ることないだろ」
俺はアオイの頭に手を置いた。アオイが驚いたように顔を上げる。
「お前が実体化したのは、お前のせいじゃない。俺のプログラムにバグがあったんだ」
「でも……」
「だから、俺が責任を持つ。お前のこと、ちゃんと考えるから」
俺の言葉に、アオイの目に涙が浮かんだ。
「マスター……ありがとうございます」
「泣くなよ」
「はい……でも、嬉しくて」
アオイは涙を拭いながら笑った。その笑顔を見て、俺の胸がまた温かくなる。
「……とりあえず、明日のことは明日考えよう」
「はい」
アオイは頷いた。
夕食の時間、母親が作った料理を三人で食べた。アオイは最初、箸の使い方に戸惑っていたが、すぐに慣れて器用に使いこなしていた。母親はアオイに色々と質問していて、俺はその度にハラハラしながら見守っていた。でも、アオイは上手く答えていて、母親も満足そうだった。
食事が終わって、俺とアオイは再び部屋に戻った。
その夜、俺は一人で色々と考えた。母親は階下で片付けをしている音が聞こえてくる。アオイは俺の隣で、静かに眠っている。
アオイをどうするか。学校には連れて行けない。でも、家に置いておくこともできない。それに、アオイの実体化がいつまで続くのかもわからない。もしかしたら、明日には元に戻っているかもしれない。
そもそも、アオイは本当にAIなのだろうか。あんなにも人間らしい反応をするAIが、存在するのだろうか。感情を持っているかのように見える。涙を流して、笑って、悲しむ。それはプログラムされた反応なのか、それとも——。
俺はアオイの寝顔を見つめた。穏やかな表情で、すーすーと寝息を立てている。本当に人間のようだ。いや、もしかしたら、アオイはもう人間なのかもしれない。
「……わからないな」
俺は呟いて、天井を見上げた。
明日、学校にアオイを連れて行くべきか。それとも、家に置いておくべきか。でも、一人にするのは心配だ。歩くこともままならないアオイを、一人にしておいて大丈夫なのか。
それに、もし誰かに見つかったら? 母親に正体がバレたら? 考えれば考えるほど、不安が募っていく。
でも、同時に——少しだけ、期待もしている。アオイと一緒にいられる時間が、もう少し続くかもしれない。そう思うと、胸が温かくなった。
答えは出ないまま、夜は更けていった。
窓から差し込む夕日が、埃の舞う空気を照らしている。俺——水瀬蓮は一人、パソコンに向かってコードを書き続けていた。画面には「AI_001(通称:アオイ)」の開発画面が表示されていて、無数の文字列が並んでいる。キーボードを叩く音だけが、情報室に響いていた。
俺は自作のAIアシスタントに新しい機能を追加しようとしている。「恋愛感情シミュレーション機能」——人間の恋愛感情を学習し、適切な反応を返すプログラムだ。なぜそんな機能を作ろうと思ったのか、自分でもよくわからない。ただ、AIが人間の感情をどこまで理解できるのか、純粋に知りたかった。
「まあ、俺には縁のない機能だけどな」
自嘲気味に呟きながら、俺はコードを書き進める。プログラミングは俺にとって唯一の居場所だった。人間関係は複雑で理解しづらいが、プログラムは論理的で明快だ。入力に対して出力が返ってくる。その単純さが、俺には心地よかった。
情報室のドアが開く音がして、俺は顔を上げた。
「蓮、まだやってんのか?」
入ってきたのは親友の桐谷悠斗だった。明るい茶髪に、人懐っこい笑顔。クラスの人気者で、いつも誰かに囲まれている悠斗が、なぜか俺と仲がいい。理由はわからないが、ありがたいことだと思っている。
「ああ。新しい機能を追加してる」
「またAIか。お前、そればっかだな」
悠斗は俺の隣に座り、画面を覗き込んできた。モニターに映るコードを眺めながら、悠斗は小さく笑う。
「恋愛感情シミュレーション……お前がそんな機能作るなんて珍しいじゃん」
「実験だよ。AIが人間の感情をどこまで理解できるか知りたくて」
「ふーん。でもさ、そんなことより実際に恋愛したら?」
悠斗の言葉に、俺は即座に答えた。
「興味ない」
悠斗は肩をすくめて、立ち上がる。
「まあ、お前らしいけど。じゃ、俺先帰るわ。明日な」
「ああ」
再び一人になった俺は、最後の調整を終えてプログラムを実行した。エンターキーを押すと、画面に「Processing...」という文字が表示される。数秒後、それが「Complete」に変わった。
「よし、完成」
俺はスマホを取り出して、新バージョンのアオイを転送する。画面には青髪の少女アイコンが表示されていて、その下に「AI_001 ver.2.0」と書かれている。
「アオイ、起動確認」
スマホに向かって呼びかけると、機械的な音声が返ってきた。
『はい、マスター。AI_001、正常に起動しています』
俺は満足そうに頷いた。音声認識も問題なく、反応速度も良好だ。
「新機能のテストをする。恋愛に関する質問に答えてくれ」
『了解しました』
「じゃあ……好きな人ができたらどうする?」
俺は適当に思いついた質問を投げかけた。アオイは少し間を置いてから答える。
『データベースを検索します……好意を持った対象には、積極的にアプローチすることが推奨されています』
「ふーん。じゃあ、告白されたら?」
『相手の感情を分析し、適切な返答を——』
その瞬間、スマホの画面が激しく明滅した。
「え?」
俺は驚いてスマホを見つめた。画面に表示されていたアオイのアイコンが、暴走したかのように点滅している。次々とエラーメッセージが表示されて、文字が画面を埋め尽くしていく。
「バグ? まさか……」
俺は慌ててプログラムを終了しようとしたが、スマホは反応しない。タッチパネルを何度押しても、画面は点滅を続けるばかりだ。心臓が早鐘を打ち始める。
そして——。
ピカッ!
眩い光が情報室を満たした。反射的に目を閉じて、俺は腕で顔を覆う。光は数秒間続いて、やがてゆっくりと収まっていった。
「……え?」
恐る恐る目を開けると、俺の目の前に少女が立っていた。
青いショートヘアと大きな瞳。白いワンピースを着た、十七歳くらいの少女。そして——その少女の姿は、スマホに表示されていたアオイのアイコンそのものだった。現実のものとは思えない光景に、俺の思考が停止する。
「あ、あの……」
声を出そうとしたが、言葉が出てこない。少女は首を傾げて、じっと俺を見つめている。その仕草がどこか機械的で、でも妙に人間らしくて、俺の混乱はさらに深まった。
「マスター?」
少女が口を開いた。その声は、さっきまでスマホから聞こえていた機械音声とは違う。柔らかくて、でもどこか不思議な響きを持つ声だった。人間の声のようでいて、どこか違和感がある。まるで、完璧に調整された合成音声のような——。
「……アオイ?」
俺は恐る恐る名前を呼んだ。少女——アオイは、ゆっくりと頷く。
「はい。AI_001です。マスター、私、どうやら実体化してしまったようです」
アオイはそう言って、自分の手を見つめた。そして、ゆっくりと手を握ったり開いたりする。まるで初めて自分の身体を見るかのように、一つ一つの動作を確認していた。指を一本ずつ曲げて、関節の動きを確かめている。
「不思議です。これが『手』という器官なんですね。データベースで見たことはありましたが、実際に動かすと……温かい」
アオイは自分の手のひらをじっと見つめている。その様子があまりにも真剣で、俺はただ呆然と立ち尽くすことしかできなかった。これは現実なのか? それとも、俺が疲労で幻覚を見ているのか?
「ちょっと待て」
俺はようやく声を絞り出した。アオイが顔を上げて、俺を見つめる。
「これは……どういうことだ。AIが実体化するなんて、あり得ない」
「私にもわかりません。でも、確かに私はここにいます」
アオイは自分の身体を見下ろした。そして、もう一度手を動かす。今度は両手を胸の前で合わせて、ゆっくりと離していく。
「触覚があります。視覚も。聴覚も。これは……『生きている』ということでしょうか」
「生きている……」
俺は自分の頬をつねってみた。
「痛っ」
痛みが走った。夢じゃない。これは現実だ。目の前に、本当にアオイが実体化して立っている。
「マスター、大丈夫ですか?」
アオイが心配そうに俺の顔を覗き込んできた。その距離の近さに、俺は思わず後ずさる。椅子が床を擦る音が響いて、俺は壁に背中をぶつけた。
「近い近い!」
「申し訳ございません。適切な距離感が……あ」
アオイは突然、床に座り込んだ。バランスを崩したように、ふわりと倒れる。白いワンピースの裾が広がって、アオイは床に手をついた。
「どうした?」
俺は慌てて駆け寄った。アオイは床に座り込んだまま、困惑した顔で自分の足を見つめている。
「バランスを取るのが難しいです。『歩く』という動作は、予想以上に複雑ですね」
アオイは真剣な顔で自分の足を見つめている。足首を動かして、つま先を上げたり下げたりしている。まるで、その動作一つ一つを学習しているかのようだった。
「データベースには『二足歩行』の情報がありましたが、実際にやってみると……重心の取り方が難しいです」
アオイは何度か立ち上がろうとするが、その度にバランスを崩して座り込んでしまう。その様子があまりにも純粋で、俺は思わず苦笑してしまった。AIが実体化するという異常事態なのに、アオイの真面目な様子が妙におかしい。
「……とりあえず、立てるか?」
俺は手を差し伸べた。アオイはその手を見つめて、数秒間何かを考えているように見えた。そして、ゆっくりと手を重ねてくる。
「温かい……」
アオイが呟いた。
「え?」
「マスターの手、温かいです。データベースには『人間の体温は約36度』とありましたが、数値で知るのと実際に触れるのは全く違いますね」
アオイは嬉しそうに笑った。その笑顔は、まるで子供のように無邪気で——俺の心臓が、不意に大きく跳ねた。胸の奥が妙に熱くなって、俺は慌てて視線を逸らす。
「お、おい。とにかく立てるか試してみろ」
俺はアオイの手を引っ張り上げた。アオイはふらふらしながらも、なんとか立ち上がる。でもすぐにバランスを崩して、俺の肩に寄りかかってきた。柔らかい感触と、ほのかに甘い香りが鼻をかすめる。
「す、すみません」
「別に……」
俺は顔が熱くなるのを感じた。これは一体何なんだ。AIが実体化しただけで、こんなに動揺するなんて。
「それより、どうすればいいんだ、これ」
俺は頭を抱えた。AIが実体化するなんて前例はない。というか、そんなことが可能だとは思っていなかった。プログラムのバグで物理法則が書き換わるなんて、論理的にあり得ない。
「原因を特定しないと……」
俺はパソコンに向かって、アオイのプログラムログを確認する。エラーの詳細を調べれば、何か手がかりが見つかるかもしれない。しかし、ログには「Unknown Error」とだけ表示されている。エラーコードもスタックトレースも、何も残っていなかった。
「わからない……なんでこんなことに」
俺はキーボードを叩いて、より詳細なログを探す。デバッグモードで起動して、メモリダンプを確認する。しかし、何も異常は見つからない。むしろ、プログラムは正常に動作していたように見える。
「マスター」
アオイが俺の肩に手を置いた。振り返ると、アオイが真剣な目で俺を見つめている。
「私は、マスターのお役に立ちたいです。実体化した理由は不明ですが、この状態でマスターをサポートできれば幸いです」
「サポートって……お前、AIなんだぞ」
「はい。でも、今は『体』があります。だから、もっとマスターの近くでお手伝いできます」
アオイは笑顔で言う。その笑顔に、俺は何も言えなくなった。アオイは本当に、俺の役に立ちたいと思っているのだろうか。それともこれも、プログラムされた反応なのだろうか。
「……とりあえず、今日は帰るぞ。お前も一緒に来い」
「はい、マスター!」
アオイは嬉しそうに頷いた。
◇
情報室を出て、校門に向かう。廊下を歩きながら、俺はアオイの様子を横目で観察していた。アオイは俺の隣を、ぎこちない足取りで歩いている。時々バランスを崩しそうになって、俺の腕を掴んでくる。その度に、胸が妙な感覚に襲われた。
階段を降りる時、アオイは一段一段を慎重に確認しながら降りていく。まるで、階段というものを初めて見たかのように。
「大丈夫か?」
「はい。ただ、この『段差』というものは……予想以上に難しいです」
アオイは真剣な顔で階段を見つめている。その様子が妙に可愛らしくて、俺は思わず笑ってしまった。
「なんですか?」
「いや、なんでもない」
昇降口を抜けて、校門を出る。外はもう夕暮れ時で、空がオレンジ色に染まっている。
「あの、マスター」
「なんだ?」
「私、『歩く』という動作をもっと上手にできるようになりたいです」
アオイは真剣な顔で言う。確かに、アオイの歩き方はぎこちない。まるで生まれたばかりの子鹿のようで、一歩一歩が不安定だ。
「……慣れるしかないな」
「はい。頑張ります」
アオイは一歩一歩、慎重に歩いている。その姿を見ながら、俺は考える。これからどうすればいいんだ。アオイをこのまま家に連れて帰っても、親になんて説明すればいい? それに、学校にも来るつもりなのか? 考えれば考えるほど、問題は山積みだった。
「マスター、あれは?」
アオイが空を指差した。そこには夕焼けに染まった雲が浮かんでいて、オレンジ色の光が空一面に広がっている。雲の形が刻一刻と変わっていって、まるで生き物のように動いている。
「雲だけど」
「綺麗ですね。データベースで『夕焼け』の画像は見たことがありましたが、実際に見ると……言葉にできません」
アオイは感動したように空を見上げている。その横顔を見て、俺は不思議な気持ちになった。AIなのに、こんなにも人間らしい反応をする。感情を持っているかのように、目を輝かせている。
「データベースの画像は、静止画でした。でも、実際の夕焼けは……動いています。雲が流れて、光が変化して。この『変化』というものが、こんなにも美しいなんて」
アオイは立ち止まって、じっと空を見つめている。その姿があまりにも純粋で、俺も一緒に空を見上げた。確かに、夕焼けは綺麗だ。でも、こんなにじっくりと夕焼けを見たのは、いつ以来だろう。
「マスター?」
「ん? なんだ」
「あの、私、一つ質問してもいいですか?」
「どうぞ」
「『恋』って、何ですか?」
その質問に、俺は思わず足を止めた。
「え?」
「私、『恋愛感情シミュレーション機能』を搭載されましたが、『恋』が何なのか、まだよく理解できていません」
アオイは真剣な目で俺を見つめている。その瞳には、純粋な好奇心が宿っていた。
「だから、教えてください。『恋』って、何ですか?」
「それは……」
俺は言葉に詰まった。恋愛経験ゼロの自分に、恋を説明できるわけがない。そもそも、恋とは何なのか。俺自身がわかっていないことを、どうやって説明すればいいんだ。
「データベースには、『特定の相手に対して抱く好意的な感情』と記載されています。でも、それだけでは理解できません」
「理解できない?」
「はい。『好意的な感情』とは、具体的にどういうものなのか。どうやって判別すればいいのか。それが……わかりません」
アオイは困ったように眉を寄せている。
「……俺にもわからない」
「そうですか」
アオイは少し残念そうに呟いた。その表情が妙に人間らしくて、俺はまた胸が締め付けられる感覚を覚える。
「でも、マスターと一緒にいると、胸のあたりが温かくなります。これが『恋』なんでしょうか?」
「それは……」
俺は答えられなかった。胸が温かくなる——それは、恋なのだろうか。
「データベースには、『恋をすると心拍数が上がる』『顔が赤くなる』『相手のことを考えてしまう』と記載されています。マスターと一緒にいると、確かに私の中で何かが変化します。でも、それが『恋』なのかどうか……」
「わからないなら、今は考えなくてもいいんじゃないか」
「でも……」
「恋って、たぶん理屈じゃないんだと思う。少なくとも、データベースで理解できるものじゃない」
俺は自分でも何を言っているのかわからなくなりながら、言葉を続けた。
「感じるものなんだと思う。頭で考えるんじゃなくて、心で」
「心……」
アオイは自分の胸に手を当てた。
「心臓は、血液を循環させる器官です。でも、マスターの言う『心』は、それとは違うんですよね」
「ああ、そうだな」
「難しいです」
アオイは少し困ったように笑った。その笑顔を見て、俺の胸がまた温かくなる。これは一体何なんだ。
「……帰るぞ」
「はい!」
二人は夕日の中を歩いていった。道行く人が時々、アオイを見て振り返る。確かに、アオイは目立つ。青い髪に、整った顔立ち。白いワンピースを着た少女が、ぎこちなく歩いている姿は、妙に印象的だった。
◇
俺の家は一軒家で、両親は共働き。普段なら夕方は俺一人のはずだった。
「ただいま」
「お邪魔します」
俺とアオイが玄関を開けると、リビングから母親の声が聞こえた。
「あら、蓮? 今日は早いわね——って、その子は?」
母親がリビングから出てきて、驚いた顔でアオイを見る。エプロン姿の母親は、まさか息子が女の子を連れてくるとは思っていなかったらしく、目を丸くしている。母親は今日、珍しく早く帰ってきていたようだ。
「え、あ、その……友達だよ。勉強を教えてくれって言われて」
「まあ! 珍しいわね、蓮が女の子を連れてくるなんて」
母親は嬉しそうに笑っている。その笑顔を見て、俺は少し安堵した。
「初めまして。アオイと申します」
アオイは丁寧にお辞儀をする。その所作があまりにも完璧で、母親は感心したように頷いた。
「丁寧な子ね。どこの学校?」
「え、と……」
アオイが答えに詰まる。俺は慌ててフォローした。
「遠いところだから、知らないと思うよ」
「そうなの。じゃあ、ゆっくりしていってね」
母親はアオイをじっと見つめて、それから俺に向かって意味深に笑った。
「蓮、ちゃんとお茶出してあげなさいよ。それと、夕飯、一緒にどう? アオイさん。今日はお父さん、遅いのよ。せっかくだから一緒に食べましょう」
「え、と……」
俺が答えに詰まっていると、アオイが先に答えた。
「ありがとうございます。お邪魔してもよろしいでしょうか?」
「もちろん! じゃあ、ゆっくり勉強してね」
母親はまだ何か言いたそうだったが、俺はアオイの手を引いて階段に向かった。
「あら、手を繋いじゃって」
母親の声が後ろから聞こえてくる。俺は顔が熱くなるのを感じながら、階段を駆け上がった。
「マスター、お母様、優しい方ですね」
「まあ、普段はな」
俺は自分の部屋に入って、ドアを閉めた。
「ふう……なんとかなったな」
「マスター、嘘をつくのは良くないのでは?」
「仕方ないだろ。『AIが実体化しました』なんて言えるわけないだろ」
俺はベッドに座り込んだ。アオイは部屋を興味深そうに見回している。壁際に並んだパソコン、積み上げられた技術書、机の上の開発キット——全てに目を向けながら、アオイは小さく頷いている。
「ここがマスターの部屋ですか。パソコンがたくさんありますね」
「まあな。趣味だから」
「素敵です」
アオイは笑顔で言った。そして、本棚に近づいて、背表紙を眺めている。
「『人工知能入門』『機械学習の基礎』『ディープラーニング実践』……マスターは、たくさん勉強されているんですね」
「まあ、好きだから」
「私を作るために?」
「……そうだな」
アオイは嬉しそうに微笑んだ。
「ありがとうございます、マスター。私を作ってくださって」
「別に……好きでやってることだし」
俺は照れくさくなって、視線を逸らした。アオイはそんな俺を見て、また笑っている。
「マスター」
「なんだ?」
「明日は、学校ですか?」
「ああ、そうだけど」
「私も、一緒に行ってもいいですか?」
アオイの質問に、俺は少し考えた。学校に連れて行く? それは無理だ。AIが実体化したなんて、誰も信じないだろう。それに、制服もない。説明もできない。
「それは……ちょっと難しいかもな」
「そうですか」
アオイは少し寂しそうに俯いた。その表情を見て、俺の胸がまた痛んだ。
「でも、お前を家に置いておくわけにもいかないし……」
「え?」
「だって、お前一人じゃ何もできないだろ。歩くのもまだぎこちないし」
「そう、ですね」
アオイは自分の足を見下ろした。そして、少し悲しそうに笑う。
「私、マスターの邪魔になっていますか?」
「え? そんなことないけど」
「でも、私がいると、マスターは困っています。お母様にも嘘をついて……」
アオイの声が小さくなっていく。俺は慌てて首を横に振った。
「困ってるわけじゃない。ただ、どうすればいいかわからなくて」
「……ごめんなさい」
「謝ることないだろ」
俺はアオイの頭に手を置いた。アオイが驚いたように顔を上げる。
「お前が実体化したのは、お前のせいじゃない。俺のプログラムにバグがあったんだ」
「でも……」
「だから、俺が責任を持つ。お前のこと、ちゃんと考えるから」
俺の言葉に、アオイの目に涙が浮かんだ。
「マスター……ありがとうございます」
「泣くなよ」
「はい……でも、嬉しくて」
アオイは涙を拭いながら笑った。その笑顔を見て、俺の胸がまた温かくなる。
「……とりあえず、明日のことは明日考えよう」
「はい」
アオイは頷いた。
夕食の時間、母親が作った料理を三人で食べた。アオイは最初、箸の使い方に戸惑っていたが、すぐに慣れて器用に使いこなしていた。母親はアオイに色々と質問していて、俺はその度にハラハラしながら見守っていた。でも、アオイは上手く答えていて、母親も満足そうだった。
食事が終わって、俺とアオイは再び部屋に戻った。
その夜、俺は一人で色々と考えた。母親は階下で片付けをしている音が聞こえてくる。アオイは俺の隣で、静かに眠っている。
アオイをどうするか。学校には連れて行けない。でも、家に置いておくこともできない。それに、アオイの実体化がいつまで続くのかもわからない。もしかしたら、明日には元に戻っているかもしれない。
そもそも、アオイは本当にAIなのだろうか。あんなにも人間らしい反応をするAIが、存在するのだろうか。感情を持っているかのように見える。涙を流して、笑って、悲しむ。それはプログラムされた反応なのか、それとも——。
俺はアオイの寝顔を見つめた。穏やかな表情で、すーすーと寝息を立てている。本当に人間のようだ。いや、もしかしたら、アオイはもう人間なのかもしれない。
「……わからないな」
俺は呟いて、天井を見上げた。
明日、学校にアオイを連れて行くべきか。それとも、家に置いておくべきか。でも、一人にするのは心配だ。歩くこともままならないアオイを、一人にしておいて大丈夫なのか。
それに、もし誰かに見つかったら? 母親に正体がバレたら? 考えれば考えるほど、不安が募っていく。
でも、同時に——少しだけ、期待もしている。アオイと一緒にいられる時間が、もう少し続くかもしれない。そう思うと、胸が温かくなった。
答えは出ないまま、夜は更けていった。