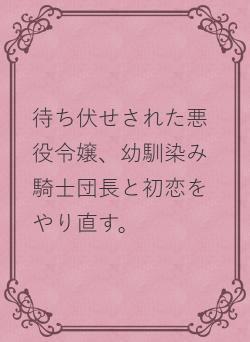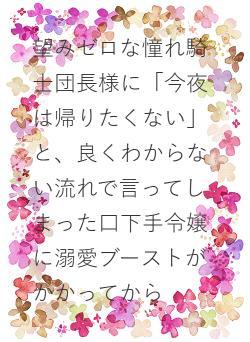状況が掴めずに、暫しぼーっと天井を眺めていたけれど、昨夜あったさまざまな出来事が思い出され、信じられない気持ちで胸がいっぱいだった。
昨夜の出来事が夢ではなかったという証拠に、鞭で叩かれて怪我をしている手には、鎮痛効果のある薬が塗られている様子で痛くない。しっかりと包帯を巻かれていた。
そして、楽な寝巻きに着替えて、特別に用意したはずのあの赤いドレスは着ていない。
これまでにはメイドにも怪我したことを隠していたのだから、これを治療してくれたか指示してくれたのは、アーロンなのだろう。
手早く身支度を調えると、扉を叩く音がして、私はそれに応えた。
「どうぞ。入っても良いわ……」
「奥様。失礼致します。おはようございます」
きっちりと執事服を来た年若い執事、クウェンティンの姿がそこにあった。
「……クウェンティン。昨夜の出来事は……」
私が言わんとしていることのその先を、正確に理解しているクウェンティンは、無表情のままで頷いた。
昨夜の出来事が夢ではなかったという証拠に、鞭で叩かれて怪我をしている手には、鎮痛効果のある薬が塗られている様子で痛くない。しっかりと包帯を巻かれていた。
そして、楽な寝巻きに着替えて、特別に用意したはずのあの赤いドレスは着ていない。
これまでにはメイドにも怪我したことを隠していたのだから、これを治療してくれたか指示してくれたのは、アーロンなのだろう。
手早く身支度を調えると、扉を叩く音がして、私はそれに応えた。
「どうぞ。入っても良いわ……」
「奥様。失礼致します。おはようございます」
きっちりと執事服を来た年若い執事、クウェンティンの姿がそこにあった。
「……クウェンティン。昨夜の出来事は……」
私が言わんとしていることのその先を、正確に理解しているクウェンティンは、無表情のままで頷いた。