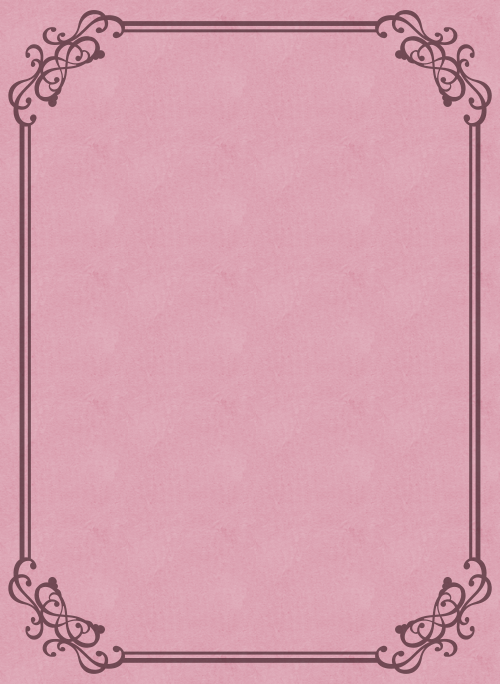1.
「椿くん、ごめんね」
激しい吹雪の影響で高速道路が通行止めになった後、迂回を余儀なくされた車の渋滞にハマりかれこれ三十分以上は過ぎただろうか。いつになったら東京へ帰れるのか、焦りと不安が押し寄せてくる。
「どうして藤堂主任が謝るんですか?」
助手席に座る部下の椿遥人はすぐに「主任のせいじゃありませんよ」と否定してくれる。けれど、大雪の予報が出ているのを知りながら現場にとどまる判断をしたのは私だ。
「でも、小林夫妻の誘いを受けたのは私で、あと一時間でも早く出発していたらこんなことにはならなかったはずだから……」
「いいえ、あれは最良の判断でしたよ」
そう言い切ってくれる彼の言葉にほんの少し救われた気がする。
私が勤務するエドガーデンは純国産にこだわった食材や雑貨を扱うセレクトショップ。経営母体は志木リゾートで主にリゾート開発を手掛けている専門デベロッパー。
私はそこから出向という形で飛ばされて二年が経とうとしている。当初はまるで畑違いの業種にどうなることかと思ったが、全国の美味しいものを探すのも、名品を見つけるのも楽しい。
今日の目的は幻とされる日本酒の買い付け。今朝早くに私は都内でレンタカーを借り、椿くんを助手席に乗せて長野へと向かった。
松川村にある造り酒屋には二度断られているのだけれど、どうしてもこのおいしさを多くの人に知ってもらいたかったから。
*
「そこをなんとかお願いできないでしょうか?」
酒蔵の軒先でなんども頭を下げると大きなため息が降ってくる。
「……うちはね、家族経営だから大量生産できないんだよ。東京のおしゃれな店に並べる商品でもないし。なんども来てもらって答えはおんなじ。悪いんだけどもう帰って」
毎回同じ文句で断られていた。数本単位では物流コストがかかりすぎるので販売店舗を限定するにしても最低五十本は確保したいところ。けれど、地元スーパーや酒屋に卸す分を差し引くと我が社に納品できるのは多くて十五本なのだという。
「それでしたら」
そう口を開いたのは椿くんだった。
「180mlの飲み切りサイズを作るのはいかがでしょう? 小林酒造の美味しい日本酒をよりたくさんの人に楽しんでいただきたい。僕のルーツでもある信州の、日本の良さを若い人たちにも伝えていきたいんです。そのためにもお力をお貸しいただけないでしょうか?」
彼の提案は小林社長の心を動かしたようで、なんと180mlの小瓶の日本酒を製造してもらえることになったのだ。瓶のデザインもこちらに任せてもらえるという。それだけでなく、夕飯を食べていかないかと誘われて、断り切れずに奥さんの手作り料理をいただくことになった。今後の仕事の話に花が咲き、お宅を出る頃にはすっかり日も暮れて大粒の雪が降り始めていた。
*
車は少しずつ流れてきていた。しかしこのまま下道で帰るとなると到着は夜中になるだろう。山道を抜ければもう少し時短になるけれど、この雪では危険が伴う。
「ねえ、椿くん。もし嫌ならはっきりいってもらって構わないんだけど……」
私は恐る恐るといった感じで話を切り出す。
「はい、なんでしょう」
「東京へ帰るの、明日でもよかったりする? この天候だと大切な部下を安全に送り届ける自信がなくて」
言葉選びは慎重にしなければいけない。部下を誘ったなんて言われてしまわないように。
「もちろんいいですよ。俺が免許証忘れたせいで、こんな吹雪の中、藤堂主任に運転させ続けるのは申し訳ないなって思っていたんです。このあたりでホテル探しましょう」
話の早い部下でよかった。椿くんならば面倒なことは言わないだろうと分かってはいたのだけれど、このご時世、セクハラだとかパワハラだとかどこで足をすくわれるのかわからない。八歳も年下の新卒社員と三十歳の私がどうにかなるなんて誰も思わないだろうけれど、用心するに越したことはない。
「検索してみますね」
椿くんはスマホで近くの宿泊施設を探し始める。
「うん、ありがとう。よろしく」
私は市街地へと車を進めた。しかし、目立った商業施設もなく商店街はほとんどシャッターが閉まっている。私も毎月のように全国各地を回っているけれど、観光資源のない山間部の町はどこも同じようだ。だからこそ、地元食材を使用した埋もれた名産品を全国に広められたらと考えている。
「藤堂主任、その先右に曲がってください」
スマホから顔を上げた椿くんは少し先を指さす。
「うん、わかった」
私はハンドルを切る。
「信州っていう旅館です」
見えてきたのはかなりレトロな木造の建物。かやぶき屋根に雪が降り積もっている。
「ここかな。ずいぶん雰囲気のある旅館だね」
「そうですね。うわ、駐車場いっぱいですね……」
私たちと同じように雪で足止めされた泊まり客だろうか。かろうじて空いている駐車スペースに車を止め、入り口のドアを開ける。「すみませーん」と声を掛ける。するとカウンターの奥から紺色の法被を着た番頭らしき男性が出てくる。
「いらっしゃいませ。ご宿泊ですか?」
「はい、予約はしていないんですが、二部屋おねがいできますか?」
「お待ちください。……まだ空いてたっけなぁ」といって番頭さんは宿帳を捲る。
「お客さん。申し訳ないけど、今夜ご用意できるのはひと部屋だけですね。この雪で急に泊り客が増えちゃったもんで。わるいねぇ」
申し訳なさそうに番頭さんは頭を下げる。ひと部屋確保できただけでもラッキーだったかもしれない。
「じゃあ、椿くんがひとりでここに泊まって」
私の提案に椿くんは目を見張る。
「それじゃあ、主任はどうするんですか?」
「ほかの宿を探してみる」
安心させるように笑ってみせて、番頭さんへ聞く。
「あのすみません。この近くに宿ってありますか?」
「あるにはあるけど、車で二、三十分はかかりますよ」
「結構遠いですね……」
行けない距離ではないが不慣れな道と吹雪ではさらに時間がかかるだろう。現時点で空室がある保証もない。電話して確かめるか。考えあぐねていると、椿くんはいう。
「藤堂主任、主任が部屋で寝て下さい! 俺は車で寝ます。そうしましょう!」
無理のある提案だ。私はぶんぶんと首を横に振る。
「そんなこことさせられないよ。私が車でいい」
「俺だってそんなことさせられませんよ! 上司を車で休ませるなんてありえないです。凍死したらどうするですか? 主任がどうぞ!」
いい出したら聞かない――のは私も同じか。
「それを言ったら椿くんだって同じじゃない! じゃあ、上司命令にすればいい?」
「職権乱用ですよ、それ」
お互いに譲り合っていると宿の電話が鳴った。番頭さんは電話に出るなりチラリとこちらを見る。いやな予感がする。
「ええ、はい。これからですか、少々お待ちくださいね」と言って電話を置いた。
「お客さんたち。宿泊希望の電話かが掛かって来てるんだけど、泊まるの?泊まらないの?」
「泊ります!」
椿くんと言葉が被り、ふたりで顔を見合わせた。
「主任さえよければ一緒に!」
「私も椿くんが嫌じゃなければ一緒で!」
背に腹は代えられない。いやそれは椿くんのセリフか……。これは誰がどう見ても緊急事態で、命の危機で、やましい気持ちなんてイチミリもなくてもしコンプライアンスに抵触するとかしないとか会社側が何か言ってきたら私は断固として戦う!それくらいの気持ちで今夜椿くんと一夜を明かそう。
「はい! 二名様ご案内~」
やけに明るい番頭さんの声に背中を押され、宿帳に記入する。それから案内されたのは十畳ほどの和室だった。床の間にテレビと冷蔵庫があるだけのシンプルな部屋。お風呂は温泉を引いているらしく、二十四時まで入浴可能だと説明された。布団はあとで仲居さんが敷きに来てくれるという。
「なんとなく懐かしい感じがする部屋ですね」
部屋を見渡して椿くんは言う。確かに昭和レトロなこの旅館はノスタルジーを感じさせる趣がある。
「とりあえず、お風呂入ってくるね。椿くんもゆっくり温まってきたら?」
「はい、そうします」
できるだけ一緒にいない方がいいだろうと私は浴衣をもってそそくさと部屋を出る。
薄暗い廊下を進み、赤い文字で女と書かれた暖簾をくぐる。籐で編まれたカゴに脱いだ服を入れると引き戸を開けた。
「うわ、すご~い」
湯気の先には一面の銀世界が広がっている。
「露天風呂とは思わなかった」
てっきり内風呂かと思っていたので喜びもひとしお。体を洗い、かけ湯をしてからそろりとお湯につかる。冷えた体に熱いお湯が沁みていく。
しばらく温泉を堪能すると、火照った体を浴衣で包み部屋へと戻った。襖をゆっくり開けると布団が二組敷かれている。しかもピタリと隣り合わせに。
「いやこれは……椿くんが帰って来ないうちにどうにかしなきゃな」
私は布団の端を持ち、横へスライドさせて、二枚の間を最大限に広げる。
「これくらい離れてればいいかな、よし!」
「なにがよしなんですか?」
急に背後から声を掛けられて心臓が止まるかと思った。
「つ、椿くん。おかえり」
声が裏返る。
「なにしてるんです?」
「別に、なにもしてないよ。そろそろ寝る?」
寝てしまえばあとは朝を待つだけ。疲れているからきっと一瞬で眠る自信がある。
「もしよければ、なんですが一杯付き合ってくれませんか?」
そういうと、椿くんは窓際に置いてあった袋の中から風呂敷に包まれた日本酒を取り出す。
「窓際に置いておいたからいい感じに冷えてますよ」
「その日本酒って?」
「小林酒造の社長からいただいたんです。試作品らしいんですが、美味しいに決まってます」
お土産までもらっていたなんて驚きだ。よほど気に入られたのだろう。
「さすが椿くんだね」
彼は物腰が柔らかで、中性的な魅力がある。女性はもちろんこと、年配男性にも好感度が高い。他人の懐に入り込むのが上手くて、交渉の場に強いのはバイヤーとして必要なスキルだ。まだ駆け出しだが、私のことなどすぐに追い抜いてしまうだろう。
「いえいえ、たまたまです。で、飲みます? 小林酒造の試作品」
「うん、飲んでみたい」
仕事につながるのであれば、断る理由はない。椿くんは宿のグラスに日本酒を注ぐ。その瞬間白ワインのような甘く爽やかな香りがひろがる。
「でも驚いたな。椿くんが長野出身だったなんて。てっきり東京育ちかと思ってたから」
「東京育ちですよ、俺。母方の祖母が長野出身手だけで」
ケロリとした顔で、そう言ってのける。
「えっ?」
なにそれ?嘘ではないのかもしれないけれど、騙された!小林社長だってきっと……。
「くーっ、沁みる。これ旨いっすよ。主任も飲んでください、ほら早く」
「あ、うん」
上手くはぐらかされた気もするが、私はグラスに口を付ける。とろりとした口当たり。お米のふくよかな旨みとコクを感じさせながらすっきりと切れのある後味。
「これ、熱燗でもいいかもね」
冷やしてももちろん美味しいが、熱燗にしておでんや炙ったスルメなんかと合わせたら最高だ。
「ね、俺もそう思います。帰ったら試してみませんか? もう一本いただいたんです」
「いいね、飲もう!」
社内で試飲会をするほどの量ではないが、好評を得たら正式に小林酒造に製造依頼をしようと思う。もちろん、エドガーデンでの販売を見据えてだ。
「約束ですよ。それで、いつにします?」
「金曜日の仕事終わりとか? その方がみんな都合がいいでしょう」
週末の方が集まりはいいと思った。それなのに椿くんは否定するように首を振る。
「いや、会社の人たちはどうでもいいです」
「ええと、どうして……?」
混乱を悟られないように冷静に問いかける。すると予想外の答えが返ってくる。
「俺と主任、二人で飲みたいんです。ずっとどうやって誘おうか、考えていました」
「冗談だよね?」
あえて明るく聞き返したのに真剣な表情を向けられて鼓動が逸る。
「冗談でこんなこと言いませんよ。だって俺、和紗さんのこと好きなんですから。俺と付き合ってください!」
いつになく真剣な表情で椿くんは言う。仕事で見せるものとは違う。私の知らない男の顔をしていた。
「待って。椿くん酔ってるでしょう?」
しかもさっき、下の名前で呼んでなかった?
「酔ってません。酔いに任せて告白なんてしませんよ。和紗さんは俺のこと、どう思ってますか?」
「ど、どうって」
突然の告白に狼狽えることしかできない私を真剣な眼差しで射貫く。
私もこんな風に後先考えず自分の思いを口にしていた時期があった。でも社会人になって年を重ねるとどうしても慎重になってしまうものだ。時に恋愛感情は人を傷つけることがあると知ってしまったから。
「椿くんは優秀な部下。それ上でも以下でもない」
きちんと線を引いた。それなのに彼は簡単に超えてくる。
「どうしたら部下以上になれますか?」
「部下は部下だよ……それに私なんかと噂になったら出世にひびくよ。椿くんも知ってるんでしょ? 私が本社から出向になった理由」
椿くんは申し訳なさそうに「はい」と頷く。
「だったら、あきらめて」
「俺、本気なんで簡単にあきらめたりしません。こうして和紗さんと働いていれば、あの噂が真実じゃないって分かります。むしろ被害者ではないんですか?」
嗚呼、それをいってくれるのがどうして彼なんだろう。
三年前、私には社内に婚約者がいた。
新卒で入社した私の教育係だった湯山秀哉は三歳年上で、営業部のエースと呼ばれるような優秀な人だった。彼からの告白で交際を始め、二年ほど付き合ってからサプライズでのプロポーズ。お互いの両親への挨拶を終えて式場選びを始めたころ、後輩の女の子の妊娠が発覚。彼との子だった。しかも四か月を超えていて、産むつもりだと告白された。
私は取り乱して、彼女のことをひどくののしってしまった。それを録音していた彼女は私からパワーハラスメントを受けたと内部通報したのだ。さらに婚約者へも付きまとい行為とセクシャルハラスメントを行ったとして停職処分を受けたのち、子会社への出向を言い渡された。
事情を知る一部の同僚たちは私の出向に反対してくれたのだけれど、あの二人のいる部署で働くのは地獄でしかなく異動を受け入れることにした。会社を辞めなかったのは、自分に非がないことを示したかったから。それが私の意地だったのかもしれない。
悪い噂は年々少なくなってはいるけれど、たまに聞こえてくるソレは私に恋愛のへの恐怖心を植え付けるには十分だった。
「そうだとしても、私はもう三十だし椿くんとは釣り合わないよ」
私が大学生の時、彼はまだ小学生だった。今は社会人という同じ枠組みにいるけれど。
「年齢を断る理由にしないでください」
「でも、いつかきつと若い子に走る」
「いやそれ、誰のこと言ってるんですか? あなたが俺を好きでいてくれる限り、絶対に浮気はしません」
誰だって最初はそう思う。この人だけが好きだと。でも人は裏切る。信じていた人に私は裏切られた。
「ごめん、信じられない」
わずかな沈黙の後、椿くんは口を開く。
「……そうですよね。いきなりこんな告白されて困りますよね。でも俺、この気持ちが本物だってもらうまで諦めたりしませんから」
怖いくらい真っ直ぐな瞳で私を見る。彼の本気が十分すぎるほど伝わる。
「わかった、私もちゃんと向き合ってみる。でも――きゃっ」
椿くんはいきなり私を抱きしめる。驚いて体がこわばる。
「すみません、なんかうれしくてつい」
「ついって、あのね。こういうの……、」
「イヤですか?そうじゃなければ少しだけこのままでいてください」
イヤかどうか聞かれると嫌ではない気がする。驚きはしたけれど、椿くんの体温は不思議なほど肌になじむ。まるで溶け合うみたいに心地がいい。
「なんか、椿くん温かくて、いい匂いする」
たとえるなら、ひだまりのような暖かな匂い。無意識にスンスンと鼻を近づける。すると椿くんはサッと私から離れた。
「……やっぱり俺、酔ったみたいで。先に寝ますね。おやすみなさい」
「あ、うん。おやすみなさい」
そういうと布団にもぐり込むと頭まですっぽりと覆ってしまった。
翌朝目を覚ますと椿くんはまだ寝ていた。
すーすーと寝息をたてる無防備な寝顔に既視感を覚える。すこしして、実家で飼っていたゴールデンレトリバーに似ていることに気付く。顔というよりは、好奇心旺盛で優しい性格が似ているのかもしれない。
椿くんが起きてしまう前に素早く着替えてメイクをする。それから番頭さんに雪下ろしの道具を借りて外へ出た。
朝日が雪に反射して辺り一面が銀色に輝いている。今日は一日中晴れの予報だ。
車の上に積もった雪を払いのけ、エンジンをかけてフロントガラスの氷を解かす。少しして椿くんがやってくる。
「おはようございます。ここにいたんですね」
「おはよう、早いね」
「主任こそ。起こしてくれたら俺がやったのに……」
いつも通りの椿くんに私はホッと胸をなでおろす。気まずい感じになってしまったらどうしようと不安だったけれど、取り越し苦労だったようだ。
「ごめんね。気持ちよさそうに寝てたから起こすのやめたの。ほら、戻って朝ごはん食べよう!」
私は椿くんと宿の朝食を食べ、東京へと車を走らせた。
「椿くん、ごめんね」
激しい吹雪の影響で高速道路が通行止めになった後、迂回を余儀なくされた車の渋滞にハマりかれこれ三十分以上は過ぎただろうか。いつになったら東京へ帰れるのか、焦りと不安が押し寄せてくる。
「どうして藤堂主任が謝るんですか?」
助手席に座る部下の椿遥人はすぐに「主任のせいじゃありませんよ」と否定してくれる。けれど、大雪の予報が出ているのを知りながら現場にとどまる判断をしたのは私だ。
「でも、小林夫妻の誘いを受けたのは私で、あと一時間でも早く出発していたらこんなことにはならなかったはずだから……」
「いいえ、あれは最良の判断でしたよ」
そう言い切ってくれる彼の言葉にほんの少し救われた気がする。
私が勤務するエドガーデンは純国産にこだわった食材や雑貨を扱うセレクトショップ。経営母体は志木リゾートで主にリゾート開発を手掛けている専門デベロッパー。
私はそこから出向という形で飛ばされて二年が経とうとしている。当初はまるで畑違いの業種にどうなることかと思ったが、全国の美味しいものを探すのも、名品を見つけるのも楽しい。
今日の目的は幻とされる日本酒の買い付け。今朝早くに私は都内でレンタカーを借り、椿くんを助手席に乗せて長野へと向かった。
松川村にある造り酒屋には二度断られているのだけれど、どうしてもこのおいしさを多くの人に知ってもらいたかったから。
*
「そこをなんとかお願いできないでしょうか?」
酒蔵の軒先でなんども頭を下げると大きなため息が降ってくる。
「……うちはね、家族経営だから大量生産できないんだよ。東京のおしゃれな店に並べる商品でもないし。なんども来てもらって答えはおんなじ。悪いんだけどもう帰って」
毎回同じ文句で断られていた。数本単位では物流コストがかかりすぎるので販売店舗を限定するにしても最低五十本は確保したいところ。けれど、地元スーパーや酒屋に卸す分を差し引くと我が社に納品できるのは多くて十五本なのだという。
「それでしたら」
そう口を開いたのは椿くんだった。
「180mlの飲み切りサイズを作るのはいかがでしょう? 小林酒造の美味しい日本酒をよりたくさんの人に楽しんでいただきたい。僕のルーツでもある信州の、日本の良さを若い人たちにも伝えていきたいんです。そのためにもお力をお貸しいただけないでしょうか?」
彼の提案は小林社長の心を動かしたようで、なんと180mlの小瓶の日本酒を製造してもらえることになったのだ。瓶のデザインもこちらに任せてもらえるという。それだけでなく、夕飯を食べていかないかと誘われて、断り切れずに奥さんの手作り料理をいただくことになった。今後の仕事の話に花が咲き、お宅を出る頃にはすっかり日も暮れて大粒の雪が降り始めていた。
*
車は少しずつ流れてきていた。しかしこのまま下道で帰るとなると到着は夜中になるだろう。山道を抜ければもう少し時短になるけれど、この雪では危険が伴う。
「ねえ、椿くん。もし嫌ならはっきりいってもらって構わないんだけど……」
私は恐る恐るといった感じで話を切り出す。
「はい、なんでしょう」
「東京へ帰るの、明日でもよかったりする? この天候だと大切な部下を安全に送り届ける自信がなくて」
言葉選びは慎重にしなければいけない。部下を誘ったなんて言われてしまわないように。
「もちろんいいですよ。俺が免許証忘れたせいで、こんな吹雪の中、藤堂主任に運転させ続けるのは申し訳ないなって思っていたんです。このあたりでホテル探しましょう」
話の早い部下でよかった。椿くんならば面倒なことは言わないだろうと分かってはいたのだけれど、このご時世、セクハラだとかパワハラだとかどこで足をすくわれるのかわからない。八歳も年下の新卒社員と三十歳の私がどうにかなるなんて誰も思わないだろうけれど、用心するに越したことはない。
「検索してみますね」
椿くんはスマホで近くの宿泊施設を探し始める。
「うん、ありがとう。よろしく」
私は市街地へと車を進めた。しかし、目立った商業施設もなく商店街はほとんどシャッターが閉まっている。私も毎月のように全国各地を回っているけれど、観光資源のない山間部の町はどこも同じようだ。だからこそ、地元食材を使用した埋もれた名産品を全国に広められたらと考えている。
「藤堂主任、その先右に曲がってください」
スマホから顔を上げた椿くんは少し先を指さす。
「うん、わかった」
私はハンドルを切る。
「信州っていう旅館です」
見えてきたのはかなりレトロな木造の建物。かやぶき屋根に雪が降り積もっている。
「ここかな。ずいぶん雰囲気のある旅館だね」
「そうですね。うわ、駐車場いっぱいですね……」
私たちと同じように雪で足止めされた泊まり客だろうか。かろうじて空いている駐車スペースに車を止め、入り口のドアを開ける。「すみませーん」と声を掛ける。するとカウンターの奥から紺色の法被を着た番頭らしき男性が出てくる。
「いらっしゃいませ。ご宿泊ですか?」
「はい、予約はしていないんですが、二部屋おねがいできますか?」
「お待ちください。……まだ空いてたっけなぁ」といって番頭さんは宿帳を捲る。
「お客さん。申し訳ないけど、今夜ご用意できるのはひと部屋だけですね。この雪で急に泊り客が増えちゃったもんで。わるいねぇ」
申し訳なさそうに番頭さんは頭を下げる。ひと部屋確保できただけでもラッキーだったかもしれない。
「じゃあ、椿くんがひとりでここに泊まって」
私の提案に椿くんは目を見張る。
「それじゃあ、主任はどうするんですか?」
「ほかの宿を探してみる」
安心させるように笑ってみせて、番頭さんへ聞く。
「あのすみません。この近くに宿ってありますか?」
「あるにはあるけど、車で二、三十分はかかりますよ」
「結構遠いですね……」
行けない距離ではないが不慣れな道と吹雪ではさらに時間がかかるだろう。現時点で空室がある保証もない。電話して確かめるか。考えあぐねていると、椿くんはいう。
「藤堂主任、主任が部屋で寝て下さい! 俺は車で寝ます。そうしましょう!」
無理のある提案だ。私はぶんぶんと首を横に振る。
「そんなこことさせられないよ。私が車でいい」
「俺だってそんなことさせられませんよ! 上司を車で休ませるなんてありえないです。凍死したらどうするですか? 主任がどうぞ!」
いい出したら聞かない――のは私も同じか。
「それを言ったら椿くんだって同じじゃない! じゃあ、上司命令にすればいい?」
「職権乱用ですよ、それ」
お互いに譲り合っていると宿の電話が鳴った。番頭さんは電話に出るなりチラリとこちらを見る。いやな予感がする。
「ええ、はい。これからですか、少々お待ちくださいね」と言って電話を置いた。
「お客さんたち。宿泊希望の電話かが掛かって来てるんだけど、泊まるの?泊まらないの?」
「泊ります!」
椿くんと言葉が被り、ふたりで顔を見合わせた。
「主任さえよければ一緒に!」
「私も椿くんが嫌じゃなければ一緒で!」
背に腹は代えられない。いやそれは椿くんのセリフか……。これは誰がどう見ても緊急事態で、命の危機で、やましい気持ちなんてイチミリもなくてもしコンプライアンスに抵触するとかしないとか会社側が何か言ってきたら私は断固として戦う!それくらいの気持ちで今夜椿くんと一夜を明かそう。
「はい! 二名様ご案内~」
やけに明るい番頭さんの声に背中を押され、宿帳に記入する。それから案内されたのは十畳ほどの和室だった。床の間にテレビと冷蔵庫があるだけのシンプルな部屋。お風呂は温泉を引いているらしく、二十四時まで入浴可能だと説明された。布団はあとで仲居さんが敷きに来てくれるという。
「なんとなく懐かしい感じがする部屋ですね」
部屋を見渡して椿くんは言う。確かに昭和レトロなこの旅館はノスタルジーを感じさせる趣がある。
「とりあえず、お風呂入ってくるね。椿くんもゆっくり温まってきたら?」
「はい、そうします」
できるだけ一緒にいない方がいいだろうと私は浴衣をもってそそくさと部屋を出る。
薄暗い廊下を進み、赤い文字で女と書かれた暖簾をくぐる。籐で編まれたカゴに脱いだ服を入れると引き戸を開けた。
「うわ、すご~い」
湯気の先には一面の銀世界が広がっている。
「露天風呂とは思わなかった」
てっきり内風呂かと思っていたので喜びもひとしお。体を洗い、かけ湯をしてからそろりとお湯につかる。冷えた体に熱いお湯が沁みていく。
しばらく温泉を堪能すると、火照った体を浴衣で包み部屋へと戻った。襖をゆっくり開けると布団が二組敷かれている。しかもピタリと隣り合わせに。
「いやこれは……椿くんが帰って来ないうちにどうにかしなきゃな」
私は布団の端を持ち、横へスライドさせて、二枚の間を最大限に広げる。
「これくらい離れてればいいかな、よし!」
「なにがよしなんですか?」
急に背後から声を掛けられて心臓が止まるかと思った。
「つ、椿くん。おかえり」
声が裏返る。
「なにしてるんです?」
「別に、なにもしてないよ。そろそろ寝る?」
寝てしまえばあとは朝を待つだけ。疲れているからきっと一瞬で眠る自信がある。
「もしよければ、なんですが一杯付き合ってくれませんか?」
そういうと、椿くんは窓際に置いてあった袋の中から風呂敷に包まれた日本酒を取り出す。
「窓際に置いておいたからいい感じに冷えてますよ」
「その日本酒って?」
「小林酒造の社長からいただいたんです。試作品らしいんですが、美味しいに決まってます」
お土産までもらっていたなんて驚きだ。よほど気に入られたのだろう。
「さすが椿くんだね」
彼は物腰が柔らかで、中性的な魅力がある。女性はもちろんこと、年配男性にも好感度が高い。他人の懐に入り込むのが上手くて、交渉の場に強いのはバイヤーとして必要なスキルだ。まだ駆け出しだが、私のことなどすぐに追い抜いてしまうだろう。
「いえいえ、たまたまです。で、飲みます? 小林酒造の試作品」
「うん、飲んでみたい」
仕事につながるのであれば、断る理由はない。椿くんは宿のグラスに日本酒を注ぐ。その瞬間白ワインのような甘く爽やかな香りがひろがる。
「でも驚いたな。椿くんが長野出身だったなんて。てっきり東京育ちかと思ってたから」
「東京育ちですよ、俺。母方の祖母が長野出身手だけで」
ケロリとした顔で、そう言ってのける。
「えっ?」
なにそれ?嘘ではないのかもしれないけれど、騙された!小林社長だってきっと……。
「くーっ、沁みる。これ旨いっすよ。主任も飲んでください、ほら早く」
「あ、うん」
上手くはぐらかされた気もするが、私はグラスに口を付ける。とろりとした口当たり。お米のふくよかな旨みとコクを感じさせながらすっきりと切れのある後味。
「これ、熱燗でもいいかもね」
冷やしてももちろん美味しいが、熱燗にしておでんや炙ったスルメなんかと合わせたら最高だ。
「ね、俺もそう思います。帰ったら試してみませんか? もう一本いただいたんです」
「いいね、飲もう!」
社内で試飲会をするほどの量ではないが、好評を得たら正式に小林酒造に製造依頼をしようと思う。もちろん、エドガーデンでの販売を見据えてだ。
「約束ですよ。それで、いつにします?」
「金曜日の仕事終わりとか? その方がみんな都合がいいでしょう」
週末の方が集まりはいいと思った。それなのに椿くんは否定するように首を振る。
「いや、会社の人たちはどうでもいいです」
「ええと、どうして……?」
混乱を悟られないように冷静に問いかける。すると予想外の答えが返ってくる。
「俺と主任、二人で飲みたいんです。ずっとどうやって誘おうか、考えていました」
「冗談だよね?」
あえて明るく聞き返したのに真剣な表情を向けられて鼓動が逸る。
「冗談でこんなこと言いませんよ。だって俺、和紗さんのこと好きなんですから。俺と付き合ってください!」
いつになく真剣な表情で椿くんは言う。仕事で見せるものとは違う。私の知らない男の顔をしていた。
「待って。椿くん酔ってるでしょう?」
しかもさっき、下の名前で呼んでなかった?
「酔ってません。酔いに任せて告白なんてしませんよ。和紗さんは俺のこと、どう思ってますか?」
「ど、どうって」
突然の告白に狼狽えることしかできない私を真剣な眼差しで射貫く。
私もこんな風に後先考えず自分の思いを口にしていた時期があった。でも社会人になって年を重ねるとどうしても慎重になってしまうものだ。時に恋愛感情は人を傷つけることがあると知ってしまったから。
「椿くんは優秀な部下。それ上でも以下でもない」
きちんと線を引いた。それなのに彼は簡単に超えてくる。
「どうしたら部下以上になれますか?」
「部下は部下だよ……それに私なんかと噂になったら出世にひびくよ。椿くんも知ってるんでしょ? 私が本社から出向になった理由」
椿くんは申し訳なさそうに「はい」と頷く。
「だったら、あきらめて」
「俺、本気なんで簡単にあきらめたりしません。こうして和紗さんと働いていれば、あの噂が真実じゃないって分かります。むしろ被害者ではないんですか?」
嗚呼、それをいってくれるのがどうして彼なんだろう。
三年前、私には社内に婚約者がいた。
新卒で入社した私の教育係だった湯山秀哉は三歳年上で、営業部のエースと呼ばれるような優秀な人だった。彼からの告白で交際を始め、二年ほど付き合ってからサプライズでのプロポーズ。お互いの両親への挨拶を終えて式場選びを始めたころ、後輩の女の子の妊娠が発覚。彼との子だった。しかも四か月を超えていて、産むつもりだと告白された。
私は取り乱して、彼女のことをひどくののしってしまった。それを録音していた彼女は私からパワーハラスメントを受けたと内部通報したのだ。さらに婚約者へも付きまとい行為とセクシャルハラスメントを行ったとして停職処分を受けたのち、子会社への出向を言い渡された。
事情を知る一部の同僚たちは私の出向に反対してくれたのだけれど、あの二人のいる部署で働くのは地獄でしかなく異動を受け入れることにした。会社を辞めなかったのは、自分に非がないことを示したかったから。それが私の意地だったのかもしれない。
悪い噂は年々少なくなってはいるけれど、たまに聞こえてくるソレは私に恋愛のへの恐怖心を植え付けるには十分だった。
「そうだとしても、私はもう三十だし椿くんとは釣り合わないよ」
私が大学生の時、彼はまだ小学生だった。今は社会人という同じ枠組みにいるけれど。
「年齢を断る理由にしないでください」
「でも、いつかきつと若い子に走る」
「いやそれ、誰のこと言ってるんですか? あなたが俺を好きでいてくれる限り、絶対に浮気はしません」
誰だって最初はそう思う。この人だけが好きだと。でも人は裏切る。信じていた人に私は裏切られた。
「ごめん、信じられない」
わずかな沈黙の後、椿くんは口を開く。
「……そうですよね。いきなりこんな告白されて困りますよね。でも俺、この気持ちが本物だってもらうまで諦めたりしませんから」
怖いくらい真っ直ぐな瞳で私を見る。彼の本気が十分すぎるほど伝わる。
「わかった、私もちゃんと向き合ってみる。でも――きゃっ」
椿くんはいきなり私を抱きしめる。驚いて体がこわばる。
「すみません、なんかうれしくてつい」
「ついって、あのね。こういうの……、」
「イヤですか?そうじゃなければ少しだけこのままでいてください」
イヤかどうか聞かれると嫌ではない気がする。驚きはしたけれど、椿くんの体温は不思議なほど肌になじむ。まるで溶け合うみたいに心地がいい。
「なんか、椿くん温かくて、いい匂いする」
たとえるなら、ひだまりのような暖かな匂い。無意識にスンスンと鼻を近づける。すると椿くんはサッと私から離れた。
「……やっぱり俺、酔ったみたいで。先に寝ますね。おやすみなさい」
「あ、うん。おやすみなさい」
そういうと布団にもぐり込むと頭まですっぽりと覆ってしまった。
翌朝目を覚ますと椿くんはまだ寝ていた。
すーすーと寝息をたてる無防備な寝顔に既視感を覚える。すこしして、実家で飼っていたゴールデンレトリバーに似ていることに気付く。顔というよりは、好奇心旺盛で優しい性格が似ているのかもしれない。
椿くんが起きてしまう前に素早く着替えてメイクをする。それから番頭さんに雪下ろしの道具を借りて外へ出た。
朝日が雪に反射して辺り一面が銀色に輝いている。今日は一日中晴れの予報だ。
車の上に積もった雪を払いのけ、エンジンをかけてフロントガラスの氷を解かす。少しして椿くんがやってくる。
「おはようございます。ここにいたんですね」
「おはよう、早いね」
「主任こそ。起こしてくれたら俺がやったのに……」
いつも通りの椿くんに私はホッと胸をなでおろす。気まずい感じになってしまったらどうしようと不安だったけれど、取り越し苦労だったようだ。
「ごめんね。気持ちよさそうに寝てたから起こすのやめたの。ほら、戻って朝ごはん食べよう!」
私は椿くんと宿の朝食を食べ、東京へと車を走らせた。