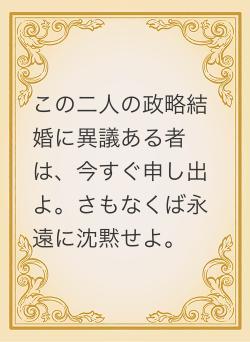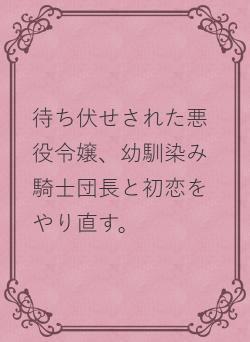気安い態度でオルランドは肩を竦めて、ヴィルフリートはさりげなく私の前に出て彼と対峙した。
「すみません。俺の恋人は照れ屋なんですよ。それにしても、この温室を昼寝場所にするなんて、センスありますね。薄暗くて……良く眠れそうだ」
ヴィルフリートは、温室の屋根を見上げた。
透明な硝子で出来ている屋根は、陽光をある程度遮蔽する魔法がかかっているので、どんなに眩しい昼間でもこの温室に降ってくる光量は一定だった。
「まあね。ヴィルフリートは使うなよ……わかっていると思うが」
「わかってますよ。俺は何もかもわかっている男なんで」
二人だけがわかり合うような視線を絡ませ合い、オルランドは苦笑して温室を出て行った。
「……あの、助けてくれてありがとうございます」
二人きりになって、私はまず感謝の言葉を口にした。
「おい。嫌なら、はっきり言え。しっかりしろよ。これから、一人で生きて行くんだろ? ブライス」
「っ……!」
はっきりと拒否の言葉は、何度も言いました……! 聞いてくれなかっただけで!
「ちっ……違います! それは……っ!」
「すみません。俺の恋人は照れ屋なんですよ。それにしても、この温室を昼寝場所にするなんて、センスありますね。薄暗くて……良く眠れそうだ」
ヴィルフリートは、温室の屋根を見上げた。
透明な硝子で出来ている屋根は、陽光をある程度遮蔽する魔法がかかっているので、どんなに眩しい昼間でもこの温室に降ってくる光量は一定だった。
「まあね。ヴィルフリートは使うなよ……わかっていると思うが」
「わかってますよ。俺は何もかもわかっている男なんで」
二人だけがわかり合うような視線を絡ませ合い、オルランドは苦笑して温室を出て行った。
「……あの、助けてくれてありがとうございます」
二人きりになって、私はまず感謝の言葉を口にした。
「おい。嫌なら、はっきり言え。しっかりしろよ。これから、一人で生きて行くんだろ? ブライス」
「っ……!」
はっきりと拒否の言葉は、何度も言いました……! 聞いてくれなかっただけで!
「ちっ……違います! それは……っ!」