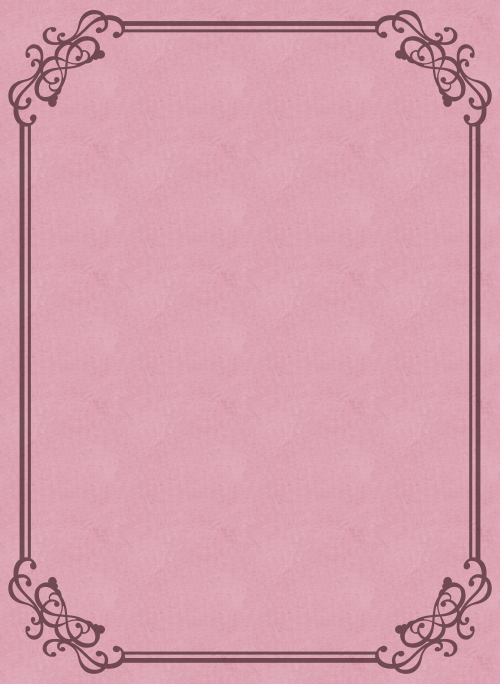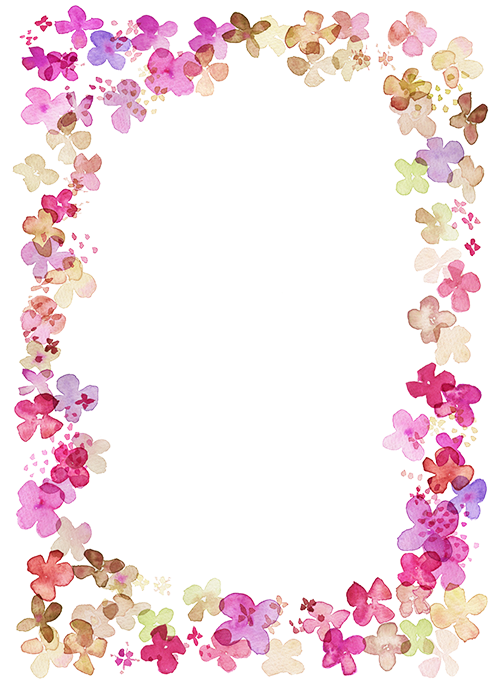病院の集中治療室。
消毒液の匂いと、機械のピッピッという無機質な音だけが響く。
泣き虫の白者は、ベッドに横たわったまま動けない。 顔はぐるぐる巻きの包帯で覆われ、目も鼻も口も、すべてが白い布の下に埋もれている。 外の世界は、もう見えない。 聞こえるのは、自分の浅い呼吸と、心臓の弱々しい鼓動だけ。
若い研修医が、カーテンを引いて入ってきた。 白衣の袖がまだ短く、名札も新品だ。
「おい、ちょっと。名前は? 身元は? 誰か連絡できる家族いるか?」
白者は、答えたかった。 喉を震わせ、声を絞り出そうとした。 だが——
何も、出ない。
声帯はもう、粉々に砕かれていた。
「……は? 喋れねぇの? マジかよ……」
研修医は呆れたように息を吐き、カルテをパタンと閉じた。
「わかんねぇなら仕方ねぇか。通報した警官にでも聞くしかねぇな」
そう呟いて、踵を返した。 カーテンが揺れ、足音が遠ざかる。
部屋に残されたのは、包帯に閉じ込められた白者の体と、静かな機械音だけ。
白者は、動けない瞳の奥で、ゆっくりと思い出す。
義理の姉貴の優しい手、小さな義理の弟の笑い声。 三人で見た夕焼け。 あの温かさ、あの匂い。 あの、たった一度きりの、家族という名の時間。
もう、二度と戻らない。
それでも、白者の心は、その記憶を繰り返し、繰り返し、抱きしめていた。
どれだけの時間が過ぎたか。 カーテンが、再び引かれる音。
今度は違う足音。 落ち着いていて、確信に満ちた歩み。
キム・ゴヌ。 医師免許は確かに持っている。 ただ、それだけだ。
彼は無言でベッドに近づき、トレイの上に置かれた注射器を手に取った。
極太の針、透明な筒の中に、大量のモルヒネが揺れている。
「もう、十分苦しんだろ」
低い声。 感情はない。 ただ、事実を述べるように。
白者の首筋に、冷たいアルコール綿が触れる。
そして——
ズブリ。
針が深く、深く刺さる。
薬液が、ゆっくりと、確実に、血管に流れ込む。
白者の体が、わずかに震えた。
包帯の下で、白い瞳が、かすかに開く。
視界は、もう何も映さない。
ただ、遠くに、義理の家族の笑顔が、ぼんやりと浮かんでいた。
「……あ……」
最後の息が、掠れた風のように漏れる。
心電図の波形が、ゆっくりと、平らになっていく。
ピーッ…… ピーッ…… ピー——————————
機械が、終わりを告げる。
キム・ゴヌは、注射器をトレイに戻し、何事もなかったように部屋を出た。
カーテンが、静かに閉まる。
白い包帯に覆われた体は、もう、動かない。
泣き虫の白者は、ようやく、すべてを終わらせた。
外では、都心の冬の風が、冷たく吹き抜けていく。
誰も、もう泣かない。
消毒液の匂いと、機械のピッピッという無機質な音だけが響く。
泣き虫の白者は、ベッドに横たわったまま動けない。 顔はぐるぐる巻きの包帯で覆われ、目も鼻も口も、すべてが白い布の下に埋もれている。 外の世界は、もう見えない。 聞こえるのは、自分の浅い呼吸と、心臓の弱々しい鼓動だけ。
若い研修医が、カーテンを引いて入ってきた。 白衣の袖がまだ短く、名札も新品だ。
「おい、ちょっと。名前は? 身元は? 誰か連絡できる家族いるか?」
白者は、答えたかった。 喉を震わせ、声を絞り出そうとした。 だが——
何も、出ない。
声帯はもう、粉々に砕かれていた。
「……は? 喋れねぇの? マジかよ……」
研修医は呆れたように息を吐き、カルテをパタンと閉じた。
「わかんねぇなら仕方ねぇか。通報した警官にでも聞くしかねぇな」
そう呟いて、踵を返した。 カーテンが揺れ、足音が遠ざかる。
部屋に残されたのは、包帯に閉じ込められた白者の体と、静かな機械音だけ。
白者は、動けない瞳の奥で、ゆっくりと思い出す。
義理の姉貴の優しい手、小さな義理の弟の笑い声。 三人で見た夕焼け。 あの温かさ、あの匂い。 あの、たった一度きりの、家族という名の時間。
もう、二度と戻らない。
それでも、白者の心は、その記憶を繰り返し、繰り返し、抱きしめていた。
どれだけの時間が過ぎたか。 カーテンが、再び引かれる音。
今度は違う足音。 落ち着いていて、確信に満ちた歩み。
キム・ゴヌ。 医師免許は確かに持っている。 ただ、それだけだ。
彼は無言でベッドに近づき、トレイの上に置かれた注射器を手に取った。
極太の針、透明な筒の中に、大量のモルヒネが揺れている。
「もう、十分苦しんだろ」
低い声。 感情はない。 ただ、事実を述べるように。
白者の首筋に、冷たいアルコール綿が触れる。
そして——
ズブリ。
針が深く、深く刺さる。
薬液が、ゆっくりと、確実に、血管に流れ込む。
白者の体が、わずかに震えた。
包帯の下で、白い瞳が、かすかに開く。
視界は、もう何も映さない。
ただ、遠くに、義理の家族の笑顔が、ぼんやりと浮かんでいた。
「……あ……」
最後の息が、掠れた風のように漏れる。
心電図の波形が、ゆっくりと、平らになっていく。
ピーッ…… ピーッ…… ピー——————————
機械が、終わりを告げる。
キム・ゴヌは、注射器をトレイに戻し、何事もなかったように部屋を出た。
カーテンが、静かに閉まる。
白い包帯に覆われた体は、もう、動かない。
泣き虫の白者は、ようやく、すべてを終わらせた。
外では、都心の冬の風が、冷たく吹き抜けていく。
誰も、もう泣かない。