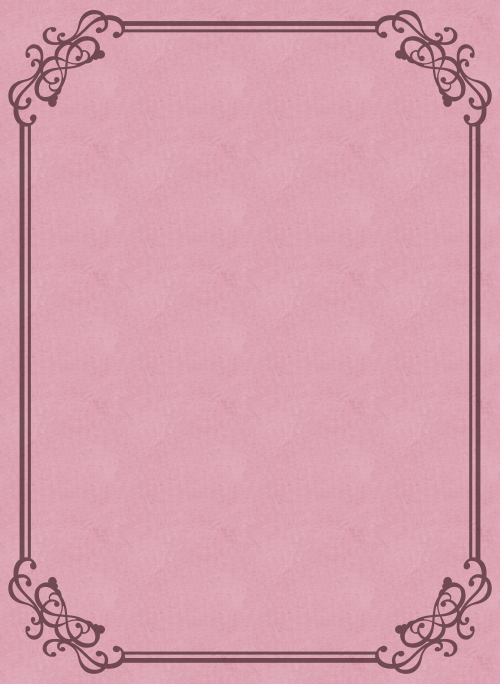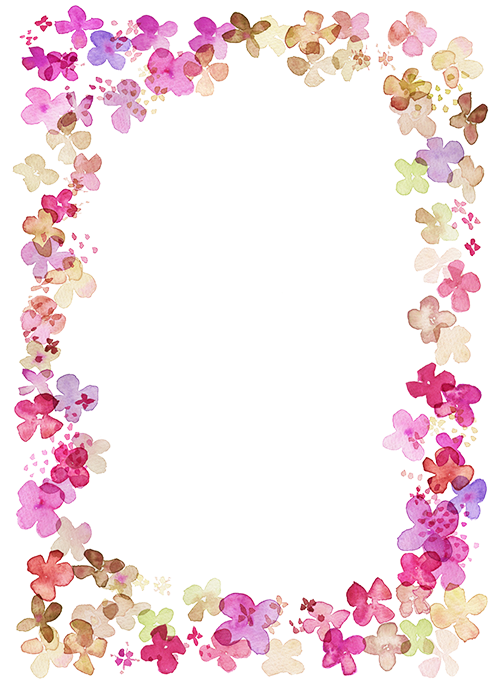ホテルの自動ドアが、乾いた音を立てて閉まる。
朝の陽光が眩しく、白者の白い瞳を刺す。
体はまだ昨夜の痛みを引きずり、歩くたびに骨が軋む。
それでも、白者は一歩ずつ、アスファルトの駐車場へ踏み出した。
その瞬間——
「うわっ、いるじゃん! マジで生きてた!」
甲高い、複数重なる笑い声。 駐車場の隅、錆びたワンボックスの影から、五、六人の小さな影が飛び出してきた。
フェアリー集団。 白者よりは全然小さかった。 色とりどりの髪、透き通った羽根、そして、手にはそれぞれ凶器めいた小さな道具。
「昨日のお前、めっちゃボコられてたって聞いたよ〜? まだ動けるんだ? すげー!」
リーダー格らしいピンク髪のフェアリーが、舌なめずりしながら近づく。
白者は反射的に身構えた。だが、体は言うことを聞かない。拳を握るだけで、肋骨が悲鳴を上げる。
「抵抗すんなよ〜、すぐ終わるから」
最初の一撃は、青い髪のフェアリーが放った。 小さな手から迸る青白い電撃。
ビリビリッ!
白者の全身が硬直し、膝から崩れ落ちた。
「動けなくなった〜! ラッキー!」
歓声が上がる。
赤毛のフェアリーが、白者の足元にしゃがみ込み、白いボロボロのスリッポンだった靴を片方ずつ強引に引き剥がした。
「ダサっ! こんなのいらねー!」
ポイッ、と二足とも、遠くのゴミ箱めがけて投げ捨てる。
次に、緑髪のフェアリーが小さなカッターを抜いた。 刃渡り五センチにも満たない、事務用のそれ。
「ちょっとだけ、遊ぼうか」
スッ、スッ、スッ……
白者の腕、太もも、ふくらはぎ。 細かく、浅く、しかし確実に皮膚を裂いていく。 血の線が、蜘蛛の巣のように広がる。
「痛い? 痛いよね〜? でも声出せないんだもんね、かわいそ〜」
紫髪のフェアリーが、爪を立てて白者の首に飛びついた。 ギュッと掴み、爪を深く食い込ませながら、ぐるぐると回す。
肉が裂ける音、鮮血が噴き出し、首筋を真っ赤に染める。
「まだ首、切れてないじゃん! もっとやろー!」
最後の一人——オレンジ髪の、小柄なフェアリー。 手に持っているのは、子供用の三徳包丁、刃は錆びて鈍いが、それでも十分に鋭い。
「ごめんね〜、これで終わりだよ」
フェアリーは白者の首元に刃を当て、ゆっくり、そして一気に押し込んだ。
グチュ……。
声帯が裂ける、湿った音。 白者の口から、血と泡が溢れ出す。 もう、言葉は出ない。声すら、出ない。
体は痙攣し、抵抗の意思すら、消え失せた。
「最後はこれ!」
ピンク髪のリーダーが、跳び上がった。 小さな体で全力の踏みつけ。 踵を、白者の顔面のど真ん中に叩き込む。
ゴキッ。
鼻骨が砕け、頬骨が陥没する。 白い髪が、血で真っ赤に染まった。
「……ふぅ」
フェアリーたちは、満足げに息を吐いた。
「終わった〜! 超楽しかった!」
「次はもっと強いヤツ探そっか」
「じゃあね〜!」
小さな羽根を震わせ、彼らは駐車場の影に消えていった。
残されたのは、血溜まりの中に横たわる、動かない白者の体だけ。
三十分後。 近隣をパトロールしていた制服の警官が、駐車場で異様な光景を見つけた。
「…………おい、大丈夫か!?」
無線が慌ただしく鳴る。 救急車のサイレンが、遠くから近づいてくる。
白者の白い瞳は、半開きのまま、空を映していた。
血に濡れた唇が、かすかに、動いた。
声は出ない。
サイレンが、朝の街に響き渡る。
その瞬間——
「うわっ、いるじゃん! マジで生きてた!」
甲高い、複数重なる笑い声。 駐車場の隅、錆びたワンボックスの影から、五、六人の小さな影が飛び出してきた。
フェアリー集団。 白者よりは全然小さかった。 色とりどりの髪、透き通った羽根、そして、手にはそれぞれ凶器めいた小さな道具。
「昨日のお前、めっちゃボコられてたって聞いたよ〜? まだ動けるんだ? すげー!」
リーダー格らしいピンク髪のフェアリーが、舌なめずりしながら近づく。
白者は反射的に身構えた。だが、体は言うことを聞かない。拳を握るだけで、肋骨が悲鳴を上げる。
「抵抗すんなよ〜、すぐ終わるから」
最初の一撃は、青い髪のフェアリーが放った。 小さな手から迸る青白い電撃。
ビリビリッ!
白者の全身が硬直し、膝から崩れ落ちた。
「動けなくなった〜! ラッキー!」
歓声が上がる。
赤毛のフェアリーが、白者の足元にしゃがみ込み、白いボロボロのスリッポンだった靴を片方ずつ強引に引き剥がした。
「ダサっ! こんなのいらねー!」
ポイッ、と二足とも、遠くのゴミ箱めがけて投げ捨てる。
次に、緑髪のフェアリーが小さなカッターを抜いた。 刃渡り五センチにも満たない、事務用のそれ。
「ちょっとだけ、遊ぼうか」
スッ、スッ、スッ……
白者の腕、太もも、ふくらはぎ。 細かく、浅く、しかし確実に皮膚を裂いていく。 血の線が、蜘蛛の巣のように広がる。
「痛い? 痛いよね〜? でも声出せないんだもんね、かわいそ〜」
紫髪のフェアリーが、爪を立てて白者の首に飛びついた。 ギュッと掴み、爪を深く食い込ませながら、ぐるぐると回す。
肉が裂ける音、鮮血が噴き出し、首筋を真っ赤に染める。
「まだ首、切れてないじゃん! もっとやろー!」
最後の一人——オレンジ髪の、小柄なフェアリー。 手に持っているのは、子供用の三徳包丁、刃は錆びて鈍いが、それでも十分に鋭い。
「ごめんね〜、これで終わりだよ」
フェアリーは白者の首元に刃を当て、ゆっくり、そして一気に押し込んだ。
グチュ……。
声帯が裂ける、湿った音。 白者の口から、血と泡が溢れ出す。 もう、言葉は出ない。声すら、出ない。
体は痙攣し、抵抗の意思すら、消え失せた。
「最後はこれ!」
ピンク髪のリーダーが、跳び上がった。 小さな体で全力の踏みつけ。 踵を、白者の顔面のど真ん中に叩き込む。
ゴキッ。
鼻骨が砕け、頬骨が陥没する。 白い髪が、血で真っ赤に染まった。
「……ふぅ」
フェアリーたちは、満足げに息を吐いた。
「終わった〜! 超楽しかった!」
「次はもっと強いヤツ探そっか」
「じゃあね〜!」
小さな羽根を震わせ、彼らは駐車場の影に消えていった。
残されたのは、血溜まりの中に横たわる、動かない白者の体だけ。
三十分後。 近隣をパトロールしていた制服の警官が、駐車場で異様な光景を見つけた。
「…………おい、大丈夫か!?」
無線が慌ただしく鳴る。 救急車のサイレンが、遠くから近づいてくる。
白者の白い瞳は、半開きのまま、空を映していた。
血に濡れた唇が、かすかに、動いた。
声は出ない。
サイレンが、朝の街に響き渡る。