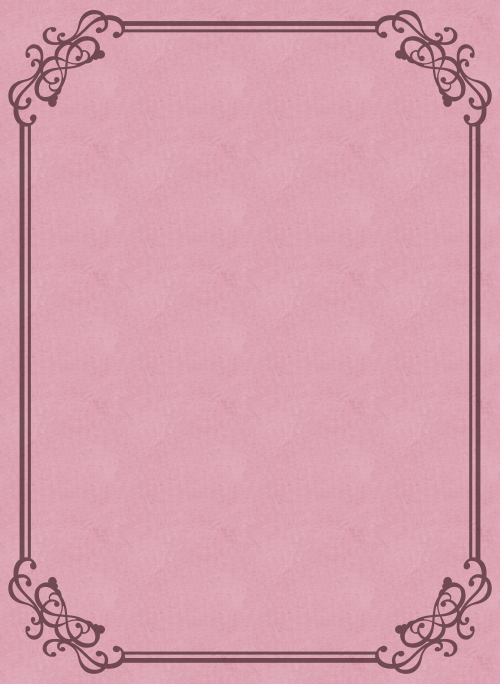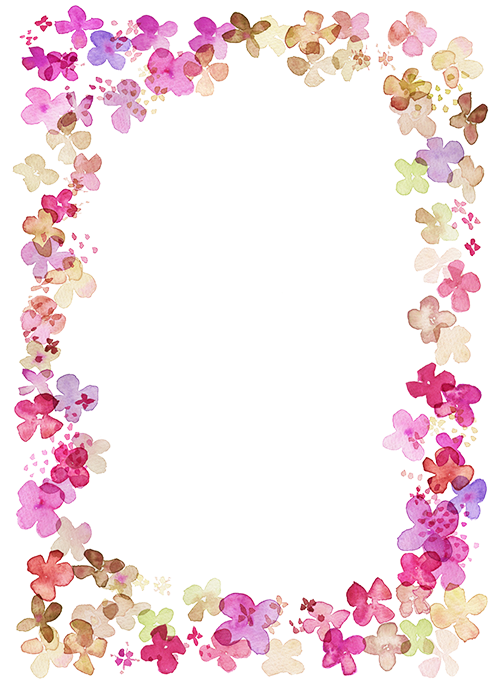夜の十一時過ぎ。
港の倉庫街は、昼間の喧騒が嘘のように静まり返っている。 街灯の光も届かず、ただ月だけが冷たく白い顔を覗かせている。
古びた倉庫の床には、まだ血の匂いが残っていた。
白髪の男——泣き虫の白者。 体中が腫れ上がり、肋骨が何本か折れているのは明らかだった。 息は浅く、途切れ途切れ。それでも、指先だけは微かに動いている。 まるで、まだ何かを掴もうとしているように。
ガラガラ……と、シャッターがわずかに持ち上げられる音。
「はぁ……めんどくせぇ」
低い、投げやりな声が響いた。
入ってきたのは、灰色のコートを羽織った長身の男。 白く跳ねた髪、白い瞳、顔立ちは整っているが、どこか苛立たしげで、眠そうな目をしている。
如月——白城上級保安官。
今は完全にサボり中だ。片手にコンビニのビニール袋。中には、さっき買ったばかりの激アツおしるこ(缶じゃなくてカップのやつ)が、まだ湯気を立てている。
「こんな時間に開いてるコンビニとか、逆に怪しくね? ……まぁいいか」
如月は倉庫の隅に腰を下ろそうとして——そこで初めて、床に転がっている白い塊に気付いた。
「……なんだコイツ」
近づいて、軽くしゃがむ。 月明かりに照らされた白者の顔を見て、如月は一瞬だけ眉をひそめた。
「死んでんのか?」
返事はない。
「生きてんならなんか言えよ」
やはり、無反応。
如月は舌打ちして、立ち上がった。
「邪魔くせぇな……ッ」
そう呟きながら、手に持っていたカップおしるこの蓋をパキッと開ける。 中から立ち上る湯気が、冷え切った倉庫の空気をわずかに温めた。
「……熱いままの方が効くかもしんねぇな」
そして——
思いっきり、白者の頭めがけて、ぶちまけた。
ドバァッ!
熱々の小豆と白玉と餡が、白い髪の上にべっとりと降り注ぐ。 湯気がシュウシュウと立ち上がり、焦げた血の匂いと甘ったるい小豆の香りが混じり合った。
「……っ」
白者の体が、ピクッと小さく震えた。
だが、それだけだ。意識があるのかすら怪しい。
「チッ」
如月は舌打ちをもう一度。 空になったカップを適当に床に投げ捨てると、白者の脇腹に、黒いブーツのつま先を軽く蹴り入れた。
ドンッ。
「死ぬなら死ねよ。邪魔ァ」
吐き捨てるように言って、如月はくるりと背を向けた。
コートの裾が翻り、赤いラインが月明かりに一瞬だけ光る。 軍帽子のつばに付いた赤いラインも、まるで血のように見えた。
シャッターをくぐり抜け、足音が遠ざかっていく。
倉庫の中には、再び静寂が戻った。
ただ——
白者の白い髪に絡まった熱い餡が、ゆっくりと、滴り落ちていく。
その滴が、血溜まりに落ちて、小さな波紋を広げたとき。
白者の指が、もう一度、かすかに、握りしめられた。
まだ、終わっていない。
夜は、まだ長い。
港の倉庫街は、昼間の喧騒が嘘のように静まり返っている。 街灯の光も届かず、ただ月だけが冷たく白い顔を覗かせている。
古びた倉庫の床には、まだ血の匂いが残っていた。
白髪の男——泣き虫の白者。 体中が腫れ上がり、肋骨が何本か折れているのは明らかだった。 息は浅く、途切れ途切れ。それでも、指先だけは微かに動いている。 まるで、まだ何かを掴もうとしているように。
ガラガラ……と、シャッターがわずかに持ち上げられる音。
「はぁ……めんどくせぇ」
低い、投げやりな声が響いた。
入ってきたのは、灰色のコートを羽織った長身の男。 白く跳ねた髪、白い瞳、顔立ちは整っているが、どこか苛立たしげで、眠そうな目をしている。
如月——白城上級保安官。
今は完全にサボり中だ。片手にコンビニのビニール袋。中には、さっき買ったばかりの激アツおしるこ(缶じゃなくてカップのやつ)が、まだ湯気を立てている。
「こんな時間に開いてるコンビニとか、逆に怪しくね? ……まぁいいか」
如月は倉庫の隅に腰を下ろそうとして——そこで初めて、床に転がっている白い塊に気付いた。
「……なんだコイツ」
近づいて、軽くしゃがむ。 月明かりに照らされた白者の顔を見て、如月は一瞬だけ眉をひそめた。
「死んでんのか?」
返事はない。
「生きてんならなんか言えよ」
やはり、無反応。
如月は舌打ちして、立ち上がった。
「邪魔くせぇな……ッ」
そう呟きながら、手に持っていたカップおしるこの蓋をパキッと開ける。 中から立ち上る湯気が、冷え切った倉庫の空気をわずかに温めた。
「……熱いままの方が効くかもしんねぇな」
そして——
思いっきり、白者の頭めがけて、ぶちまけた。
ドバァッ!
熱々の小豆と白玉と餡が、白い髪の上にべっとりと降り注ぐ。 湯気がシュウシュウと立ち上がり、焦げた血の匂いと甘ったるい小豆の香りが混じり合った。
「……っ」
白者の体が、ピクッと小さく震えた。
だが、それだけだ。意識があるのかすら怪しい。
「チッ」
如月は舌打ちをもう一度。 空になったカップを適当に床に投げ捨てると、白者の脇腹に、黒いブーツのつま先を軽く蹴り入れた。
ドンッ。
「死ぬなら死ねよ。邪魔ァ」
吐き捨てるように言って、如月はくるりと背を向けた。
コートの裾が翻り、赤いラインが月明かりに一瞬だけ光る。 軍帽子のつばに付いた赤いラインも、まるで血のように見えた。
シャッターをくぐり抜け、足音が遠ざかっていく。
倉庫の中には、再び静寂が戻った。
ただ——
白者の白い髪に絡まった熱い餡が、ゆっくりと、滴り落ちていく。
その滴が、血溜まりに落ちて、小さな波紋を広げたとき。
白者の指が、もう一度、かすかに、握りしめられた。
まだ、終わっていない。
夜は、まだ長い。