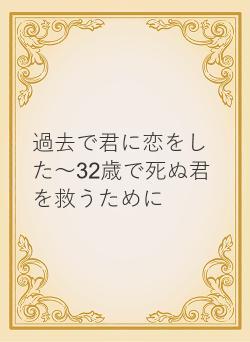彼女の告白が静かに終わったあと、部屋の空気はしんとしたまま動かなかった。男は何も言えずにいた。時計の音も、外の風の音も、どこか遠い世界のもののように思えた。
彼女がここにいられないという現実。戻らなければならない世界があるという事実。それが胸の奥にじわじわと広がっていく。まるで冷たい水が肌の下に染み込むように。
それでも男は、彼女の言葉をすぐには信じ切ることができなかった。「人魚」だとか「海の国」だとか、夢のような話だと思った。けれど、その目を見れば、疑う余地などどこにもなかった。あの静けさは、物語の中の嘘には宿らない。
じゃあ、自分はどうするのか――
彼女と別れて、この町で、これまでどおりに日々を続けていくのか。仕事をして、帰って、夜になったらまた海を眺めるのか。そう思った瞬間、胸の奥から不意に何かがこみ上げてきた。
彼女のいない日々を思った。あの夕暮れに立っていた姿。巻貝を拾ってポケットにしまった手のうごき。波を見つめていた横顔。なぜかその一つひとつが、ありありと浮かんでは、心を締めつけた。
もう、あの目を見ないで暮らしていくなんて無理だと、男は思った。
たとえそれがどんな場所でも、たとえ自分が何も知らない世界でも、それでも彼女と一緒にいたい。それだけが、今の自分にとっての真実だった。
「……じゃあ、俺も行くよ」
その言葉は、声というよりも、胸の奥からしぼり出した息のようだった。彼女の横顔が、ふと動いた。少しだけ驚いたように、でもすぐに優しく微笑んで、彼女は首を横に振った。
「それはできないの」
男は彼女を見つめた。目の奥に浮かぶ不安と願いが、その瞳にそのまま映っているようだった。
「どうして? 一緒にいられないなら、そんなの……」
言葉を途中で止めた。彼女は静かにうなずいた。
「海の国は、あなたが思っているような場所じゃないの。そこは私たちにとっては故郷だけど、人間が生きていける場所じゃない。空気も、光も、重さも……すべてが違うの。あなたの身体は、きっと長くはもたない」
男は何かを言い返そうとしたが、声にならなかった。ただ、胸の奥がじんじんと痛んだ。自分がなぜここまで強く彼女に惹かれているのか、その理由すらまだはっきりとはわからない。それでも、彼女と離れることだけは受け入れがたかった。
彼女は男の手をそっと握った。その手は海の水に濡れたように、少しだけ冷たかった。
「あなたが来たいと思ってくれるのは、うれしい。でも、それはできないの。だから……お願い、ここで生きていて」
その声には、決して揺るがないものがあった。彼女自身もまた苦しんでいるのだと、男は悟った。自分を拒むためではなく、守ろうとしているのだと。
男は、静かに目を伏せた。すぐには何も言えなかった。ただ彼女の手のぬくもりだけを、しっかりと感じていた。
彼女がここにいられないという現実。戻らなければならない世界があるという事実。それが胸の奥にじわじわと広がっていく。まるで冷たい水が肌の下に染み込むように。
それでも男は、彼女の言葉をすぐには信じ切ることができなかった。「人魚」だとか「海の国」だとか、夢のような話だと思った。けれど、その目を見れば、疑う余地などどこにもなかった。あの静けさは、物語の中の嘘には宿らない。
じゃあ、自分はどうするのか――
彼女と別れて、この町で、これまでどおりに日々を続けていくのか。仕事をして、帰って、夜になったらまた海を眺めるのか。そう思った瞬間、胸の奥から不意に何かがこみ上げてきた。
彼女のいない日々を思った。あの夕暮れに立っていた姿。巻貝を拾ってポケットにしまった手のうごき。波を見つめていた横顔。なぜかその一つひとつが、ありありと浮かんでは、心を締めつけた。
もう、あの目を見ないで暮らしていくなんて無理だと、男は思った。
たとえそれがどんな場所でも、たとえ自分が何も知らない世界でも、それでも彼女と一緒にいたい。それだけが、今の自分にとっての真実だった。
「……じゃあ、俺も行くよ」
その言葉は、声というよりも、胸の奥からしぼり出した息のようだった。彼女の横顔が、ふと動いた。少しだけ驚いたように、でもすぐに優しく微笑んで、彼女は首を横に振った。
「それはできないの」
男は彼女を見つめた。目の奥に浮かぶ不安と願いが、その瞳にそのまま映っているようだった。
「どうして? 一緒にいられないなら、そんなの……」
言葉を途中で止めた。彼女は静かにうなずいた。
「海の国は、あなたが思っているような場所じゃないの。そこは私たちにとっては故郷だけど、人間が生きていける場所じゃない。空気も、光も、重さも……すべてが違うの。あなたの身体は、きっと長くはもたない」
男は何かを言い返そうとしたが、声にならなかった。ただ、胸の奥がじんじんと痛んだ。自分がなぜここまで強く彼女に惹かれているのか、その理由すらまだはっきりとはわからない。それでも、彼女と離れることだけは受け入れがたかった。
彼女は男の手をそっと握った。その手は海の水に濡れたように、少しだけ冷たかった。
「あなたが来たいと思ってくれるのは、うれしい。でも、それはできないの。だから……お願い、ここで生きていて」
その声には、決して揺るがないものがあった。彼女自身もまた苦しんでいるのだと、男は悟った。自分を拒むためではなく、守ろうとしているのだと。
男は、静かに目を伏せた。すぐには何も言えなかった。ただ彼女の手のぬくもりだけを、しっかりと感じていた。