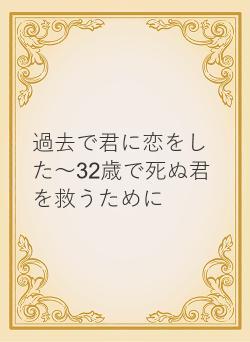朝方、風が窓を静かに叩いていた。眠っていた男はその音で目を覚ました。隣を見ると、彼女はもう起きていて、小さなキッチンの方に背を向けて立っていた。
背中越しにわかるその気配は、静かで、どこか遠くを見つめているようだった。
男は声をかけようとしたが、なぜか言葉が喉の奥で止まった。ただその背中に、何かが遠ざかろうとしているような、説明のつかない予感があった。
彼女はやがて振り返り、穏やかな笑みを浮かべて、男の前に腰を下ろした。そして、ほんの少し間を置いてから、口を開いた。
「……あなたに話さなきゃいけないことがあるの」
その声には震えも強さもなかった。ただ、すべてを受け入れようとしているような、静けさだけがあった。
男はうなずいた。心のどこかで、何か大切なことが今ここで告げられるのだと悟っていた。
彼女は目を伏せ、少しの間、言葉を選ぶように黙っていた。そして、手のひらをそっとひらくと、その中心に、小さな鱗のかけらを乗せて見せた。
それはまるで光を吸い込んでいるかのような、不思議な青と銀のあいだの色をしていた。人工のものにはない、深い海のような輝きだった。
「私、人間じゃないの」
かのじょはそう言って、まっすぐに男の目を見た。
「……私は、人魚なの。もともとは、海の底にある国で暮らしてたの。でも、どうしても、地上に来たかった。ほんの少しのあいだだけでいいから、人の世界を見てみたかった」
男は言葉を失った。ただ、彼女の目から目を逸らすことはなかった。
「本当は、誰にも言ってはいけないの。でも、あなたには……ちゃんと話しておきたかった。私は……もうすぐ、海に帰らなければいけないの」
その言葉は静かに響きながらも、確かに男の胸を打った。
男はその鱗を見つめながら、胸の奥に重く、ゆっくりと沈んでいくような痛みを覚えた。
彼女はそっと鱗を閉じるように手のひらを握りしめると、かすかに微笑んだ。
「でも、あなたと過ごせた時間は、本当に……うれしかった。あの波打ち際で、あなたが声をかけてくれたときから、きっと、こうなることは決まってたのかもしれないね」
その声には、涙の代わりに、深い名残惜しさがにじんでいた。
背中越しにわかるその気配は、静かで、どこか遠くを見つめているようだった。
男は声をかけようとしたが、なぜか言葉が喉の奥で止まった。ただその背中に、何かが遠ざかろうとしているような、説明のつかない予感があった。
彼女はやがて振り返り、穏やかな笑みを浮かべて、男の前に腰を下ろした。そして、ほんの少し間を置いてから、口を開いた。
「……あなたに話さなきゃいけないことがあるの」
その声には震えも強さもなかった。ただ、すべてを受け入れようとしているような、静けさだけがあった。
男はうなずいた。心のどこかで、何か大切なことが今ここで告げられるのだと悟っていた。
彼女は目を伏せ、少しの間、言葉を選ぶように黙っていた。そして、手のひらをそっとひらくと、その中心に、小さな鱗のかけらを乗せて見せた。
それはまるで光を吸い込んでいるかのような、不思議な青と銀のあいだの色をしていた。人工のものにはない、深い海のような輝きだった。
「私、人間じゃないの」
かのじょはそう言って、まっすぐに男の目を見た。
「……私は、人魚なの。もともとは、海の底にある国で暮らしてたの。でも、どうしても、地上に来たかった。ほんの少しのあいだだけでいいから、人の世界を見てみたかった」
男は言葉を失った。ただ、彼女の目から目を逸らすことはなかった。
「本当は、誰にも言ってはいけないの。でも、あなたには……ちゃんと話しておきたかった。私は……もうすぐ、海に帰らなければいけないの」
その言葉は静かに響きながらも、確かに男の胸を打った。
男はその鱗を見つめながら、胸の奥に重く、ゆっくりと沈んでいくような痛みを覚えた。
彼女はそっと鱗を閉じるように手のひらを握りしめると、かすかに微笑んだ。
「でも、あなたと過ごせた時間は、本当に……うれしかった。あの波打ち際で、あなたが声をかけてくれたときから、きっと、こうなることは決まってたのかもしれないね」
その声には、涙の代わりに、深い名残惜しさがにじんでいた。