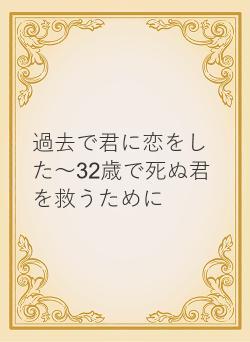海には月の光がやわらかく差していた。波は穏やかで、風もほとんどなく、空にはいくつかの星がにじむように浮かんでいた。
ふたりは浜辺をゆっくりと歩いていた。言葉はほとんどなかったが、それでも不思議と会話が続いているような心地がした。足音が砂を踏むたび、互いの存在がすぐそばにあることを確かめているようだった。
やがて、女が立ち止まった。男も足を止める。ふたりのあいだに短い沈黙が流れたあと、彼女が顔を上げて男を見つめた。月明かりに照らされたその目には、悲しみも、戸惑いも、すでになかった。ただ、深い静けさと、かすかな熱が宿っていた。
風が彼女の髪をかすかに揺らした。男は何も言わず、そっと彼女の肩に手を置いた。彼女もまた何も言わず、その手に身を預けるように、静かに男の胸に顔を埋めた。
しばらくのあいだ、ふたりはそうしていた。ただ波の音だけが背後で繰り返し、空には雲がゆるやかに流れていた。
その一瞬のぬくもりの中に、男は胸の奥からすっと湧き上がるものを感じていた。言葉よりも先に、そっと差し出した手に、彼女が何のためらいもなく触れた。
そしてふたりは、夜の静けさのなかを寄り添いながら歩き出した。
男の住む小さな家は、海辺からそれほど離れていない。家にたどり着くころには、月は高く、風はさらに穏やかになっていた。
扉を閉めたあとも、しばらくふたりは言葉を交わさなかった。けれどそれは、言葉がいらないという確かな感覚だった。
たとえば、夜がどれほど長くても、波の音がどれほど遠くから響いても――ふたりの間にあるものは、もう確かだった。
その夜、波音はいつになく静かだった。風はそっと窓辺をなで、星は雲の間から淡く瞬いていた。どこかで遠く、小さな貝殻が転がる音がした。すべてが、静かにひとつへと結ばれていくような夜だった。
ふたりは浜辺をゆっくりと歩いていた。言葉はほとんどなかったが、それでも不思議と会話が続いているような心地がした。足音が砂を踏むたび、互いの存在がすぐそばにあることを確かめているようだった。
やがて、女が立ち止まった。男も足を止める。ふたりのあいだに短い沈黙が流れたあと、彼女が顔を上げて男を見つめた。月明かりに照らされたその目には、悲しみも、戸惑いも、すでになかった。ただ、深い静けさと、かすかな熱が宿っていた。
風が彼女の髪をかすかに揺らした。男は何も言わず、そっと彼女の肩に手を置いた。彼女もまた何も言わず、その手に身を預けるように、静かに男の胸に顔を埋めた。
しばらくのあいだ、ふたりはそうしていた。ただ波の音だけが背後で繰り返し、空には雲がゆるやかに流れていた。
その一瞬のぬくもりの中に、男は胸の奥からすっと湧き上がるものを感じていた。言葉よりも先に、そっと差し出した手に、彼女が何のためらいもなく触れた。
そしてふたりは、夜の静けさのなかを寄り添いながら歩き出した。
男の住む小さな家は、海辺からそれほど離れていない。家にたどり着くころには、月は高く、風はさらに穏やかになっていた。
扉を閉めたあとも、しばらくふたりは言葉を交わさなかった。けれどそれは、言葉がいらないという確かな感覚だった。
たとえば、夜がどれほど長くても、波の音がどれほど遠くから響いても――ふたりの間にあるものは、もう確かだった。
その夜、波音はいつになく静かだった。風はそっと窓辺をなで、星は雲の間から淡く瞬いていた。どこかで遠く、小さな貝殻が転がる音がした。すべてが、静かにひとつへと結ばれていくような夜だった。