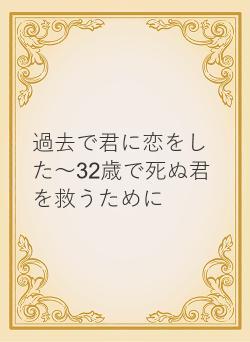しばらく、ふたりの間に言葉はなかった。
海の風が少し強くなったように感じた。波の音も、どこか不安定に耳に届く。遊歩道の明かりがぽつぽつと灯り始める中で、彼女は海の方を見つめたまま動かなかった。けれどその横顔には、どこかぽつんと取り残されたような孤独がにじんでいた。
男はその姿を黙って見ていた。
慰めの言葉とは、何なのだろうと思った。表面的な優しさを並べることはできる。頑張って、無理しないで、大丈夫――そんな言葉を口にすることは、難しくない。でも彼女が抱えている何かは、そんな簡単な言葉で触れていいものではない気がしていた。
それでも、このまま黙っているのは、もっと残酷だと思った。
何を言えばいいのか、正直わからない。ただ、目の前にいる彼女のその心の奥に、ほんの少しでも手を差し伸べたくて、男は息を吸い、そっと言葉を選んだ。
「……たぶん、僕にはあなたが抱えてること、全部はわからないと思います」
彼女がほんの少しだけこちらを見た。驚いたわけでも、警戒したわけでもない。ただ、その声に耳を澄ませるような静かな動きだった。
「それでも、何かに心が押し潰されそうなときに、誰かがそばにいるだけで少しだけ楽になることって……あると思うんです」
言いながら、自分でもどこか頼りないと思った。自分のような人間が、彼女の悲しみに触れていいのか。かえって傷つけてしまうのではないか。でも、それでも、この想いは嘘じゃない。
「僕が、そばにいてもいいですか」
その言葉が出た瞬間、男の心は強く鼓動を打った。海の匂いと夜気の冷たさの中で、その鼓動だけがやけに生々しく感じられた。
彼女は返事をしなかった。けれどその肩が、わずかに震えた。
男はそれに気づいて、一歩だけ、ほんの一歩だけ彼女に近づいた。そして、ためらいがちに自分の上着を脱ぐと、そっと彼女の肩にかけた。驚かせないように、ゆっくりと、風が吹きすぎるのをやわらげるように。
彼女は肩越しに男を見た。目が少し潤んでいた。けれどその瞳には、拒絶も、恐れもなかった。
「……ありがとう」
ぽつりとこぼれたその言葉は、夜の波間に溶けていった。男の胸の奥で、それは確かなぬくもりとなって残った。
彼女が何を抱えているのかは、まだわからない。きっとこれからも、全部を知ることはできないかもしれない。それでも、彼女の心に少しでも寄り添いたい――そう強く思った。慰めとは、与えるものではなく、ただそこに居ることなのかもしれないと、男は初めて思った。
海の風が少し強くなったように感じた。波の音も、どこか不安定に耳に届く。遊歩道の明かりがぽつぽつと灯り始める中で、彼女は海の方を見つめたまま動かなかった。けれどその横顔には、どこかぽつんと取り残されたような孤独がにじんでいた。
男はその姿を黙って見ていた。
慰めの言葉とは、何なのだろうと思った。表面的な優しさを並べることはできる。頑張って、無理しないで、大丈夫――そんな言葉を口にすることは、難しくない。でも彼女が抱えている何かは、そんな簡単な言葉で触れていいものではない気がしていた。
それでも、このまま黙っているのは、もっと残酷だと思った。
何を言えばいいのか、正直わからない。ただ、目の前にいる彼女のその心の奥に、ほんの少しでも手を差し伸べたくて、男は息を吸い、そっと言葉を選んだ。
「……たぶん、僕にはあなたが抱えてること、全部はわからないと思います」
彼女がほんの少しだけこちらを見た。驚いたわけでも、警戒したわけでもない。ただ、その声に耳を澄ませるような静かな動きだった。
「それでも、何かに心が押し潰されそうなときに、誰かがそばにいるだけで少しだけ楽になることって……あると思うんです」
言いながら、自分でもどこか頼りないと思った。自分のような人間が、彼女の悲しみに触れていいのか。かえって傷つけてしまうのではないか。でも、それでも、この想いは嘘じゃない。
「僕が、そばにいてもいいですか」
その言葉が出た瞬間、男の心は強く鼓動を打った。海の匂いと夜気の冷たさの中で、その鼓動だけがやけに生々しく感じられた。
彼女は返事をしなかった。けれどその肩が、わずかに震えた。
男はそれに気づいて、一歩だけ、ほんの一歩だけ彼女に近づいた。そして、ためらいがちに自分の上着を脱ぐと、そっと彼女の肩にかけた。驚かせないように、ゆっくりと、風が吹きすぎるのをやわらげるように。
彼女は肩越しに男を見た。目が少し潤んでいた。けれどその瞳には、拒絶も、恐れもなかった。
「……ありがとう」
ぽつりとこぼれたその言葉は、夜の波間に溶けていった。男の胸の奥で、それは確かなぬくもりとなって残った。
彼女が何を抱えているのかは、まだわからない。きっとこれからも、全部を知ることはできないかもしれない。それでも、彼女の心に少しでも寄り添いたい――そう強く思った。慰めとは、与えるものではなく、ただそこに居ることなのかもしれないと、男は初めて思った。