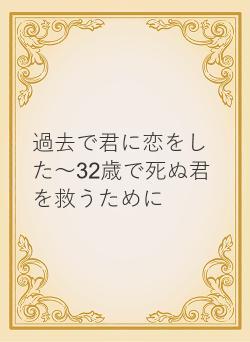砂浜をしばらく歩いたところで、彼女はふと立ち止まり、もう一度ゆっくりと海に目を向けた。潮の満ち引きが波の音に揺らぎをもたらしていた。空はすでに群青に染まりはじめていて、浜辺には、誰のものとも知れない足跡がところどころに残っていた。
男は隣に立ち、言葉を探していた。
彼女の「家族に不幸があった」という言葉が、何度も頭の中で繰り返されていた。その声があまりにも静かで、あまりにも遠かったせいか、ただ聞いたというだけでは済まされない何かが、胸の奥に残っていた。
彼女のことは、まだほとんど知らない。名前すら聞いていない。なのに、彼女の悲しみの一部に触れてしまったような気がして、それを見過ごすことができなかった。
「……無理に聞くつもりはないんですけど」
波音にかき消されないよう、男は少し声を張った。
「何か……僕にできること、ありませんか」
彼女は顔をこちらに向けなかった。ただ海の方を見つめたまま、ほんの少しだけ首を横に振った。
それだけで、男は何かを拒まれたような気がして、心の中がざわついた。まだ何も始まっていないのに、もう終わってしまいそうな、そんな不安が喉元までせり上がってくる。
「もし、誰かに話すだけでも少し楽になるなら……僕、聞くことくらいはできますから」
自分でも、なぜこんなにまっすぐな言葉を選んでいるのかわからなかった。ただ、彼女の顔に浮かんだ寂しさが、自分の中にもじんわりと染み込んできて、どうにかしたいと思わずにはいられなかった。
彼女はようやく、ゆっくりと顔をこちらに向けた。その表情は、先ほどよりも穏やかだったが、同時に何かを諦めているような静けさもまとっていた。
「ありがとう。でも……それでも、話せないことってあるんです」
その声はやはり小さかったが、はっきりとした意志がこもっていた。断るというより、哀しみを抱いたまま、それを他人に明かせないことへの戸惑いが混じっていた。
男はうなずくしかなかった。
わかっていた。彼女がその悲しみを口にするのがどれほど難しいことなのかは、わずかな言葉の重みだけでも察することができた。だが、それでもどこかで、自分には彼女を救えるのではないかという、根拠のない希望があった。
それが否定されたことに対する落胆と、自分の無力さを知った恥ずかしさが、胸の奥で静かにぶつかり合っていた。
「……すみません」
なぜか、男の方がそう言っていた。
「ううん。……謝らないで。あなたの気持ち、うれしかったです」
彼女の笑みは柔らかく、そしてどこか遠かった。まるで、いまこの場にいるはずなのに、少しずつ海の向こうへと気持ちが引かれていっているかのようだった。
男はその横顔を見つめながら、波の音が今までよりも冷たく聞こえるのを感じていた。そして、自分の言葉では到底届かない場所に、この人の心の一部があることを、初めてはっきりと知った。
男は隣に立ち、言葉を探していた。
彼女の「家族に不幸があった」という言葉が、何度も頭の中で繰り返されていた。その声があまりにも静かで、あまりにも遠かったせいか、ただ聞いたというだけでは済まされない何かが、胸の奥に残っていた。
彼女のことは、まだほとんど知らない。名前すら聞いていない。なのに、彼女の悲しみの一部に触れてしまったような気がして、それを見過ごすことができなかった。
「……無理に聞くつもりはないんですけど」
波音にかき消されないよう、男は少し声を張った。
「何か……僕にできること、ありませんか」
彼女は顔をこちらに向けなかった。ただ海の方を見つめたまま、ほんの少しだけ首を横に振った。
それだけで、男は何かを拒まれたような気がして、心の中がざわついた。まだ何も始まっていないのに、もう終わってしまいそうな、そんな不安が喉元までせり上がってくる。
「もし、誰かに話すだけでも少し楽になるなら……僕、聞くことくらいはできますから」
自分でも、なぜこんなにまっすぐな言葉を選んでいるのかわからなかった。ただ、彼女の顔に浮かんだ寂しさが、自分の中にもじんわりと染み込んできて、どうにかしたいと思わずにはいられなかった。
彼女はようやく、ゆっくりと顔をこちらに向けた。その表情は、先ほどよりも穏やかだったが、同時に何かを諦めているような静けさもまとっていた。
「ありがとう。でも……それでも、話せないことってあるんです」
その声はやはり小さかったが、はっきりとした意志がこもっていた。断るというより、哀しみを抱いたまま、それを他人に明かせないことへの戸惑いが混じっていた。
男はうなずくしかなかった。
わかっていた。彼女がその悲しみを口にするのがどれほど難しいことなのかは、わずかな言葉の重みだけでも察することができた。だが、それでもどこかで、自分には彼女を救えるのではないかという、根拠のない希望があった。
それが否定されたことに対する落胆と、自分の無力さを知った恥ずかしさが、胸の奥で静かにぶつかり合っていた。
「……すみません」
なぜか、男の方がそう言っていた。
「ううん。……謝らないで。あなたの気持ち、うれしかったです」
彼女の笑みは柔らかく、そしてどこか遠かった。まるで、いまこの場にいるはずなのに、少しずつ海の向こうへと気持ちが引かれていっているかのようだった。
男はその横顔を見つめながら、波の音が今までよりも冷たく聞こえるのを感じていた。そして、自分の言葉では到底届かない場所に、この人の心の一部があることを、初めてはっきりと知った。