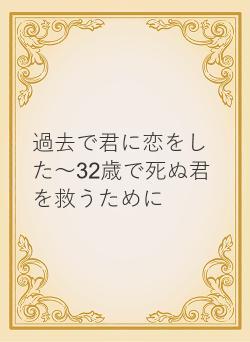ふと、彼女のポケットから何かが滑り落ちた。
それは、さっき拾い上げた小さな巻貝だった。夕映えを受けて、濡れたような光を放ちながら砂の上に転がった。
「あっ、落としましたよ」
男が声をかけてしゃがみこみ、巻貝を拾い上げる。手のひらの上で転がるその殻は、わずかに温かく、先ほどまで彼女の手のひらにあったことを想像させた。
「ありがとう」
彼女は受け取ると、今度は両手で大切そうに包み込んだ。男は何気ないやりとりのはずなのに、どこか深く触れてはいけないものに触れてしまったような感覚に囚われた。
それは、彼女の目の奥に漂う陰りのせいかもしれなかった。どれほど柔らかく笑っていても、その笑みの奥に、どこか「遠くを見ているような」気配があった。
少しの沈黙のあと、男はなるべく気取らずに、静かに口を開いた。
「……その貝、気に入ったんですね」
「ええ。なんとなく、見つけたときから、手放したくなかったんです。……海の中で、ずっと待っていたみたいで」
そう言って、彼女は目を伏せた。その声音には、どこか物悲しい響きがあった。
男は言葉を選びながら歩を進めた。彼女の言葉に引っかかる何かがあった。“ずっと待っていた”という表現に、無意識とは思えないような重みを感じたのだ。
「……さっき、海を見ていたとき、少し寂しそうに見えました」
彼女は驚いたように横目で彼を見たが、否定はしなかった。むしろ、その視線の奥に、ようやく理解してもらえたかのような、わずかな安堵が浮かんだ。
「そうかもしれません」
彼女はぽつりとそう言い、少し立ち止まって、波の方を見やった。男も隣に立ち、彼女の表情を盗み見る。頬に流れる髪が風に揺れ、目元にかかった影が、彼女の心の奥をさらに遠く感じさせた。
「最近……家族に不幸があったんです。まだ、うまく言葉にできなくて」
波音にまぎれるように、小さくそう告げられた。男は一瞬、何かを返そうとして口を開いたが、結局言葉を飲み込んだ。あまりに軽い言葉では彼女の悲しみに触れられない気がしたし、踏み込みすぎても彼女を傷つけるだけかもしれなかった。
「……そうだったんですね」
ようやく絞り出したその一言は、頼りないほど静かだったが、彼女は軽くうなずいた。
「……すみません、こんな話」
「謝らないでください。……話してくれて、ありがとうございます」
風が少し強くなり、砂を巻き上げた。彼女の髪が宙に揺れ、男の胸元をかすめていく。
男は思った。この人の持つ静かな悲しみが、ただの偶然ではない気がする。だが、それが何なのかは、まだわからない。ただ、もっと知りたいと思った。彼女が見ている“遠く”が、どこにあるのか。
そのとき、どこからか海鳥の声が聞こえて、空を見上げると、暮れかけた空に一羽の影が流れていた。
彼女はふたたび巻貝を見つめ、今度は慎重に、胸のポケットにそっとしまった。
男はそれを見ながら、小さく息を吐いた。この人の悲しみが、ほんのわずかでも軽くなるように、自分にできることがあれば――そんなことを考えていた。
それは、さっき拾い上げた小さな巻貝だった。夕映えを受けて、濡れたような光を放ちながら砂の上に転がった。
「あっ、落としましたよ」
男が声をかけてしゃがみこみ、巻貝を拾い上げる。手のひらの上で転がるその殻は、わずかに温かく、先ほどまで彼女の手のひらにあったことを想像させた。
「ありがとう」
彼女は受け取ると、今度は両手で大切そうに包み込んだ。男は何気ないやりとりのはずなのに、どこか深く触れてはいけないものに触れてしまったような感覚に囚われた。
それは、彼女の目の奥に漂う陰りのせいかもしれなかった。どれほど柔らかく笑っていても、その笑みの奥に、どこか「遠くを見ているような」気配があった。
少しの沈黙のあと、男はなるべく気取らずに、静かに口を開いた。
「……その貝、気に入ったんですね」
「ええ。なんとなく、見つけたときから、手放したくなかったんです。……海の中で、ずっと待っていたみたいで」
そう言って、彼女は目を伏せた。その声音には、どこか物悲しい響きがあった。
男は言葉を選びながら歩を進めた。彼女の言葉に引っかかる何かがあった。“ずっと待っていた”という表現に、無意識とは思えないような重みを感じたのだ。
「……さっき、海を見ていたとき、少し寂しそうに見えました」
彼女は驚いたように横目で彼を見たが、否定はしなかった。むしろ、その視線の奥に、ようやく理解してもらえたかのような、わずかな安堵が浮かんだ。
「そうかもしれません」
彼女はぽつりとそう言い、少し立ち止まって、波の方を見やった。男も隣に立ち、彼女の表情を盗み見る。頬に流れる髪が風に揺れ、目元にかかった影が、彼女の心の奥をさらに遠く感じさせた。
「最近……家族に不幸があったんです。まだ、うまく言葉にできなくて」
波音にまぎれるように、小さくそう告げられた。男は一瞬、何かを返そうとして口を開いたが、結局言葉を飲み込んだ。あまりに軽い言葉では彼女の悲しみに触れられない気がしたし、踏み込みすぎても彼女を傷つけるだけかもしれなかった。
「……そうだったんですね」
ようやく絞り出したその一言は、頼りないほど静かだったが、彼女は軽くうなずいた。
「……すみません、こんな話」
「謝らないでください。……話してくれて、ありがとうございます」
風が少し強くなり、砂を巻き上げた。彼女の髪が宙に揺れ、男の胸元をかすめていく。
男は思った。この人の持つ静かな悲しみが、ただの偶然ではない気がする。だが、それが何なのかは、まだわからない。ただ、もっと知りたいと思った。彼女が見ている“遠く”が、どこにあるのか。
そのとき、どこからか海鳥の声が聞こえて、空を見上げると、暮れかけた空に一羽の影が流れていた。
彼女はふたたび巻貝を見つめ、今度は慎重に、胸のポケットにそっとしまった。
男はそれを見ながら、小さく息を吐いた。この人の悲しみが、ほんのわずかでも軽くなるように、自分にできることがあれば――そんなことを考えていた。